【堺市】めまいとの関連あり! ~ワレンベルグ症候群とは?~
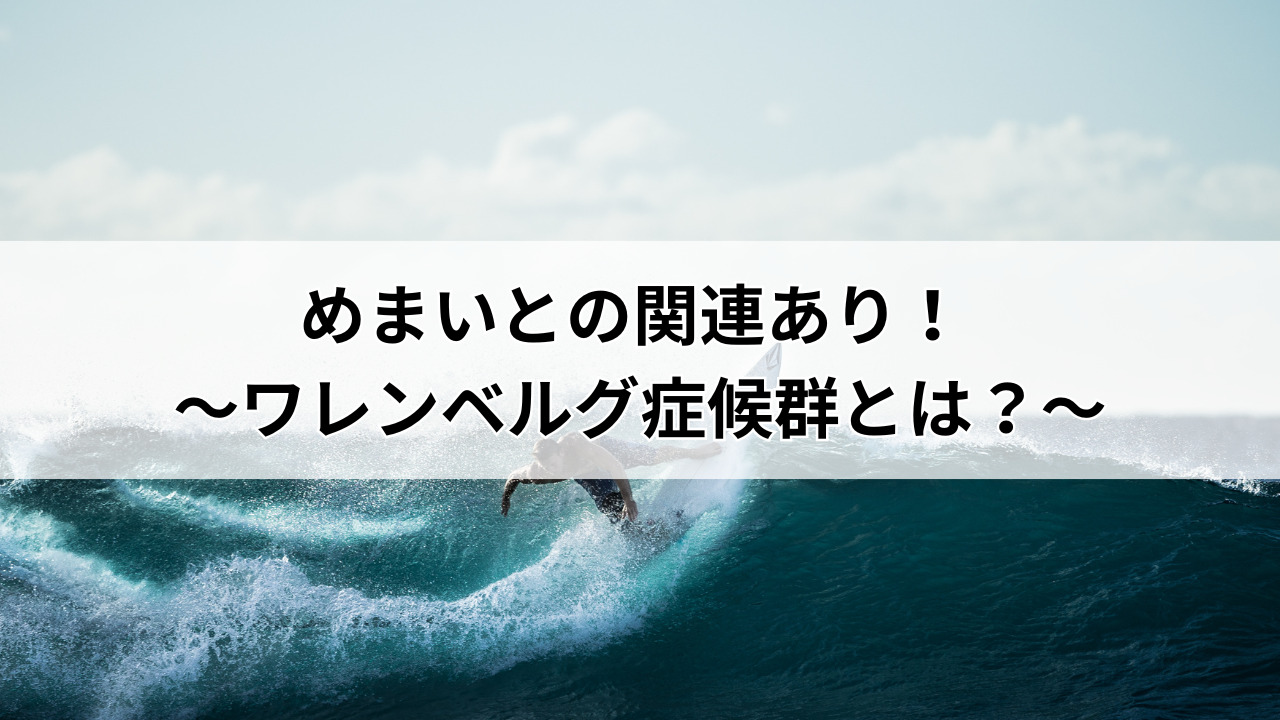
はじめに
こんにちは!
大阪府堺市中区大野芝町にある介護保険を使用しない完全自己負担型の自費リハビリで、脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・パーキンソン病・指定難病など幅広い疾患に対応しており、ロボットリハビリや型にとらわれない最先端のリハビリを受ける事が出来る「脳神経リハビリHL堺」というリハビリセンターで勤務する理学療法士です!
退院後も「少しでも元の生活に近づきたい」「自分の体を理解したい」と願う方に向けて、今回はワレンベルグ症候群という神経障害について詳しく解説します。
特に「めまい」や「ふらつき」が続いている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
- ワレンベルグ症候群とは?
- 主な症状とその影響
- 原因と診断の流れ
- めまいのメカニズムと特徴
- 症状の具体例
- リハビリテーションの重要性と内容
- 退院後にできるセルフケアのヒント

ワレンベルグ症候群とは?
ワレンベルグ症候群(Wallenberg syndrome)は、脳の延髄(えんずい)と呼ばれる部位の外側に血流が届かなくなることで発生する脳梗塞の一種です。
この延髄は、呼吸や心拍の調整、嚥下、バランス感覚など、生命維持や日常動作に関わる多くの機能を担っています。
この症候群は主に椎骨動脈(ついこつどうみゃく)や後下小脳動脈(こうかしょうのうどうみゃく)という血管が詰まることで起こります。
これにより、延髄の周辺の神経や組織が障害を受け、さまざまな症状が出現します。
主な症状とその影響
ワレンベルグ症候群には以下のような症状が見られますが、すべての人に同じ症状が出るわけではありません。
それぞれの状態に応じた対応が必要になります。
-
嚥下障害(えんげしょうがい)
最もよく見られる症状の一つが食べ物や飲み物をうまく飲み込めないという障害です。
これは延髄にある嚥下に関わる神経がダメージを受けるためです。
重度になると誤嚥による肺炎のリスクが高まるため、専門的なリハビリや栄養管理が重要です。 -
めまいとバランス障害
めまいはワレンベルグ症候群の代表的な症状の一つで、「自分が回っている感じ」や「地面が揺れている感じ」として感じることがあります。
これは延髄や小脳がバランスを司る神経と密接に関わっているために起こります。
歩行や起立時にふらつくことも多く、転倒のリスクが高まります。 -
目の異常(眼振など)
視界が揺れたり、目が勝手に動いてしまう「眼振(がんしん)」という症状が出ることがあります。
これも平衡感覚と関連しており、視覚情報と身体の動きの不一致からさらなるめまいを引き起こすことがあります。 -
感覚の左右差
顔の片側の感覚が鈍くなったり、体の片側だけが「痛みや温度を感じにくい」といった症状もよく見られます。
これは、延髄を通る神経が一部遮断されるためで、日常生活での注意力が必要になります。
原因と診断の流れ
ワレンベルグ症候群の原因は、主に以下のような要素が関与しています。
- 脳梗塞:血のかたまり(血栓)が血管を塞ぎ、脳の一部に血液が届かなくなる。
- 動脈解離(どうみゃくかいり):首の外傷や無理な動きなどで血管が裂け、血流が止まる。
- 動脈硬化:高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病が関係し、血管が狭くなる。
診断は、MRIやCTといった画像診断を用いて脳の血流状態を確認することによって行われます。
加えて、症状の出方や既往歴、身体所見などから総合的に判断されます。

めまいのメカニズムと特徴
ワレンベルグ症候群によるめまいには、いくつかの医学的背景があります。
-
前庭神経の障害
耳の奥には「前庭(ぜんてい)」というバランスを感知する部分がありますが、これとつながる前庭神経が延髄を通っています。
この神経が障害を受けることで、脳がうまくバランス情報を処理できなくなり、めまいを感じます。 -
小脳の関与
延髄のすぐ近くには小脳があり、こちらも運動の微調整やバランス維持に関与しています。
小脳機能が低下すると、体をまっすぐ保つことが難しくなり、めまいやふらつきを感じるのです。
症状の具体例
- 回転性のめまい:まるで自分や部屋がグルグル回っているような感覚。
- ふらつき:立っているとよろけたり、歩行中に左右にブレたりします。
- 吐き気や嘔吐:激しいめまいが続くと、自律神経にも影響が出て、気分が悪くなることもあります。
リハビリテーションの重要性と内容
ワレンベルグ症候群の回復には、リハビリが欠かせません。
めまいやふらつきに対しては、理学療法士と共に段階的にバランス感覚を再訓練していきます。
-
バランス訓練
めまいやふらつきのある方には、立位保持や歩行練習、姿勢制御訓練が有効です。
バランスボードなどの道具を使い、楽しみながら取り組むことも可能です。 -
眼球運動のトレーニング
眼振などの症状には、視線を一定方向に動かす練習や視覚と頭の動きを一致させるトレーニングを行います。
これにより、視覚と平衡感覚の協調性を高めていきます。 -
前庭リハビリ
前庭神経の働きを補うために、前庭リハビリテーション(Vestibular Rehabilitation)と呼ばれる専門的な運動療法が行われることもあります。
理学療法士の指導のもと、症状に応じた内容で安全に実施されます。

退院後にできるセルフケアのヒント
ワレンベルグ症候群は回復に時間がかかる病気ですが、日々の取り組みで生活の質を改善することができます。
- 疲れすぎないように日常を調整すること
- 転倒予防のための環境整備(手すり、滑り止めマットの設置など)
- 不安な症状があるときは、リハビリスタッフや主治医に相談すること
めまいがある時ほど、「じっとしている」よりも「安全に動いて、慣らしていく」ことが大切です。
理学療法士は、その「安全に動く」ための道筋を一緒に考えるパートナーです。
まとめ
ワレンベルグ症候群は、延髄に血流が届かなくなることで起こる脳梗塞の一種です。
特に「めまい」や「バランス障害」「嚥下障害」などの症状が強く出ることがありますが、早期の治療と継続的なリハビリによって回復は十分に可能です。
症状に不安を感じている方も、まずは「知ること」から始めましょう。
自分の体の状態を理解し、理学療法士などの専門職と一緒に、少しずつ日常生活を取り戻していくことが、回復への一歩となります。
お問い合わせ
-
【堺市中区】脳神経リハビリHL堺に、お気軽にお問い合わせください!
TEL:072-349-7303
-
動画の配信を行っております!
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。