廃用症候群とは?
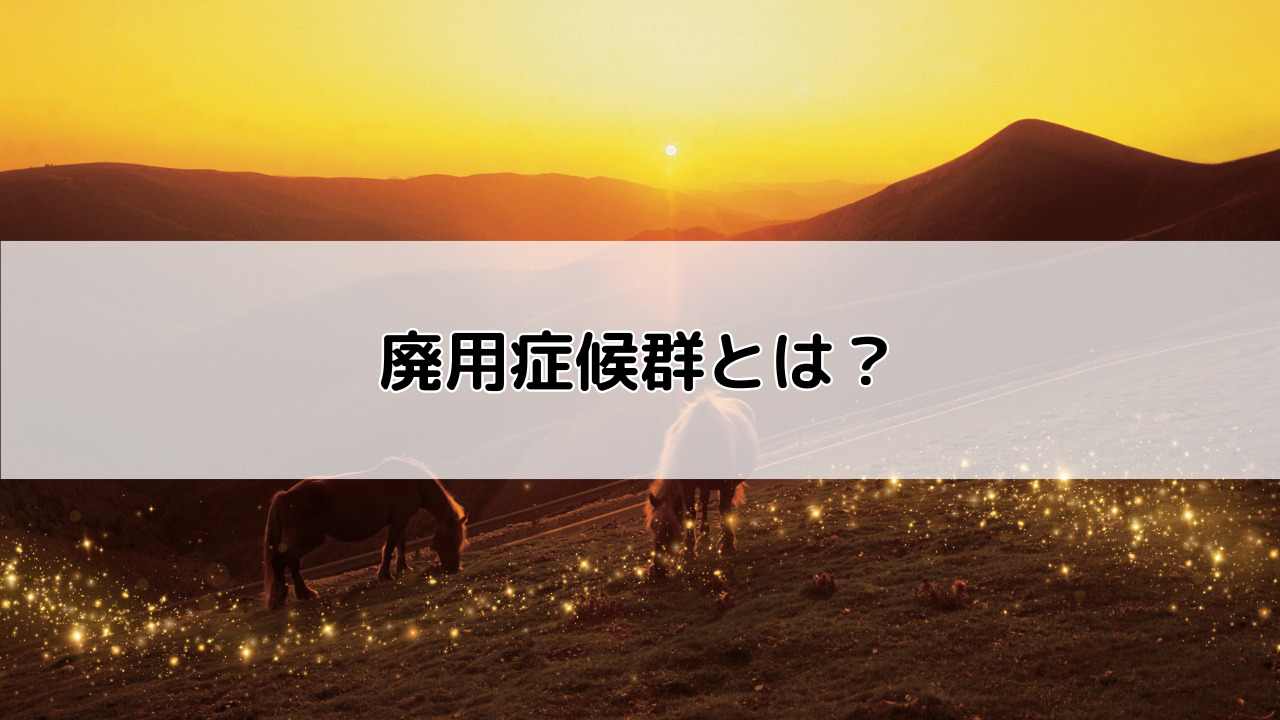
はじめに
私たちの身体は「使わない」と驚くほど早く衰えていきます。
病気やケガで入院したあと、もう一度元気に暮らすためには、ただ休んでいるだけではなく「動くこと」が何より重要です。
そこで知っておいてほしいのが「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)」という言葉です。
この記事では、廃用症候群とは?なぜ起こるのか?予防や改善するには?
リハビリの専門家である理学療法士の視点から分かりやすくお伝えします。
目次
- 廃用症候群とは?
- なぜ廃用症候群になるのか?
- 廃用症候群を予防するためにできること
- リハビリテーションの重要な役割
- 早めのリハビリが回復のカギ

廃用症候群とは?
廃用症候群とは、長期間にわたって身体を動かさない状態が続くことで、筋肉や関節、骨、さらには心の健康にまで影響が出てくる状態のことを指します。
入院中にベッド上で安静にしていたり、退院後に家で動かずに過ごしていたりすると徐々に身体が衰えていきます。
この状態は「生活不活発病」とも呼ばれ、特に高齢者に多く見られます。
身体を動かさない日々が続くと、まず筋肉が細くなり、次第に立ち上がったり歩いたりといった動作が難しくなります。
それだけでなく、関節が固まって動かしづらくなったり、骨の密度が減って骨折しやすくなったり全身にさまざまな問題が起こります。
さらには気持ちの落ち込みや認知機能の低下、心肺機能の低下といった症状まで見られるようになります。
なぜ廃用症候群になるのか?
廃用症候群の大きな原因は「動かないこと」です。
たとえば、手術後に医師の指示で長期間安静にしていたり、転倒を恐れて活動を控えてしまったりして、徐々に身体を使わない状態が続きます。
また、慢性的な疲れや意欲の低下、生活の中で動く習慣がなくなることも原因となります。
動かない日が続くと体力や筋力はあっという間に落ちていきます。
特に高齢者は回復にも時間がかかるため、動かない期間が長くなるほど廃用症候群が進行しやすくなるのです。

廃用症候群を予防するためにできること
廃用症候群は予防が何より大切です。
では、どのようなことを心がければよいのでしょうか?
まず大切なのは、「できるだけ早く動き始めること」です。
入院中であれば、医師やリハビリスタッフと相談のうえ、ベッド上での体操や起き上がる練習からスタートします。
退院後も日常生活の中でこまめに身体を動かすことが大切です。
たとえば、朝起きたら軽くストレッチをする、食事のあとに家の中を歩いてみる、短い距離でも買い物に出かけるといった小さな行動の積み重ねが身体の衰えを防ぎます。
また、週に数回のリハビリや運動指導を受けることで、自分に合った運動を無理なく続けることもできます。
リハビリテーションの重要な役割
廃用症候群の改善や予防には、リハビリテーションが欠かせません。
リハビリとは、ただの運動ではなく、患者一人ひとりの状態に合わせて計画される「体と心の回復プログラム」です。
まず、リハビリでは低下した筋力や体力を回復させる運動療法を行います。
寝たきりの状態から少しずつ身体を起こし、関節を動かしたり筋肉を刺激したりすることで機能の回復を促します。
また、リハビリの中には、立ち上がりや歩行、食事、トイレといった日常生活動作(ADL)を練習することも含まれています。
これは、自立した生活を目指すうえで非常に重要です。
さらに、リハビリには合併症の予防という側面もあります。
例えば、長時間同じ姿勢で寝ていると褥瘡(床ずれ)ができるリスクが高まりますが、定期的な姿勢変換や関節運動によってこれを防ぐことができます。
精神的なケアもリハビリの一部です。
身体を動かすことで気持ちが前向きになり、うつや不安といった症状が軽減されることが分かっています。
リハビリの中で他者と関わる時間が生まれることで、社会とのつながりを感じることもできるでしょう。

早めのリハビリが回復のカギ
廃用症候群の怖いところは、「気づいたときには元に戻すのが難しい」という点です。
だからこそ、予防も治療も「早め」が大切です。
たとえば、手術の翌日からリハビリを開始することで、身体機能の低下を最小限に抑えることができます。
また、退院直後の生活の中でも、リハビリスタッフと連携しながら継続的に身体を動かすことが長期的な健康維持に繋がります。
ロボットを使ったリハビリも、こうした早期の運動支援に非常に効果的です。
自分の力だけでは難しい動作も、ロボットのサポートによってスムーズに実施できるため、安心してリハビリに取り組めます。
まとめ
廃用症候群は、身体を「使わない」ことで進行しますが、「使い続ける」ことで予防や改善ができます。
そしてその鍵を握るのが、リハビリテーションです。
入院中も、退院後の生活も、少しずつでも身体を動かす意識を持つことが、将来の自立した生活を守る第一歩となります。
ご自身やご家族の体調が気になる方は、ぜひ理学療法士や医療スタッフにご相談ください。
一人ひとりの状態に合わせたリハビリを通して、より豊かな生活を取り戻すお手伝いができればと思います。
-
動画の配信を行っております。
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。