【堺市】脳卒中と寝たきりの関係 〜退院後の生活を支えるために知っておきたいこと〜
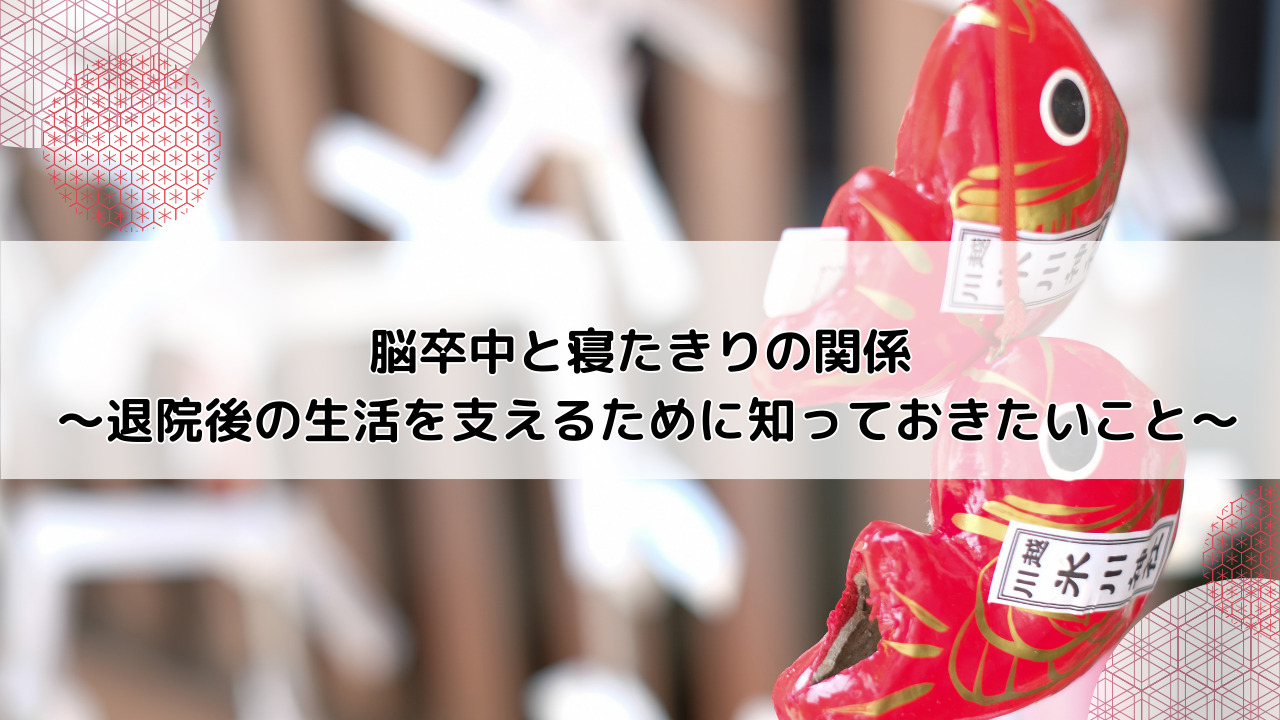
はじめに
こんにちは!
大阪府堺市中区大野芝町にある介護保険を使用しない完全自己負担型の自費リハビリで、脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・パーキンソン病・指定難病など幅広い疾患に対応しており、ロボットリハビリや型にとらわれない最先端のリハビリを受ける事が出来る「脳神経リハビリHL堺」というリハビリセンターで勤務する理学療法士です!
脳卒中は、日本における寝たきりの原因として最も多く報告されている疾患の一つです。
特に高齢者の場合、発症後のリハビリがうまく進まなければ、そのまま寝たきり状態に陥ってしまうケースが少なくありません。
しかし、正しい知識と早期からの対応があれば、そのリスクを大きく下げることが可能です。
ここでは、「脳卒中と寝たきり」の関係について、わかりやすく解説していきます。

目次
- 脳卒中とはどんな病気か
- 寝たきりになりやすい理由
- 寝たきりによる二次的なリスク
- リハビリテーションの力とその可能性
- 回復を後押しする生活習慣の改善
- ストレスと向き合う時間も大切
- 定期的な医療チェックも忘れずに

脳卒中とはどんな病気か
脳卒中とは、脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血・くも膜下出血)することによって、脳の一部が損傷を受ける病気です。
この損傷により、運動機能や言語機能、認知機能といった、人が生活していく上で欠かせない機能に障害が生じることがあります。
特に体を動かす神経がダメージを受けた場合は、手足の麻痺や感覚の異常が起き、自分の力で起き上がる・歩くといった日常的な動作ができなくなってしまいます。
その結果、ベッドから動けなくなり、寝たきりになってしまうことがあるのです。
寝たきりになりやすい理由
脳卒中をきっかけに寝たきりになる理由はさまざまですが、最も大きな要因は「体を動かす力が急激に低下すること」です。
脳の損傷によって筋肉が動かなくなると、ほんの数日間でも筋力がどんどん落ちていきます。
特に高齢者は元々の体力が低いため、さらに回復しづらくなってしまいます。
また、脳の損傷部位によっては、バランスが取れなくなったり、体の感覚がわからなくなったりすることもあります。
これにより、転倒を恐れて動かなくなったり、起き上がるのが怖くなったりして、ますます寝たきりの状態が固定化していくのです。
寝たきりによる二次的なリスク
寝たきり状態が続くと、体にはさまざまな悪影響が現れます。
まず、動かないことで筋肉が急速に弱くなっていきます(筋萎縮)。
関節が固まって動かしづらくなる「関節拘縮」も、よく見られる症状です。
さらに、体を動かさないことで血流が悪くなり、皮膚に圧がかかり続けて「褥瘡(じょくそう)」と呼ばれる床ずれができることもあります。
また、食事をきちんと摂れなかったり、トイレの際にカテーテルを使うことによって、「誤嚥性肺炎」や「尿路感染症」といった感染症のリスクも高まります。
このように、寝たきりは単に「動けない」という問題だけでなく、全身の健康を脅かす深刻な状態を引き起こすのです。

リハビリテーションの力とその可能性
脳卒中後のリハビリテーションは、寝たきりを防ぐための最も重要な手段です。
特に発症からの「早期リハビリ」がカギになります。
なぜなら、脳は損傷を受けた部分の代わりに、別の神経回路を使って機能を再構築しようとする性質があるからです。
たとえ麻痺が残っていても、反復的なリハビリを行うことで、徐々に別の神経回路が活性化され、少しずつ動きが戻ってくることがあります。
もちろん回復の度合いやスピードには個人差がありますが、「動ける可能性があるなら、動かす努力を早くから始める」ことが、寝たきりを防ぐ最大のポイントです。
回復を後押しする生活習慣の改善
リハビリと並行して、生活習慣を見直すことも非常に大切です。
まず、食事に関しては、栄養バランスの取れた食事を心がけることが回復を助けます。
特に地中海式食事法(オリーブオイルや魚、野菜中心の食事)やDASH食事法(高血圧予防を目的とした低塩食)は、再発予防にも効果があるとされています。
運動については、たとえ寝たきりに近い状態でも、できる範囲で体を動かすことが大切です。
理学療法士の指導のもとで、関節をゆっくり動かしたり、ベッド上で姿勢を変えるだけでも、血流改善や筋力低下の予防に効果があります。
また、日常生活では、高血圧や糖尿病といった生活習慣病をしっかりと管理し、喫煙を控えることも脳卒中の再発防止には欠かせません。

ストレスと向き合う時間も大切
意外に見落とされがちですが、ストレスも脳卒中の回復や予防に大きな影響を与えます。
心が緊張したままだと、血圧が上がりやすくなり、再発のリスクを高めます。
音楽を聴いたり、読書や趣味の時間を作ったりして、リラックスする時間を意識的に持つようにしましょう。
また、家族や周囲の人とのコミュニケーションも、精神的な支えとして大きな役割を果たします。
「一人じゃない」と感じられることが、リハビリのモチベーションにもつながっていきます。
定期的な医療チェックも忘れずに
リハビリや生活改善と並んで、定期的な医療チェックも非常に重要です。
血圧や血糖値の管理がしっかりできていないと、再び脳卒中を発症するリスクが高まります。
かかりつけの医師と連携しながら、必要な検査や服薬を継続していくことが、長期的な健康維持につながります。
まとめ
脳卒中は、身体だけでなく、その後の生活全体に大きな影響を及ぼす疾患です。
しかし、発症後すぐに適切なリハビリを開始し、日々の生活習慣を見直すことで、寝たきりになるリスクを大きく減らすことができます。
リハビリは、決して一人ではできないものです。
理学療法士や医師、看護師、家族の力を借りながら、少しずつ前に進むことが大切です。
身体が思うように動かなくても、「今できること」に目を向け、希望を持って毎日を積み重ねていくことが、回復への一番の近道になります。
お問い合わせ
-
【堺市中区】脳神経リハビリHL堺に、お気軽にお問い合わせください!
TEL:072-349-7303
-
動画の配信を行っております!
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。