脳血管疾患と立脚後期の重要性
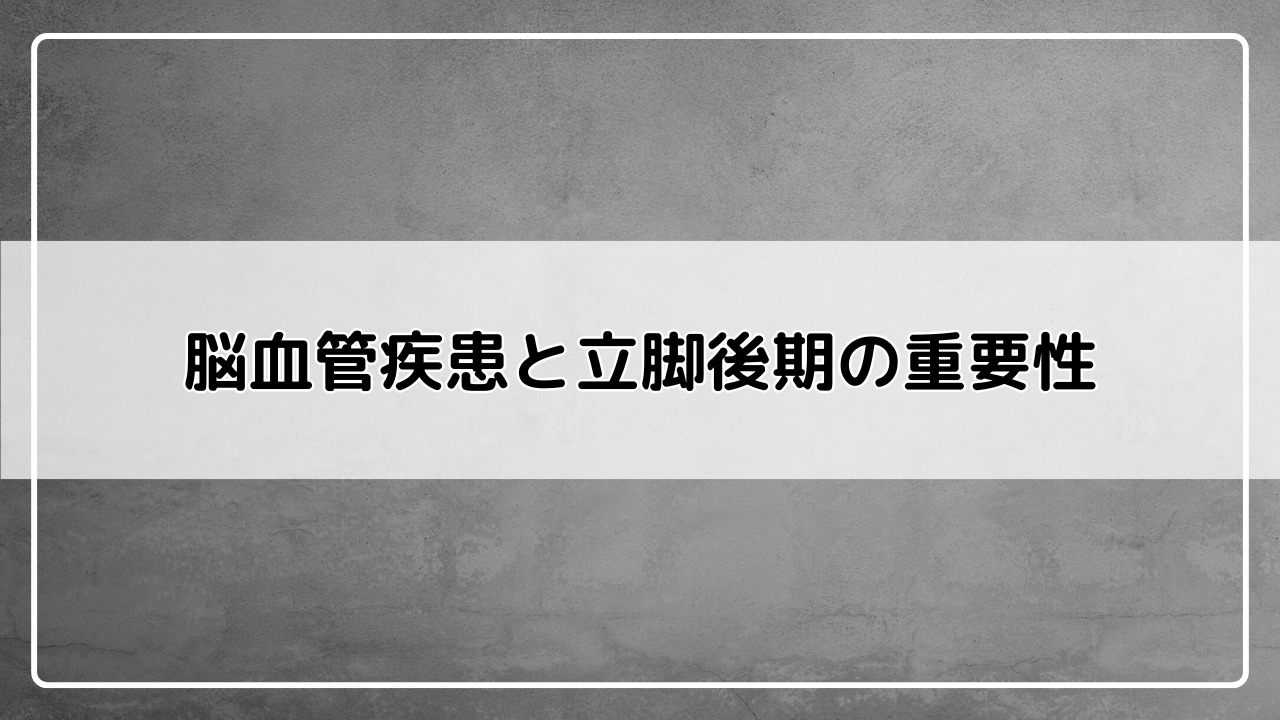
はじめに
脳血管疾患のリハビリにおいて、歩行能力の回復はとても大切です。
その中でも「立脚後期」は、スムーズな歩行を実現するためのカギを握るフェーズです。
歩行は片足がついている状態の立脚期と片足を振り出して浮いている状態の遊脚期に分けられます。
立脚後期とは、足が地面をしっかりと押して蹴り出す、前に進むための推進力を生み出す瞬間のことを言います。
この動作がうまくできないと、歩くスピードが遅くなったり、つまずきやすくなったりします。
特に脳卒中の後遺症がある方は、麻痺側の足の動きが制限されることが多く、より意識的なリハビリが必要になります。
今回、少し難しい内容ですが脳神経リハビリを行う上で、重要な内容であると思いますので本稿を投稿します。
ご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。

目次
- 立脚後期の動作が不十分だと何が起こる?
- 立脚後期の改善には股関節の動きがカギ!
- 立脚後期を改善するためのリハビリ方法
立脚後期の動作が不十分だと何が起こる?
立脚後期の動作がスムーズにできないと、歩行にいくつかの問題が発生します。
-
「推進力の不足」
足がしっかりと地面を押せない事で、次の一歩を踏み出す力が足りず、歩行速度が低下します。 -
「クリアランスの不足」
遊脚期(足を前に振り出すタイミング)で足がしっかり持ち上がらず、つまずきやすくなる状態のことを言います。
特に麻痺側の足は、足首がうまく動かないため、地面をこすってしまうことが多いです。 -
「歩幅の短縮」
立脚後期の動きが不十分だと、歩幅が短くなり、結果として歩く効率が悪くなってしまいます。
そうなると、少し歩いただけでも疲れやすくなります。 -
「不安定な歩行」
歩行の安定性にも影響があり、転倒のリスクが高まります。
特に高齢者や脳卒中の後遺症がある方にとっては、バランスを崩しやすくなるので注意が必要です。 -
「異常な歩行パターン」
例えば、足を引きずるような「ぶん回し歩行」や体を無理に前へ持っていく歩き方になってしまうことがあります。
こうした異常歩行は、疲労感を増す為、より歩行を難しくしてしまいます。

立脚後期の改善には股関節の動きがカギ!
立脚後期の動作をスムーズにするためには、股関節の動きがとても重要になります。
特に「股関節の伸展可動域(後ろに伸ばす動き)」がしっかり確保できているかがカギになります。
股関節の伸展がしっかりできると足を後方に蹴る動作がスムーズになり、より効率的に前に進むことができます。
逆に、この動きが制限されてしまうと歩行速度が遅くなり、歩幅も短くなります。
また、股関節の動きが悪いと下半身の筋肉の働きにも影響を及ぼします。
例えば、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)や太ももの筋肉(大腿四頭筋)がうまく使えなくなり、結果として立脚後期の動作が非効率になってしまうのです。
そのため、股関節の柔軟性を維持し、適切に動かせるようにすることが大切です。
さらに、股関節の伸展が制限されると体が他の部分で補おうとする「代償動作」が起こりやすくなります。
例えば、骨盤を無理に前後に動かしたり、麻痺していない側の足を過剰に使ったりしてしまうのです。
こうした代償動作は、余計なエネルギーを使うため、疲れやすくなるだけでなく姿勢の崩れや痛みの原因にもなります。
立脚後期を改善するためのリハビリ方法
では、立脚後期の動きを改善するにはどんなリハビリが効果的なのでしょうか?
股関節の伸展を強化するエクササイズ
股関節をしっかりと伸ばす動作を取り入れることで、立脚後期の蹴り出しが改善されます。
例えば、スクワットやランジなどの運動を行うことで、股関節の伸展筋(大殿筋など)を強化しスムーズな歩行を促します。
足関節の背屈を改善するストレッチやエクササイズ
足首の動きが悪いと、立脚後期の蹴り出しもうまくいきません。
足首をしっかりと動かせるようにするために、背屈(つま先を上に上げる動作)を意識したストレッチやエクササイズを取り入れることが大切です。
電気刺激療法の活用
脳卒中後の患者さんには、電気刺激を使って筋肉の活動を促すリハビリも効果的です。
特に前脛骨筋(すねの筋肉)やふくらはぎの筋肉に電気刺激を与えながら歩くことで、立脚後期の筋活動が活性化し、推進力を向上させることができます。
意識的な歩行練習
歩行そのものを練習することも大切です。
特に麻痺側の足を意識的に使いながら歩くことで、立脚後期の動作が改善されます。
また、骨盤の動きをコントロールしながら歩くことで、効率的な歩行パターンを身につけることができます。
バランス訓練の導入
片足立ちや不安定な場所での立位練習を行うことで立脚後期の安定性が向上します。
これにより、歩行時のバランスが改善され転倒のリスクも軽減できます。

まとめ
脳血管疾患のリハビリでは、歩行能力を取り戻すことがとても重要です。
その中でも、立脚後期の動作は歩行のスムーズさや安定性に大きく影響します。
もし立脚後期の動作が不十分だと推進力が足りず歩くスピードが遅くなったり、つまずきやすくなったりします。
そのため、股関節や足首の柔軟性を高めるエクササイズ、電気刺激療法、歩行練習、バランス訓練などを取り入れることで、立脚後期の動きを改善することができます。
リハビリをしっかり続けることで安全でスムーズな歩行を目指しましょう!
こちらのアカウントからリハビリ方法の動画配信を行っています。
インスタアカウント
TikTokアカウント
YouTubeアカウント

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。