被殻出血とは?-脳の深部で起こる出血とその影響-
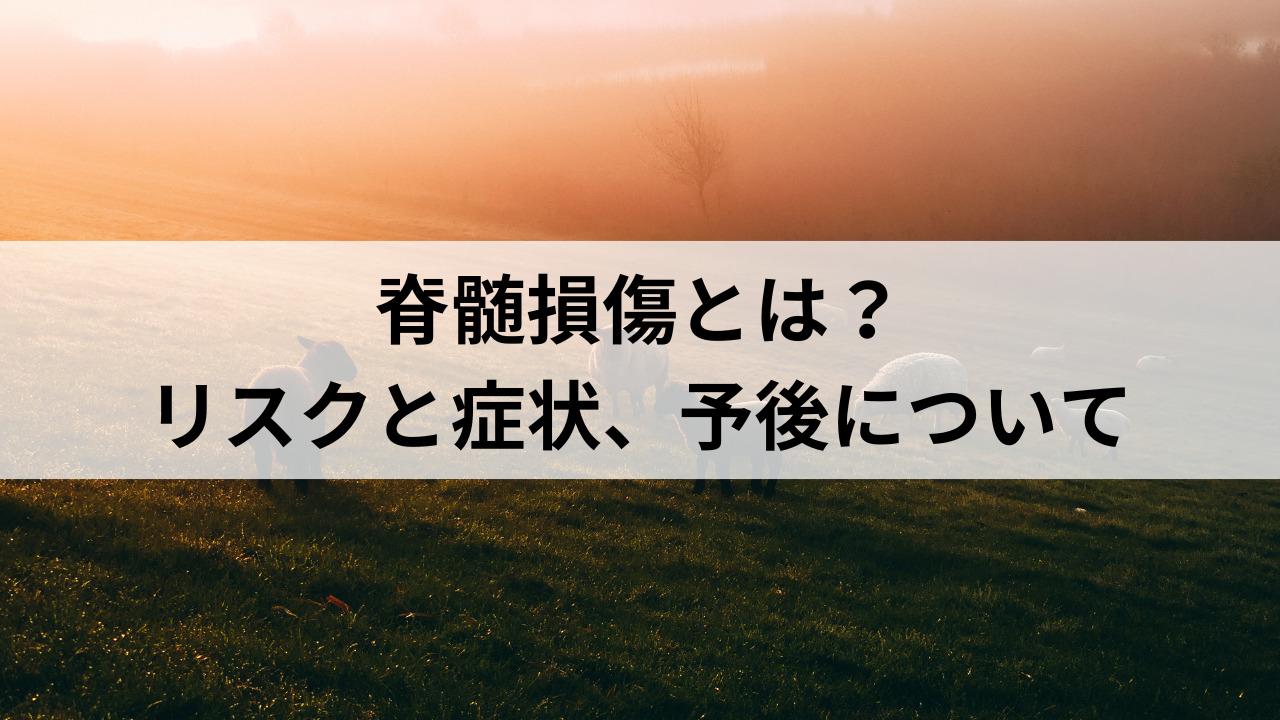
はじめに
被殻出血(ひかくしゅっけつ)は、脳の奥深くにある「被殻」という部分で起こる出血性脳卒中です。
被殻は大脳基底核の一部で、体の動きの調節や学習、感情に関わる重要な役割を担っています。
この部分で出血が起こると運動障害や感覚障害をはじめ、さまざまな神経の症状が現れることがあります。
-
当施設の利用者様で、被殻出血の症状改善を目標に来られた方がいましたので、今回この記事を書かせていただきます。
改善事例はこちら

目次
- 被殻出血の特徴
- 被殻出血の主な原因-高血圧と動脈硬化が二大要因-
- 被殻出血の症状-運動障害、感覚障害、言語障害など多岐にわたる-
- 被殻出血の診断と治療-早期発見と適切な治療が重要-
- リハビリテーションの重要性-機能回復と社会復帰を目指して-
被殻出血の特徴
被殻出血は、脳卒中全体の約10%から15%を占め、特に高血圧が主な原因となることが多い病気です。
高血圧によって脆くなった血管が破裂し、被殻内で出血を引き起こします。
この出血が周囲の脳組織を圧迫し、神経細胞にダメージを与えることでさまざまな症状が現れます。
被殻出血は、発症すると突然の激しい頭痛、意識障害、体の片側の麻痺や感覚障害などが現れることが特徴です。
これらの症状は、出血の程度や範囲、そして出血が起こった被殻の位置によって大きく異なります。
早期の診断と適切な治療が後遺症を最小限に抑え、患者さんの生活の質(QOL)を維持するために非常に重要です。
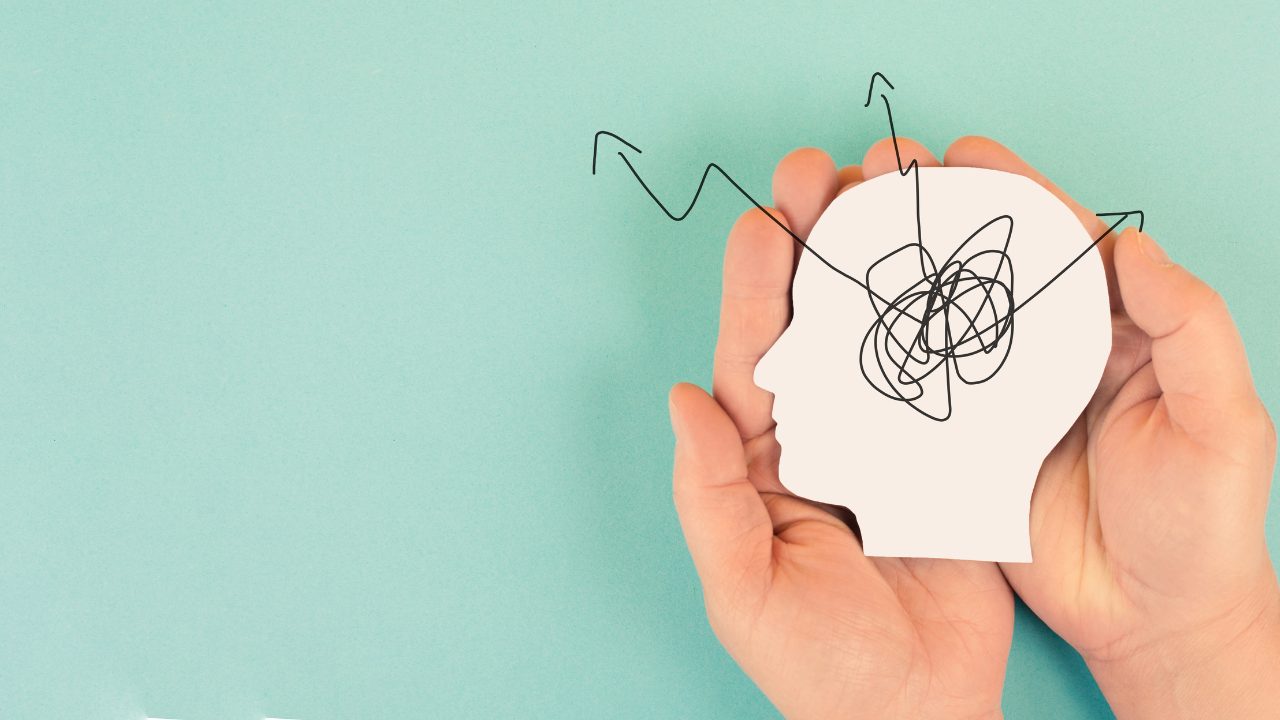
被殻出血の主な原因-高血圧と動脈硬化が二大要因-
被殻出血の最も一般的な原因は、長期間にわたる高血圧です。
高血圧は、血管の壁に常に圧力をかけて血管を脆くします。
特に被殻に栄養を送る細い血管は、高血圧によるダメージを受けやすく破裂しやすい状態になります。
動脈硬化も被殻出血の重要なリスク要因です。
動脈硬化は、血管の壁にコレステロールなどが溜まり、血管が硬く狭くなる状態を指します。
これにより、血管は弾力性を失い、血圧の変動に耐えられなくなります。
特に糖尿病や高脂血症などの生活習慣病は、動脈硬化を進行させ被殻出血のリスクを高めます。
これらの要因に加えて、以下のような要因も被殻出血のリスクを高める可能性があります。
- 加齢:血管は年齢とともに自然と脆くなります。
- 遺伝的要因:家族に脳卒中が多い場合、リスクが高まることがあります。
- 生活習慣:喫煙、過度のアルコール摂取、高脂肪食などは、血管に悪影響を与えます。
- 特定の病気:脳動脈瘤や脳動静脈奇形などの血管の異常も出血のリスクを高めます。
被殻出血の症状-運動障害、感覚障害、言語障害など多岐にわたる-
被殻出血の症状は、出血の大きさ、位置、そして影響を受けた脳の領域によって異なります。
一般的な症状には、以下のようなものがあります。
- 体の片側の運動麻痺:体の片側の手足や顔に力が入らなくなる、または動かしにくくなります。
- 体の片側の感覚障害:体の片側の感覚が鈍くなる、しびれる、または全く感じなくなることがあります。
- 言語障害:言葉が出にくくなる、呂律が回らなくなる、または他人の言葉を理解できなくなることがあります。
- 視野障害:視野の一部が欠ける、または物が二重に見えることがあります。
- 意識障害:意識がもうろうとする、または昏睡状態になることがあります。
- 頭痛や嘔吐:出血による脳の圧力の上昇によって引き起こされます。
これらの症状は、出血の程度や速度によって異なり、突然現れることが多いです。
特に重度の出血の場合、意識障害や呼吸困難を引き起こし、生命に関わることもあります。

被殻出血の診断と治療-早期発見と適切な治療が重要-
被殻出血の診断は、主に画像検査によって行われます。
- CTスキャン:出血の有無、位置、そして大きさを素早く確認できます。
- MRI:より詳しい脳の状態を把握し、出血の原因や周囲の脳組織への影響を評価できます。
治療は、出血の程度と患者さんの状態に応じて、内科的治療と外科的治療が選択されます。
内科的治療
- 血圧管理:血圧を下げる薬を投与し、再出血を防ぎます。
- 脳の腫れの軽減:脳の腫れを抑える薬を投与します。
- リハビリテーション:早期からリハビリを開始し、機能回復を促します。
外科的治療
- 開頭血腫除去術:頭蓋骨を開け、血の塊を取り除きます。
- 内視鏡的血腫除去術:内視鏡を使って、小さな穴から血の塊を取り除きます。
手術は、血の塊が大きい場合や神経の症状が進んでいる場合に検討されます。
リハビリテーションの重要性-機能回復と社会復帰を目指して-
被殻出血後のリハビリテーションは、後遺症を最小限に抑え、日常生活への復帰を支援するために欠かせません。
リハビリテーションは、患者さんの状態に合わせて個別に計画され、以下のような内容が含まれます。
- 理学療法:運動機能の回復、筋力強化、歩行訓練などを行います。
- 作業療法:日常生活の動作の練習、手先の機能回復、生活環境の調整などを行います。
- 言語療法:言葉の機能の回復、コミュニケーション能力の向上を目指します。
高次脳機能リハビリテーション:記憶障害、注意障害、計画を立てて実行する能力の障害など、高次脳機能障害に対するリハビリを行います。
リハビリテーションは、発症後早期から開始し継続的に行うことが重要です。
最新のリハビリテーション技術として、リハビリテーションロボットが活用されることもあります。

まとめ
被殻出血は、高血圧や動脈硬化などが原因で起こる重篤な脳卒中です。
早期発見と適切な治療、そしてリハビリテーションが、後遺症を最小限に抑え、患者さんの生活の質を維持するために重要です。
日常生活においては、定期的な血圧測定と管理、バランスの取れた食事と適度な運動、禁煙と節酒、ストレス管理、定期的な健康診断などのの対策を講じることで、被殻出血のリスクを減らし、健康な生活を送ることができます。
ご質問は、ぜひ当施設にご連絡ください!
-
当施設の利用者様で、被殻出血の症状改善を目標に来られた方がいましたので、今回この記事を書かせていただきます。
改善事例はこちら
-
動画の配信を行っております。
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。