脳血管疾患後の運動不足が招くリスクと対策
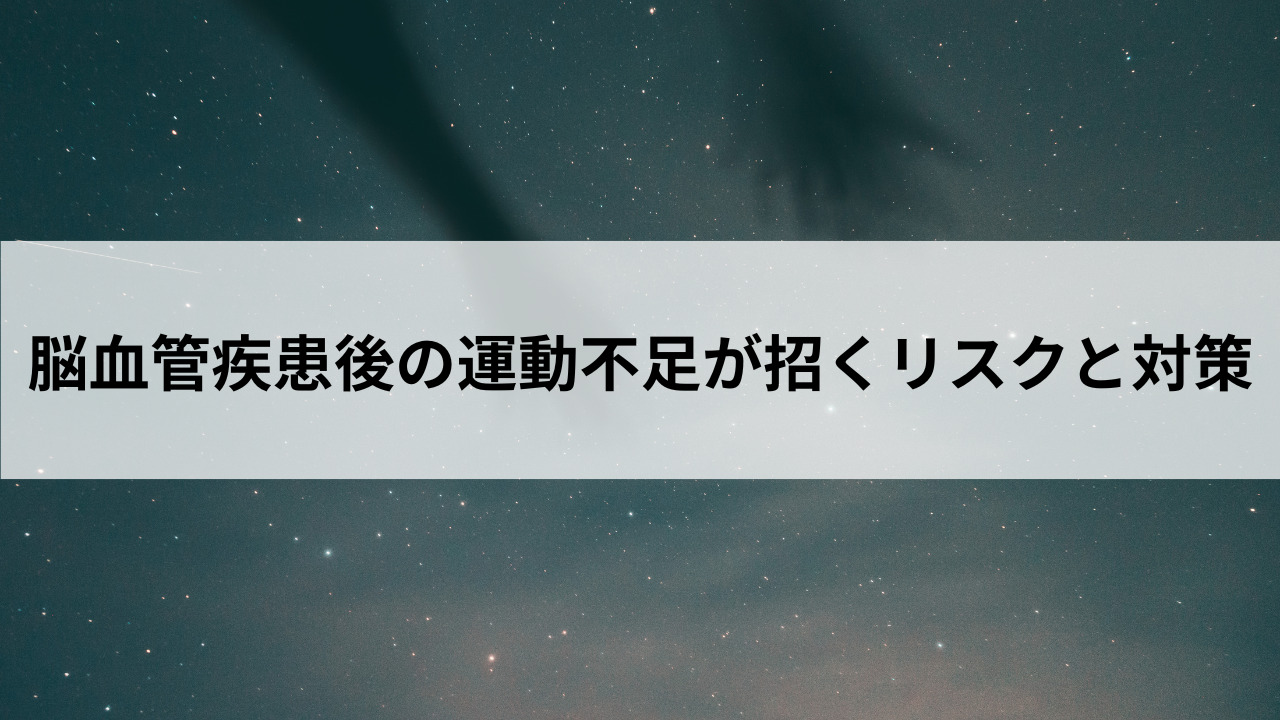
目次
- 脳血管疾患後の運動不足で何が起きる?知っておきたい4つのリスク
- 運動不足を解消!自宅でできる簡単な運動療法
- 自費リハビリで専門家のサポートを受けよう!
- まとめ
はじめに
脳卒中を経験された後、以前のようにスムーズに身体を動かせないことに不安を感じていませんか?
「リハビリは病院で一通り終わったし…」「これ以上良くなる気がしない…」と、諦めかけていませんか?
脳卒中などの脳血管疾患を経験すると、麻痺や感覚障害といった後遺症が残ることがあります。
その影響で、思うように身体を動かせず、運動不足に陥りやすい状態になってしまいます。
しかし、ここで諦めてしまってはいけません!
脳血管疾患後の運動不足は、体力や筋力の低下だけでなく、新たな病気のリスクを高める可能性も潜んでいます。
この記事では、自費リハビリで働く理学療法士である私が、脳血管疾患後の運動不足が招くリスクと、その対策について、専門用語を交えつつもわかりやすく解説していきます。
ご自身のリハビリや日常生活をより良いものにするために、ぜひ最後まで読んでみて下さい。
脳血管疾患後の運動不足で何が起きる?知っておきたい4つのリスク
脳血管疾患によって脳がダメージを受けると、身体を動かすための指令がうまく伝わらなくなり、麻痺や感覚障害、言語障害といった後遺症が現れることがあります。
その結果、以前のように活発に動くことが難しくなり、運動不足の状態に陥りやすくなります。
運動不足は、健康な方にとっても様々な病気のリスクを高める要因となりますが、脳血管疾患の経験者にとっては、さらに深刻な問題を引き起こす可能性があります。
ここでは、脳血管疾患後の運動不足によって何が起きるのか、具体的なリスクを4つ詳しく見ていきましょう。
1-1. 筋力低下と廃用症候群
脳卒中後は、麻痺によって特定の筋肉を動かす機会が減り、筋力が低下しやすくなります。
そして、運動不足の状態が続くと、筋肉を構成する筋繊維自体が細くなってしまい、さらに筋力が低下する「廃用性筋萎縮」という状態に陥ってしまいます。
また、筋肉だけでなく、関節をスムーズに動かすための柔軟性も低下し、関節が硬くなって動きが悪くなる「関節拘縮」も併発しやすくなります。
これらの状態は総称して「廃用症候群」と呼ばれ、日常生活動作(ADL)の低下、つまりは着替えや食事、トイレといった基本的な動作さえも困難になり、最終的には寝たきりのリスクを高める可能性もあるのです。
1-2. 心肺機能の低下
運動不足は、心臓や肺といった循環器系にも悪影響を及ぼしその機能を低下させてしまいます。
心臓は、全身に血液を送り出すポンプのような役割を担っています。しかし、運動不足によって心筋(心臓の筋肉)が衰えてしまうと、十分な量の血液を送り出すことができなくなってしまいます。
また、肺は、呼吸を通して体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する役割を担っています。しかし、運動不足によって肺の機能が低下すると、呼吸が浅くなってしまい十分な酸素を取り込むことができなくなってしまいます。
心肺機能の低下は、日常生活において「疲れやすくなった」「すぐに息切れがする」「動悸がする」といった症状を引き起こし、日常生活に支障をきたすだけでなく、将来的には心疾患などのリスクを高めることにも繋がります。
1-3. 血栓のリスク増加
脳梗塞は、脳の血管が血栓によって詰まってしまうことで発症します。
この血栓は、血液中のコレステロールや脂肪分などが血管壁に付着し塊となってしまったものです。
運動不足は、血液の流れを滞らせ血栓を作りやすくしてしまう要因となります。
一度脳梗塞を発症した方は、そうでない方に比べて再発のリスクも高いため、運動不足による血栓形成には特に注意が必要です。
1-4. メンタルヘルスへの影響
脳卒中後は、後遺症による身体的な変化や以前のように活動できないことによる生活の制限、社会復帰への不安などから精神的に不安定になりやすい時期です。
そのため、うつ病などの精神的な不調に陥ってしまう方も少なくありません。
運動不足は、ストレスホルモンの分泌を増加させ、うつ病のリスクを高めるだけでなく、意欲や集中力、思考力の低下にも繋がると言われています。
運動不足を解消!自宅でできる簡単な運動療法
脳血管疾患後の運動不足によって、様々なリスクが潜んでいることをご理解いただけたでしょうか?
「でも、具体的にどんな運動をすればいいのかわからない…」「体力に自信がない…」という方もご安心ください。
ここでは、ご自宅で簡単にできる運動療法を3つご紹介いたします。
無理のない範囲で、できるものから始めてみましょう。
2-1 有酸素運動で心肺機能強化!
有酸素運動は、心臓や肺などの循環器系を活性化し、心肺機能を高め、持久力を向上させる効果があります。
また、ストレス発散効果も期待できます。
【具体的な有酸素運動】
- ウォーキング: ご自身のペースで、安全な場所を歩きましょう。最初は短い距離や時間から始め、慣れてきたら徐々に距離や時間を伸ばしていくと良いでしょう。
- 水中歩行: 水の中は、水の浮力が働くため、陸上よりも関節への負担を軽減することができます。プールなどで行ってみましょう。
- サイクリング: 自転車などを利用し、負荷を調整しながら行いましょう。
【運動療法を行う際の注意点】
運動前に必ず医師に相談し、許可を得てください。
自分の体力や体調に合わせて、無理のない範囲で行いましょう。
運動中に痛みや不調を感じたら、すぐに中止してください。
こまめな水分補給を忘れずに行いましょう。
自費リハビリで専門家のサポートを受けよう!
脳血管疾患後の運動療法は、効果的な方法で行うことが重要です。
自己流で行うよりも、専門家の指導を受けることで、より安全かつ効果的に運動能力の改善を目指せます。
自費リハビリでは、理学療法士などの専門家が、患者さん一人ひとりの症状や体力レベル、目標に合わせたリハビリプログラムを作成し、マンツーマンで指導を行います。
【自費リハビリのメリット】
- 個別対応で効果UP!: 個別プログラムで、あなたのペースでリハビリを進められます。
- 専門家の的確な指導: 理学療法士が、運動方法や注意点などを丁寧に指導します。
- モチベーション維持: 定期的に通うことで、モチベーションを維持しやすくなります。
脳血管疾患後の運動不足は、様々なリスクを招きますが、適切な運動療法を行うことで、これらのリスクを予防し健康的な生活を送ることができます。
ぜひ、この記事を参考に、ご自身のペースで運動を始めてみて下さい。
そして、「一人では不安」「もっと効果的なリハビリを受けたい」と感じたら、自費リハビリも検討してみて下さい。
専門家のサポートを受けながら、一緒に「動ける喜び」を実感していきましょう!
まとめ
脳卒中などの脳血管疾患を経験すると、後遺症による運動機能の低下から、運動不足に陥りやすくなります。運動不足は筋力や心肺機能の低下、血栓リスクの増加、メンタルヘルスへの悪影響など、様々なリスクを招きます。
しかし、諦める必要はありません!
自宅でもできるストレッチや筋力トレーニング、有酸素運動などを積極的に取り入れることで、これらのリスクを減らし、健康的な生活を目指せる可能性があります。
「一人では不安」「もっと効果的なリハビリを受けたい」という方は、専門家が個別にサポートしてくれる自費リハビリという選択肢もあります。
ご自身のペースで、できることから「運動」習慣をスタートさせてみましょう!

執筆者:安原
施設長/理学療法士
施設長の安原です。
2019年に理学療法士免許を取得し大学卒業後、回復期病院と訪問リハビリで整形疾患や脳血管疾患を中心に経験し現在に至ります。
回復期病院では疾患の知識、治療技術の勉強(SJF、PNF、筋膜etc)に励み、チームリーダーや副主任を経験。
訪問リハビリでは在宅での日常生活動作を中心に介入しする。
一人ひとりの回復に対して集中して介入したいと思い、2023年9月から脳神経リハビリHL堺に勤務。
希望や悩みに対して寄り添い、目標とするゴールに向けて一緒に歩んでいければと思っています。