異常な痛み?それはアロディニアかもしれません
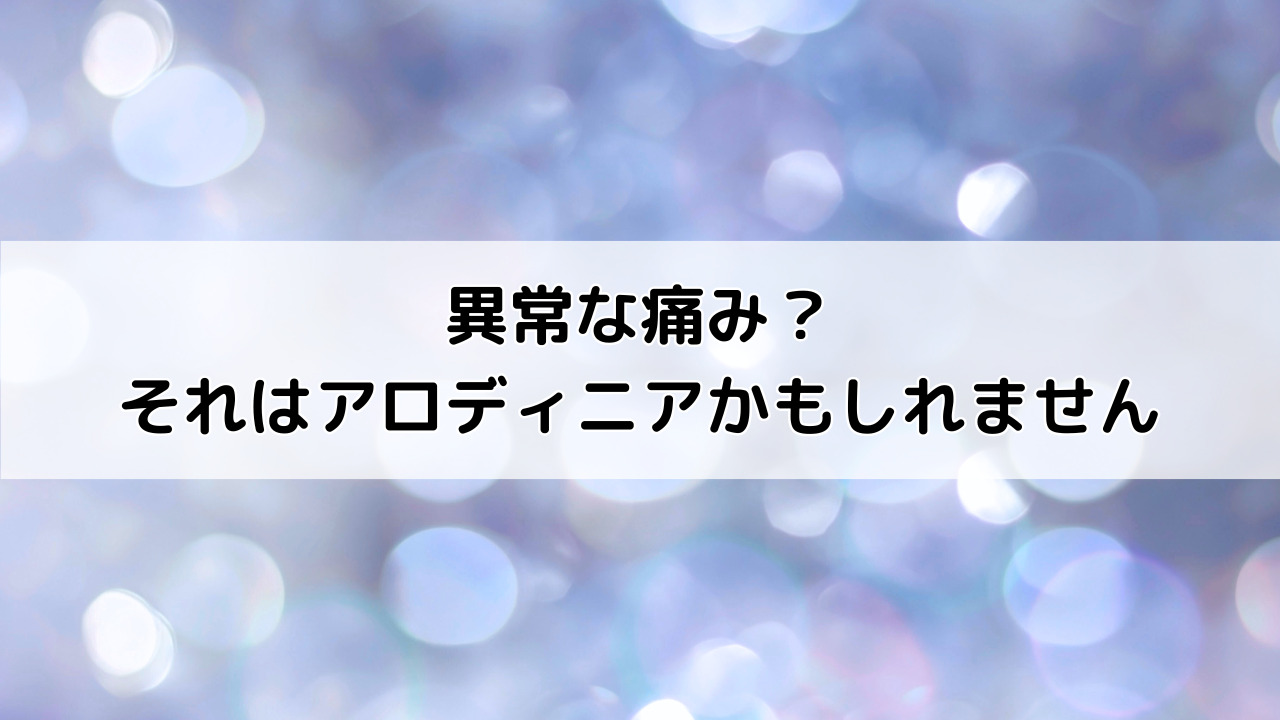
はじめに
「あれ?なんだか最近、ちょっとした触れ方や温度の変化で、今まで感じたことのないような痛みを感じる…」
もしあなたがそう感じているなら、それは「アロディニア(異痛症)」という症状かもしれません。
脳血管疾患を経験された方の中にも、このアロディニアに悩まされている方がいらっしゃいます。
今回は、この不思議な痛み「アロディニア」について詳しく解説していきたいと思います。
この記事を読むことで、「もしかして私のこの痛みはアロディニアかも?」と感じた方は、ぜひ当施設までお気軽にご相談ください。
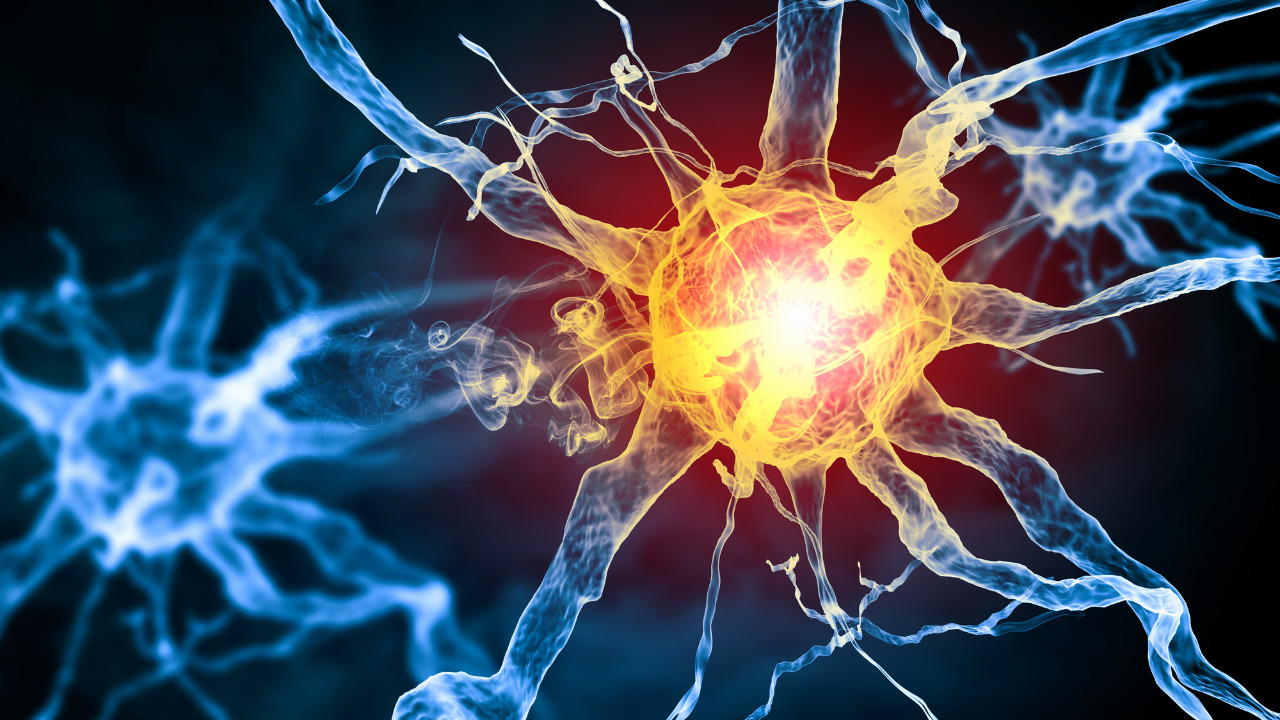
目次
- アロディニアとは? 通常は痛くない刺激が痛みに変わる不思議
- アロディニアが起こるメカニズム
- アロディニアの主な症状
- アロディニアの治療(薬物療法)
- アロディニアの治療(リハビリテーション)
- アロディニアと関連する主な疾患
アロディニアとは? 通常は痛くない刺激が痛みに変わる不思議
アロディニア(異痛症)とは、通常であれば痛みとして感じないはずの軽い刺激に対して、強い痛みを感じてしまう状態のことです。
「異なった痛み」と書くように、私たちの体が本来痛みとして認識しないような刺激、例えば、そっと触られたり、わずかな温度変化があったりするだけで、「ズキッ!」としたり、「ピリピリ」としたりといった、不快な痛みとして感じてしまうのです。
このアロディニアは、神経系の過敏な反応によって引き起こされると考えられており、特に神経の障害による痛み、つまり「神経障害性疼痛」の一種として知られています。
まるで、体の痛みのセンサーが異常に敏感になってしまっているような状態と言えるかもしれません。

アロディニアが起こるメカニズム
では、なぜこのような不思議な痛みが起こってしまうのでしょうか?
アロディニアの背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
-
神経の過敏性が高まっている
私たちの体には、様々な情報を脳に伝える神経というネットワークが張り巡らされています。
アロディニアの場合、この神経のネットワーク、特に痛みを伝える神経が何らかの原因で過敏な状態になっていると考えられています。
そのため、通常は「触られた」という感覚として処理されるはずの軽い刺激が過敏になった神経を介して「痛い!」という信号として脳に伝わってしまうのです。 -
脳や脊髄の痛みを処理する回路が混乱している
痛みを感じる仕組みは、末梢の神経から脳へと信号が伝わるだけでなく、脳や脊髄といった中枢神経も深く関わっています。
アロディニアでは、この脳や脊髄にある痛みを処理する神経回路が異常に活発になっている可能性があります。
その結果、本来であれば弱い刺激として処理されるはずの情報が脳内で過剰に増幅され、「強い痛み」として認識されてしまうのです。
これは「中枢性感作」と呼ばれる現象の一つです。 -
神経そのものが損傷を受けている
脳卒中などの病気や怪我などによって、神経そのものが直接的なダメージを受けるとアロディニアが生じることがあります。
例えば、帯状疱疹後に残る神経痛なども神経の損傷が原因でアロディニアを引き起こすことがあります。
損傷した神経は正常な信号伝達ができなくなり、その結果、予期せぬ痛みを引き起こしてしまうことがあるのです。
アロディニアの主な症状
アロディニアによって感じる痛みは、人によって様々ですが、いくつかの特徴的な症状が見られます。
-
触覚過敏:何が触れても痛い
これはアロディニアの代表的な症状の一つです。
例えば、顔に髪の毛が触れただけでピリッとした痛みを感じたり、普段は何とも思わない洋服の摩擦やメガネのフレームが当たる感触が不快な痛みとして感じられたりすることがあります。
特に頭部に起こる場合は「頭部アロディニア」と呼ばれることもあります。
まるで、肌の表面に目に見えないトゲがたくさん刺さっているような、そんな感覚かもしれません。 -
全身性の痛み:どこにでも現れる可能性
アロディニアは、体の特定の一部分だけでなく、様々な部位に現れることがあります。
軽い圧迫やちょっとした接触でも、ズキズキとしたり、焼けるような強い痛みを感じることがあります。
日常生活のちょっとした動作、例えばドアノブを握る、椅子に座る、布団が触れるといったことさえも苦痛に感じてしまうことがあるのです。 -
片頭痛との深い関係
アロディニアは、特に片頭痛を持つ方に多く見られることが知られています。
研究によると片頭痛患者さんの約40〜70%がアロディニアを経験するとも言われています。
片頭痛の発作中はもちろんのこと、発作がない時でもアロディニアの症状が現れることがあります。
片頭痛によって神経が過敏になったり、炎症が起きたりすることがアロディニアを引き起こす一因と考えられています。

アロディニアの治療(薬物療法)
神経の過敏性を抑えるために、抗うつ薬や抗けいれん薬といった、神経に作用する特別な薬剤が用いられることがあります。
これらの薬は、痛みの信号が過剰に伝わるのを抑制したり、脳の痛みを処理する回路を調整したりする効果が期待されます。
アロディニアの治療(リハビリテーション)
薬物療法と並行して、リハビリテーションも非常に重要な役割を果たします。
私たち理学療法士は、様々な方法を用いて、アロディニアによる痛みの軽減と、日常生活の質の向上をサポートします。
-
感覚リハビリテーション
感覚リハビリテーションは、アロディニアの症状を和らげるために有効なアプローチの一つです。
様々な質感の素材(例えば、最初は非常に柔らかいシルクのようなものから始め、徐々にタオルや少し硬めの布などへ)を使って、痛む部分に優しく触れることから始めます。
これを段階的に繰り返すことで、過敏になっている感覚神経を少しずつ慣らし、痛みの感覚を鈍化させていくことを目指します。 -
運動療法
痛みを避けるために体を動かすことが億劫になりがちですが、適切な運動療法は、体の機能を改善し痛みの感覚を軽減する助けとなります。
ただし、無理に痛む部位を動かすのではなく、痛みを引き起こさない範囲でストレッチや軽い筋力トレーニングなどを行います。
これにより、血行が促進され神経の働きが整うことも期待できます。 -
認知行動療法(CBT)
アロディニアのような慢性的な痛みは、心理的な状態にも大きな影響を与えることがあります。
認知行動療法は、痛みに対する考え方や捉え方を変えることで、痛みにうまく対処していくためのスキルを身につけることを目指す心理療法です。
痛みを必要以上に恐れたり、悲観的に考えたりする傾向を修正し、より前向きな気持ちでリハビリに取り組むことができるようサポートします。 -
薬物療法との連携
リハビリテーションは、医師による薬物療法と連携して行うことで、より高い効果が期待できます。
薬によって痛みが軽減されることで、リハビリテーションに取り組みやすくなり、さらに体の機能改善が進むという相乗効果が生まれます。 -
精神的なサポート
慢性的な痛みは、精神的な負担も大きいものです。
カウンセリングや心理的なサポートを通じて、患者様が抱える不安や苦痛を共有し、痛みに向き合い、受け入れていくための心の準備をサポートすることも私たちの大切な役割です。
アロディニアに対するリハビリテーションは、画一的なものではなく、患者様一人ひとりの症状や状態、そして目標に合わせて個別のプログラムを作成し、提供していくことが重要です。
アロディニアと関連する主な疾患
アロディニアは、いくつかの疾患と深く関連していることが知られています。
これらの疾患を理解することもアロディニアへの理解を深める上で大切です。
-
片頭痛
先ほども触れましたが、片頭痛はアロディニアと非常に関連の深い疾患です。
片頭痛発作時に、頭皮や顔などが普段以上に敏感になり、触れるだけで痛みを感じることがあります。 -
糖尿病性神経障害
糖尿病が長く続くと末梢神経が損傷を受けることがあります。
この糖尿病性神経障害もアロディニアの重要な原因の一つです。
足や手にピリピリとした痛みやしびれが生じ、軽い触覚刺激に対しても痛みを感じることがあります。 -
帯状疱疹後神経痛
帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスが原因で起こる皮膚の病気ですが、神経にも炎症を起こします。
帯状疱疹が治った後も、神経の損傷によって痛みが残ることがあり、これが帯状疱疹後神経痛です。
この神経痛の一つとして、アロディニアが現れることがあります。 -
繊維筋痛症(ファイブロマイアルジー)
繊維筋痛症は、全身の慢性的な痛みや疲労感を主な症状とする疾患ですが、多くの場合アロディニアも伴います。
軽く触れるだけでも、強い痛みとして感じてしまうことがあります。 -
多発性硬化症
多発性硬化症は、脳や脊髄といった中枢神経系の病気で、神経の情報を伝える仕組みに異常が生じます。
この病気の経過中にアロディニアが見られることがあります。
アロディニアは、これらの疾患における神経系の異常な反応を示す重要なサインであり、適切な診断と治療が不可欠です。
もし、アロディニアのような症状を感じている場合は、早めに専門医に相談することが大切です。

まとめ
アロディニアは、神経系の過敏性や異常によって引き起こされる複雑な症状であり、日常生活に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、適切な診断と、薬物療法とリハビリテーションを組み合わせた専門的なアプローチによって、症状の軽減や生活の質の改善が期待できます。
私たちは、あなたの「もう一度、自分らしく動けるようになりたい」という願いを全力でサポートいたします。
一緒に痛みのない、より快適な生活を取り戻しましょう。
-
動画の配信を行っております。
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。