【堺市】視床痛とは?脳が感じる痛みの正体は?
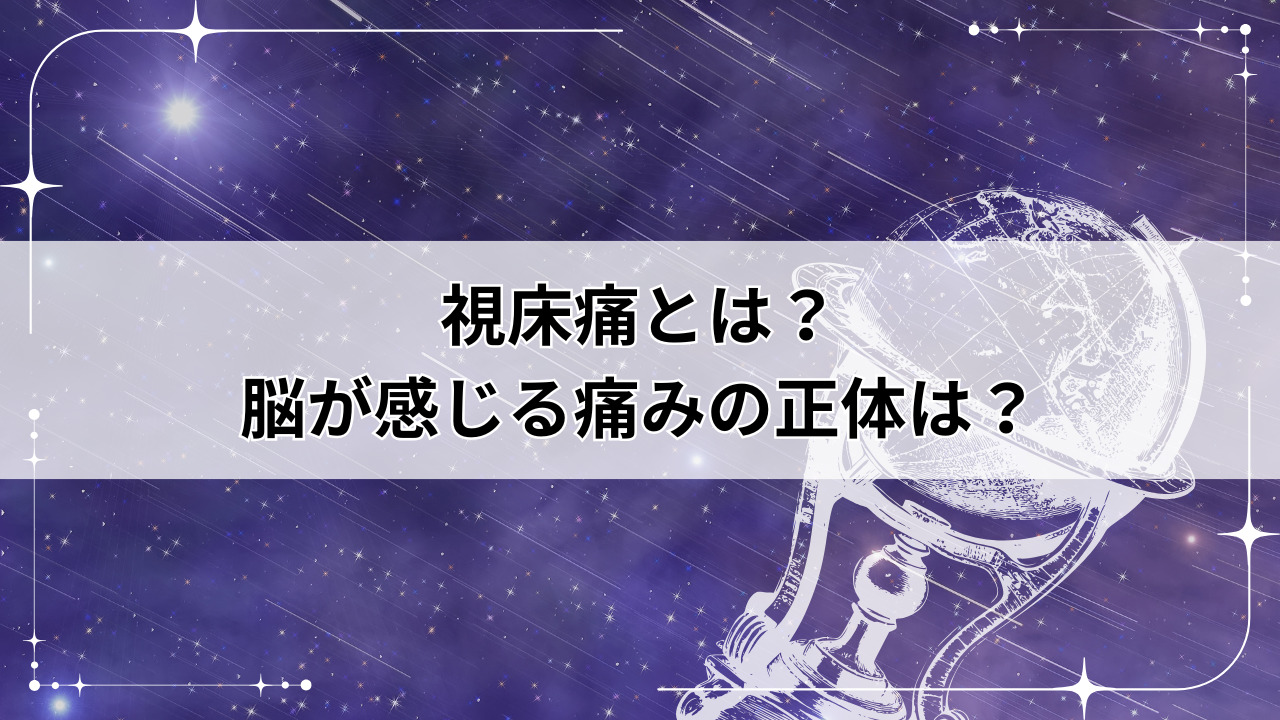
はじめに
こんにちは!
大阪府堺市中区大野芝町にある介護保険を使用しない完全自己負担型の自費リハビリで、脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・パーキンソン病・指定難病など幅広い疾患に対応しており、ロボットリハビリや型にとらわれない最先端のリハビリを受ける事が出来る「脳神経リハビリHL堺」というリハビリセンターで勤務する理学療法士です!
脳卒中や脳出血などの後遺症として、「視床痛(ししょうつう)」という非常に厄介な痛みが現れることがあります。
この痛みは、骨折や打撲のように目に見える外傷がないにもかかわらず、体の奥深くから湧き上がるような強い苦痛を伴います。
この記事では、視床痛とはどのような痛みなのか、なぜ起こるのか、そしてどのように治療やリハビリで向き合っていけるのかをできる限りわかりやすくご説明します。
目次
-
視床痛とはどんな痛みか?
-
薬物療法
視床痛の治療でまず行われるのが薬物療法です。
神経に働きかける薬を使い、痛みの感覚を和らげます。抗うつ薬(アミトリプチリン、デュロキセチンなど):気分の落ち込みに使われる薬ですが、神経に対して痛みの緩和にも効果があります。
抗けいれん薬(ガバペンチン、プレガバリンなど):元々はてんかんの薬ですが、神経の過敏な反応を抑えるために使われます。
オピオイド系鎮痛薬:非常に強い痛みがある場合に一時的に使用されますが、依存のリスクがあるため注意深く管理されます。
-
神経ブロック
神経の痛みの信号を一時的に遮断する方法もあります。
例えば、「星状神経節ブロック」や「硬膜外ブロック」といった方法があります。
これらは麻酔科などで行われ、効果がある人には痛みの軽減が期待できます。 -
神経調節技術
最近では、脳そのものに働きかける治療も行われています。深部脳刺激療法(DBS):手術で視床に電極を埋め込み、電気刺激を加えることで痛みの信号をコントロールします。
経頭蓋磁気刺激(TMS):こちらは非侵襲的で、頭に磁気を当てて脳の働きを調整します。DBSに比べて体への負担が少ないと研究が進んでいます。
-
リハビリテーション
リハビリテーションは、理学療法士として私が最も重視している分野です。視床痛を感じる部分に対して、刺激への慣れを促す「感覚統合リハビリテーション」が行われます。
たとえば、痛みを感じやすい部位に対して、柔らかいブラシでなでたり、温かさや冷たさを交互に与えたりすることで、少しずつ神経を慣らしていきます。この方法は、短期間で劇的に痛みが消えるというものではありませんが、継続することで痛みに対する感覚を鈍らせ、日常生活が少しでも楽になるよう導いていきます。
-
心理的アプローチ
慢性的な痛みは、心にも影響を与えます。
そこで「認知行動療法(CBT)」という心理療法も取り入れられています。
これは、痛みに対する考え方や反応を整理し、不安やストレスを軽減することで、痛みの感じ方そのものを変えていく方法です。 -
【堺市中区】脳神経リハビリHL堺に、お気軽にお問い合わせください!
TEL:072-349-7303 -
動画の配信を行っております!
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら
-
視床痛の原因となる脳血管疾患とは?
-
視床痛の治療とリハビリの方法
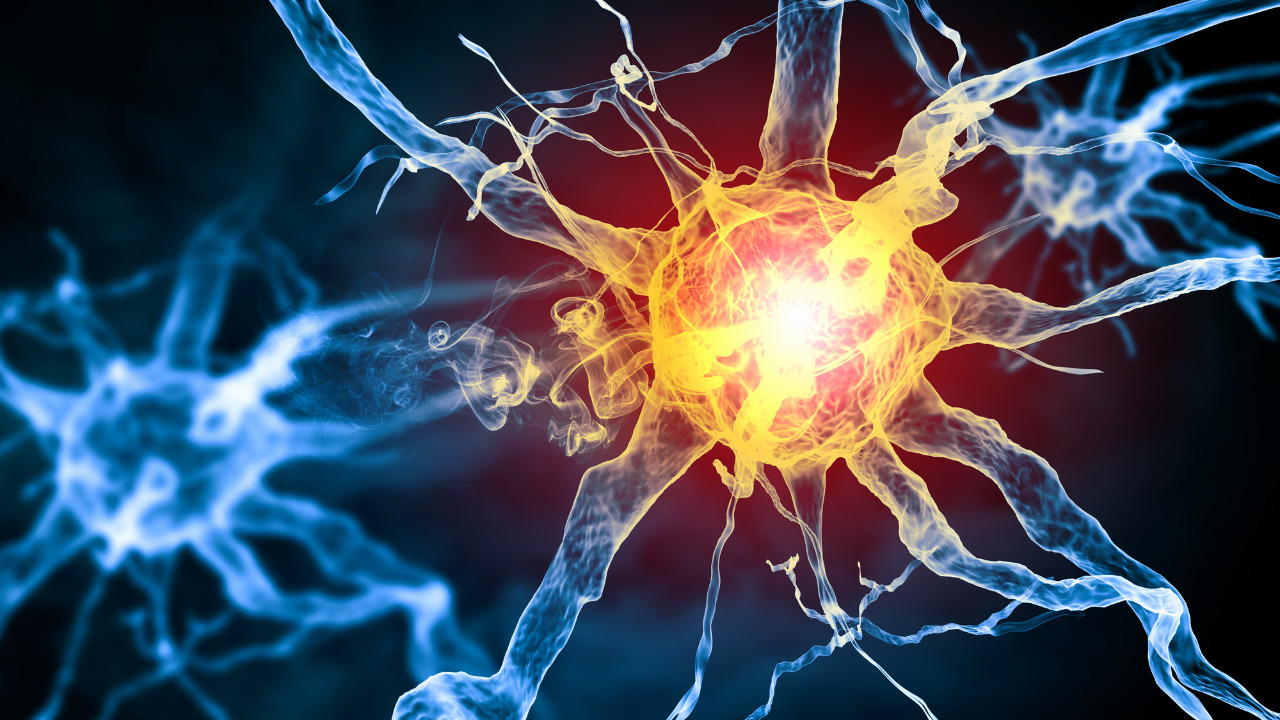
視床痛とはどんな痛みか?
視床痛とは、脳の「視床」という部位が損傷を受けたことで起こる神経の痛みです。
視床は、皮膚や内臓から伝わってくる感覚情報(熱さ、冷たさ、触れられた感覚など)を脳のほかの部分に伝える重要な中継地点です。
この視床が脳卒中や脳出血で損傷されると、感覚の情報処理がうまくいかなくなり、「痛み」として誤って脳が認識してしまうのです。
この視床痛の特徴は、いくつかの独特な感覚として現れます。
まず、「灼熱感」と呼ばれる焼けるような痛みが出ることがあります。
また、「刺すような鋭い痛み」も多くの方が経験される症状です。
そしてさらに厄介なのが、ほんの少し触れただけでも激しい痛みを感じてしまう状態、これを「異痛症(いつうしょう)」と呼びます。
普通は気にならないような洋服が肌に触れるだけで激痛を感じることもあるのです。
また、感覚のバランスが崩れることで、通常は痛みを感じないような温度や刺激にも強く反応してしまいます。
これを「アロディニア(アロディニア:Allodynia)」と言い、例えばぬるま湯に手を入れただけでも痛みとして感じることがあります。
このように視床痛は、身体の一部が実際に傷ついているわけではないにもかかわらず、強い痛みを感じる状態です。
これにより精神的なストレスや不安が高まり、睡眠や日常生活に大きな影響を与えてしまうことも少なくありません。
視床痛の原因となる脳血管疾患とは?
視床痛の主な原因は、視床に損傷を与える脳血管疾患です。
特に代表的なものとして「脳出血」と「脳梗塞」があります。
「脳出血」は、脳内の血管が破れ出血することで起こります。
特に「視床出血」はその中でも視床に直接影響を与えるため、視床痛が発生しやすくなります。
出血が視床の外側に起こると、感覚の伝達が過剰に刺激され、非常に強い痛みを引き起こすことがあります。
一方、「脳梗塞」は、血栓などにより脳の血流が止まってしまうことで起きます。
視床への血流が遮断されると、神経細胞が酸素不足に陥り、細胞がダメージを受けます。
その結果、感覚情報を処理する神経回路に異常が起こり、視床痛が生じます。
これらの疾患による視床の損傷は、痛みの信号を「間違って処理する」状態を生み出し、視床痛という症状として現れるのです。
視床痛の治療とリハビリの方法
視床痛は、薬や医療的な処置だけでなく、理学療法や心理的なサポートも含めた多角的なアプローチが必要です。
ここでは、現在考えられている主な治療法をご紹介します。

まとめ
視床痛は、目に見えにくく理解されづらい痛みであり、患者さんにとってはとても辛い症状です。
しかし、医学の進歩とともに、薬やリハビリ、心理的な支援を組み合わせることで、少しずつ症状を和らげる方法が確立されつつあります。
痛みを完全に取り除くことが難しい場合もありますが、「痛みとどう向き合うか」「どうすれば生活の質を少しでも上げられるか」という視点でサポートを行うことが、理学療法士としての大きな役割だと私は考えています。
視床痛を抱える方も、どうか一人で悩まず、医療者と連携しながらご自身に合った方法を一緒に見つけていきましょう。
リハビリも、無理のない範囲で少しずつ続けていくことで、希望の光が見えてきます。
お問い合わせ

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。