脳血管性パーキンソニズム〜脳の血管障害が引き起こすパーキンソン病に似た症状〜
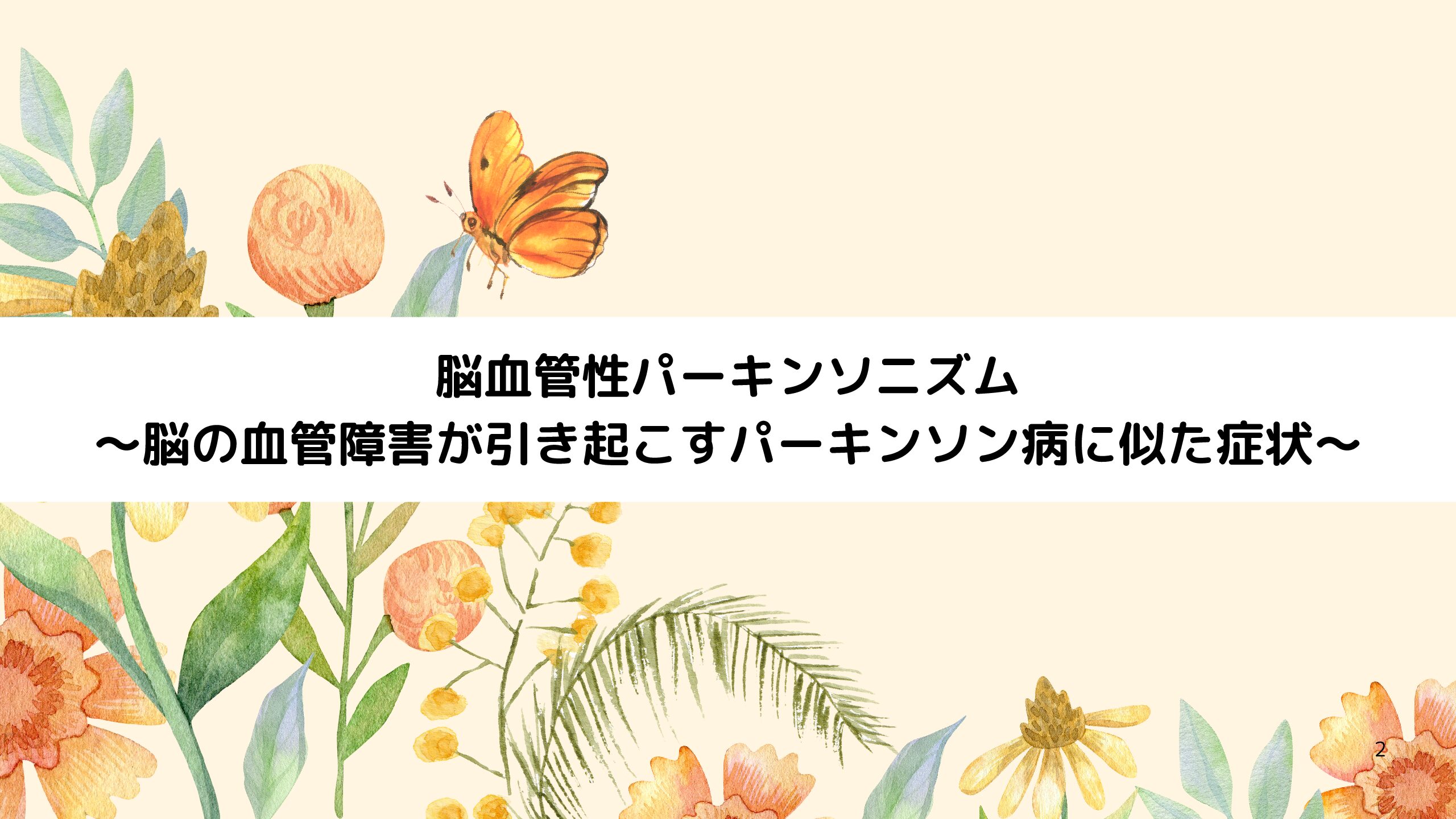
はじめに
脳血管性パーキンソニズム(Vascular Parkinsonism)は、脳の血管に何らかの障害が生じることで発症する神経疾患です。
具体的には、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害の後遺症として現れることが多く、特に高齢の方に見られます。
この病気は、パーキンソン病と似た運動症状を示すため注意が必要です。
今回は、パーキンソン病と勘違いしやすい疾患の紹介をさせていただきます。
目次
- 脳血管性パーキンソニズムの主な症状
- 脳血管性パーキンソニズムが発症するメカニズム
- 脳血管性パーキンソニズムの治療の難しさ
- パーキンソン病との違いを理解する
- 脳血管性パーキンソニズムの治療
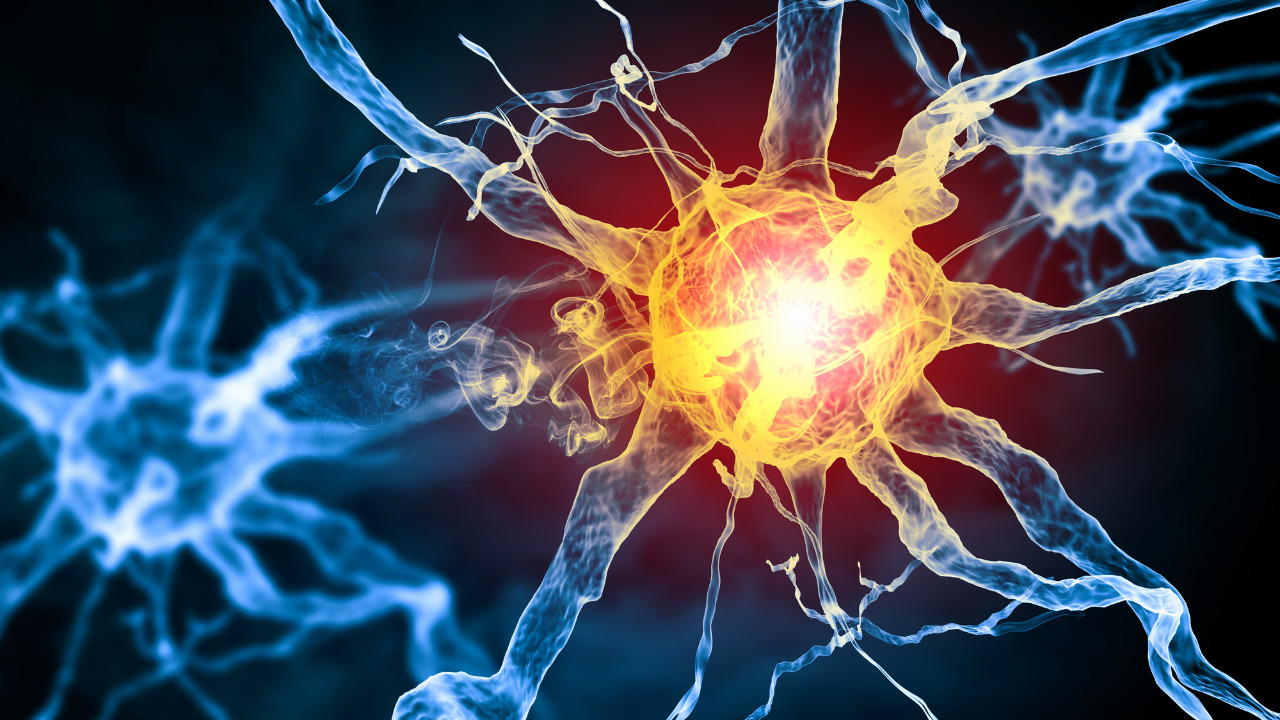
脳血管性パーキンソニズムの主な症状
脳血管性パーキンソニズムの最も特徴的な症状は、下肢を中心とした運動障害です。具体的には、以下のような症状が現れます。
- 歩行時の不安定さ: バランスを取ることが難しくなり、ふらつきやすくなります。
- 姿勢保持の困難さ: 立っているときに体が傾きやすくなったり、姿勢をまっすぐに保てなくなったりします。
- 筋肉のこわばり: 特に足の筋肉が硬くなり、スムーズな動きが難しくなります。
- すくみ足: 歩き始めの一歩が出にくくなったり、歩いている途中で足が止まってしまったりします。
- 小刻み歩行: 歩幅が小さくなり、ちょこちょことした歩き方になることがあります。まるで足が地面に吸い付いているかのように見えることもあります。
これらの症状は、日常生活における移動能力を大きく低下させる可能性があります。
脳血管性パーキンソニズムが発症するメカニズム
通常のパーキンソン病は、脳内のドーパミンという神経伝達物質を作る神経細胞が減少することで発症します。
しかし、脳血管性パーキンソニズムは、脳の血管障害、つまり小さな脳梗塞や脳出血などが運動をコントロールする脳の神経回路に影響を与えることで起こります。
そのため、パーキンソン病とは根本的な発症メカニズムが異なります。
脳血管性パーキンソニズムの治療の難しさ
脳血管性パーキンソニズムの治療は、一般的なパーキンソン病の治療薬であるレボドパがあまり効果を示さないことが多いとされています。
これは、病気の原因がドーパミンの減少ではないためです。
したがって、治療の中心は、脳梗塞の再発予防や高血圧、糖尿病、脂質異常症といった脳血管障害のリスクファクターの管理になります。
パーキンソン病との違いを理解する
脳血管性パーキンソニズムとパーキンソン病は、どちらも運動症状を主な特徴とする病気ですが、その原因や進行の仕方には重要な違いがあります。
-
原因:パーキンソン病は、脳の神経細胞が徐々に変性・減少していくことが主な原因です。
一方、脳血管性パーキンソニズムは、脳の血管が詰まったり破れたりする脳血管障害が直接的な原因となります。 -
症状の進行:パーキンソン病の症状は、一般的にゆっくりと時間をかけて進行します。
一方、脳血管性パーキンソニズムは、脳血管障害が起こった後に比較的急速に症状が現れることが多く、その後は階段状に症状が悪化していくことがあります。
これらの違いを理解することは、適切な診断と治療方針を立てる上で非常に重要です。

脳血管性パーキンソニズムの治療
脳血管性パーキンソニズムの治療に関する研究は、まだ発展途上にありますが患者さんの生活の質を向上させるための様々なアプローチが試みられています。
薬物療法の現状と研究
脳血管性パーキンソニズムの薬物療法においては、レボドパが試みられることがありますが、効果は個人差が大きいことが知られています。
最新の研究では、脳のどの部位に血管病変があるかによってレボドパの効果が異なる可能性が示唆されており、特に黒質という部位の神経経路に障害がある場合には、比較的効果が得られやすいと考えられています。
しかし、全体としては約3割の患者さんにしか明らかな効果が見られないという報告もあります。
レボドパ以外にも、ビタミンD療法や反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)といった治療法が研究されています。
ビタミンDは、神経保護作用や抗炎症作用を持つ可能性が指摘されており、脳血管性パーキンソニズムの症状改善に役立つのではないかと期待されています。
また、rTMSは、磁気刺激を用いて脳の特定の部位の活動を調整する治療法で、運動機能の改善に繋がる可能性が研究されていますが、まだ十分な科学的根拠はありません。
リハビリテーションの重要性
薬物療法と並んで、リハビリテーションは脳血管性パーキンソニズムの治療において非常に重要な役割を果たします。
理学療法や作業療法を通じて、以下のような効果が期待できます。
-
バランス能力の改善:バランス練習や体幹の安定性を高める運動を行うことで、転倒のリスクを減らします。
運動能力の維持・向上:筋力トレーニングや関節の柔軟性を保つ運動、歩行練習などを行うことで、日常生活動作の維持・向上を目指します。 - 日常生活動作の練習:食事、着替え、入浴など、日常生活に必要な動作をスムーズに行えるように練習します。
- 合併症の予防:呼吸器系の合併症や関節の拘縮などを予防するためのケアや運動指導を行います。
患者さん一人ひとりの症状や状態に合わせたリハビリテーションプログラムを継続的に行うことが、生活の質を維持し、より自立した生活を送るために不可欠です。
新しい治療アプローチへの期待
近年では、脳卒中後の神経機能回復を目指した新しい治療法も研究されており、脳血管性パーキンソニズムへの応用も期待されています。
例えば、神経成長因子(NGF)や脳由来神経栄養因子(BDNF)といった成長因子を用いた再生医療の研究が進められています。
動物実験では、これらの成長因子が神経細胞の生存を促進する効果が示されていますが、ヒトに対する効果はまだ臨床試験の段階です。
今後の展望
脳血管性パーキンソニズムの治療研究は、まだ多くの課題が残されていますが、着実に進んでいます。
今後は、患者さん個々の病態をより深く理解し、それに応じたオーダーメイドの治療法やリハビリテーションプログラムの開発が重要になると考えられます。
そのためには、さらなる臨床試験や基礎研究の推進が不可欠です。

まとめ
脳血管性パーキンソニズムは、脳の血管障害によって引き起こされるパーキンソン病に似た神経疾患であり、特に高齢者に多く見られます。
主な症状は下肢の運動障害で、歩行不安定や筋肉のこわばりなどが特徴です。
一般的なパーキンソン病とは原因が異なり、ドーパミン補充療法が効きにくい場合があります。
治療の中心は、脳血管障害の再発予防と、リハビリテーションによる運動機能の維持・改善です。
最新の研究では、新しい薬物療法や再生医療の可能性も探られており、今後の発展が期待されます。
退院後も、諦めずに積極的にリハビリに取り組むことが、より質の高い生活を送るために重要です。
私たち理学療法士は、患者さん一人ひとりの目標達成に向けて、専門的な知識と技術でサポートさせていただきます。
-
動画の配信を行っております。
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。