【堺市】脳血管リハビリに欠かせない!中枢パターン生成器(CPG)とは?
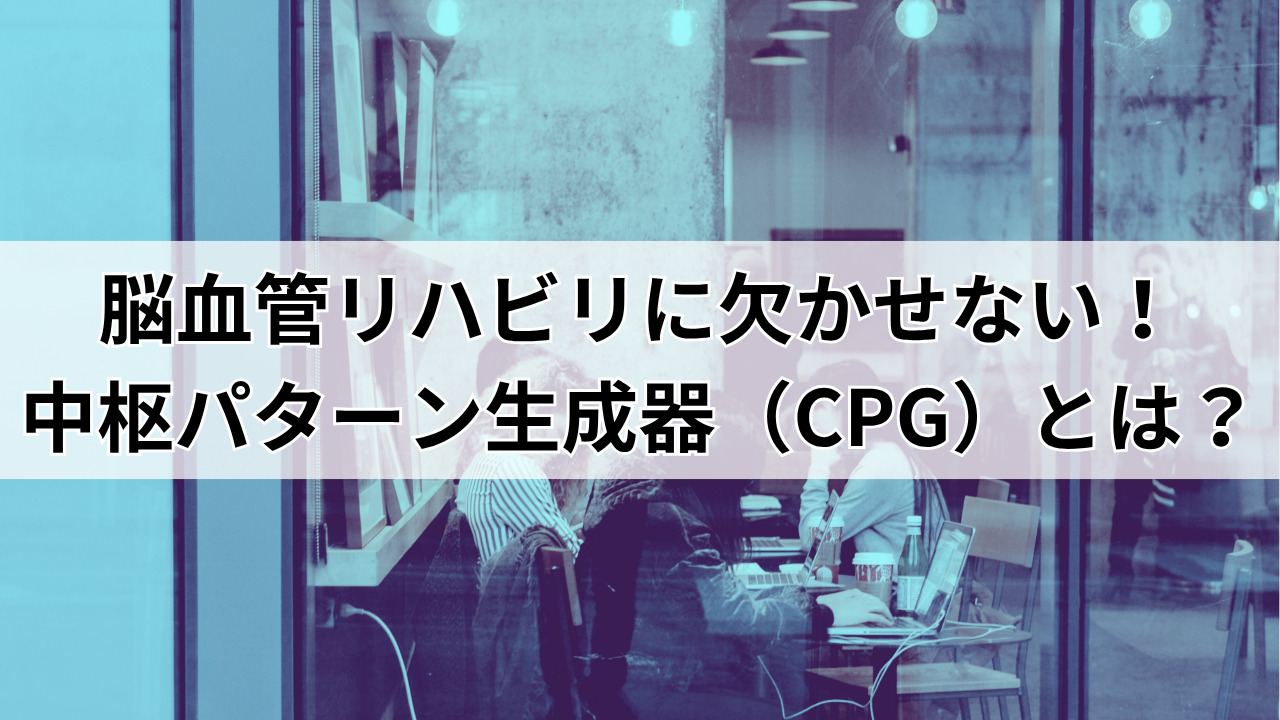
はじめに
こんにちは!
大阪府堺市中区大野芝町にある介護保険を使用しない完全自己負担型の自費リハビリで、脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・パーキンソン病・指定難病など幅広い疾患に対応しており、ロボットリハビリや型にとらわれない最先端のリハビリを受ける事が出来る「脳神経リハビリHL堺」というリハビリセンターで勤務する理学療法士です!
病気やケガで運動機能が低下したとき、多くの方が「元のように歩けるようになりたい」と強く願います。
実は、その希望を叶えるための重要なキーワードが「CPG(中枢パターン生成器)」です。
このブログでは、CPGとは何か、どのようにリハビリに活かされているのか、最新の治療法や具体的なトレーニングについて、専門的な内容を分かりやすく解説していきます。

目次
- CPG(中枢パターン生成器)とは?
- CPGのリハビリテーションへの応用
- アクティビティベースの療法(ABT)とCPGの関係
- 具体的なトレーニング方法
CPG(中枢パターン生成器)とは?
CPG(Central Pattern Generator)は、脊髄の中にある神経回路で、人が「歩く」「走る」「呼吸する」といったリズムのある運動を無意識のうちに行うための仕組みです。
たとえば、意識しなくても足を交互に動かして歩けるのは、CPGが自動的にそのパターンを作り出してくれているからです。
CPGは、脳からの指令がなくても一定の運動リズムを生み出すことができるため、脳卒中や脊髄損傷といった中枢神経系の障害を受けた方のリハビリテーションにおいて、非常に重要な役割を果たしています。
うまくCPGを活性化できれば、損傷を受けた神経が回復しづらくても、身体の運動機能を補う形で歩行能力などの再獲得が可能になるのです。
CPGのリハビリテーションへの応用
近年のリハビリ医療では、CPGの働きを最大限に引き出すような治療法が注目されています。
代表的なのが「トレッドミル歩行訓練」や「体重支持歩行」といった手法です。
これらの訓練は、患者さんの足に適切なリズムで動きを与えることで、CPGを刺激して自然な歩行パターンを呼び起こすことを目的としています。
例えば、脊髄損傷後に自力で歩けなくなってしまった患者さんでも、体重を支えるハーネスを使いながらトレッドミルの上で歩く練習を繰り返すと、CPGが再活性化されて次第に歩行機能が改善するケースがあります。
また、こうした訓練は神経回路の「可塑性(かそせい)」、つまり再構築能力を高める効果も期待されています。
神経は訓練を繰り返すことで、新たなつながりを形成しやすくなるため、継続的なアプローチがとても重要なのです。
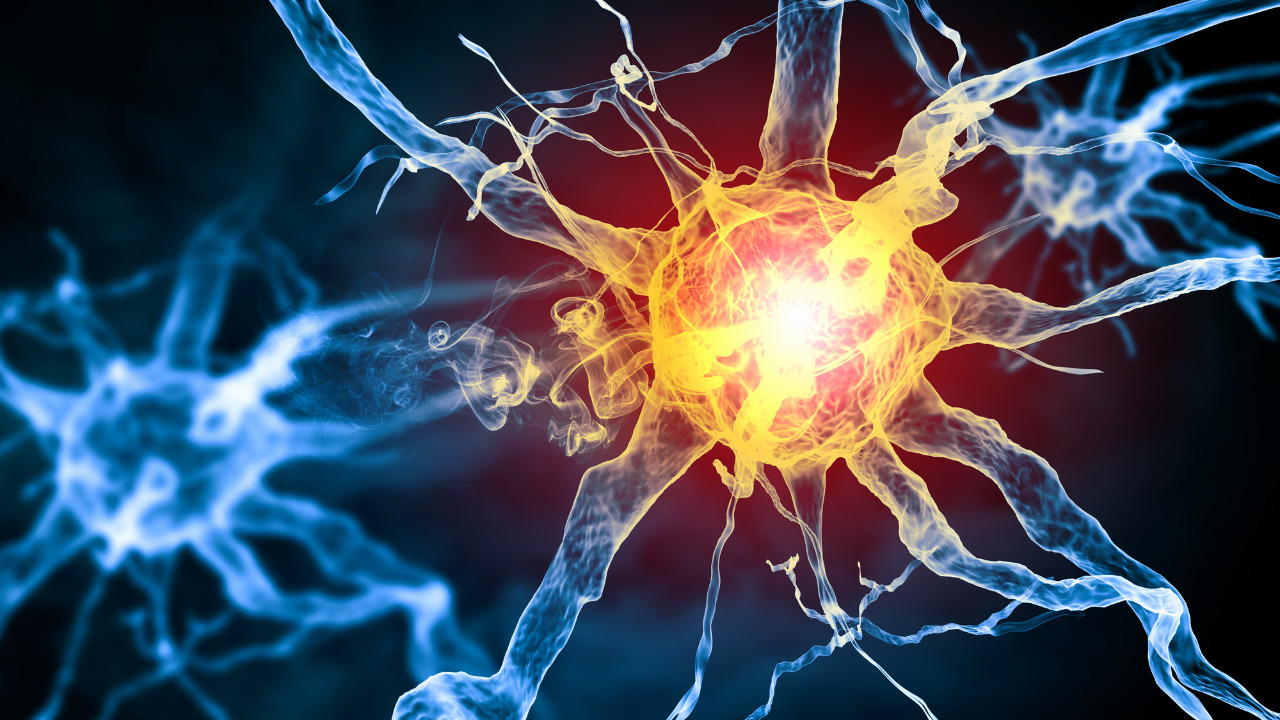
アクティビティベースの療法(ABT)とCPGの関係
CPGを活性化する上で特に有効なのが「アクティビティベースの療法(ABT)」です。
これは、ただ受動的に機械に動かされるのではなく、患者さん自身が積極的に身体を動かすことを促すリハビリ手法です。
-
神経回路の再活性化
ABTでは、「自分で動くこと」が治療の中核になります。
たとえ完全には動かせなくても、動かそうとする努力が脊髄内のCPGに刺激を与え、神経回路を再び目覚めさせる効果があります。 -
感覚フィードバックの活用
歩行や運動中に感じる「地面の感触」や「身体の位置感覚」などの感覚情報は、CPGにとって重要な調整材料です。
こうした感覚が脊髄を介してCPGに届くことで、より自然で効果的な運動パターンが生まれます。 -
脊髄刺激との併用
近年では、脊髄に微弱な電気刺激を与える治療法(脊髄刺激療法)とABTを組み合わせることで、CPGをより効果的に活性化させようという研究も進んでいます。
実際に、これにより歩行能力が大きく改善した例も報告されています。 -
繰り返しが鍵を握る
CPGの活性化には「繰り返しの運動」が非常に大切です。
同じ動きを何度も繰り返すことで、神経系が「記憶」しやすくなり、身体がスムーズに反応できるようになります。
これは「神経可塑性」を引き出す上でも不可欠なポイントです。

具体的なトレーニング方法
アクティビティベースの療法では、患者の状態に合わせてさまざまな運動パターンが実施されます。
以下に代表的なトレーニングをご紹介します。
-
トレッドミル歩行訓練
トレッドミル(ランニングマシン)を使って、体重を支えながら歩行を行う訓練です。
必要に応じて理学療法士が足の動きをサポートします。
この方法は歩行のリズムを呼び覚まし、CPGを効果的に刺激します。 -
ステッピング運動
足を交互に踏み出す動作を反復して練習する運動です。
これは歩行の基礎となる動作で、下肢筋力を強化しながらCPGの運動パターンを再学習させます。 -
体重支持歩行
専用の装置を使って患者の体重を一部支えた状態で歩行を練習します。
これにより、転倒の不安なく安全に歩行練習ができ、筋力やバランスの改善も期待できます。 -
機能的動作訓練
日常生活に必要な動作を模した運動を繰り返し練習します。
たとえば、立ち上がる、椅子に座る、物を取るといった動作を行い、実生活に役立つ運動機能の向上を目指します。 -
バランス訓練
バランス感覚を養う訓練も重要です。
片足立ちや不安定なマットの上を歩くといった練習を行い、姿勢制御能力を高め、転倒リスクの軽減を図ります。
まとめ
中枢パターン生成器(CPG)は、人間が自然に歩くためのリズムをつくる神経の仕組みであり、脳や脊髄に障害を負った方の「再び歩く力」を引き出す鍵となります。
特にアクティビティベースの療法は、CPGを活性化し、神経回路の再構築や運動機能の改善を目指す最新のリハビリ手法です。
トレッドミル歩行訓練や体重支持歩行などの具体的な運動パターンを取り入れることで、患者さん自身の「動く力」を呼び覚まし、日常生活への復帰をサポートします。
もし「もっと良くなりたい」「もう一度歩けるようになりたい」という強い気持ちがあるなら、CPGに注目したリハビリを選ぶことで、その可能性は確実に広がります。
ぜひ、医療スタッフと相談しながら、前向きにリハビリに取り組んでいきましょう。
お問い合わせ
-
【堺市中区】脳神経リハビリHL堺に、お気軽にお問い合わせください!
TEL:072-349-7303
-
動画の配信を行っております!
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。