【堺市】脳梗塞と廃用症候群の深い関係
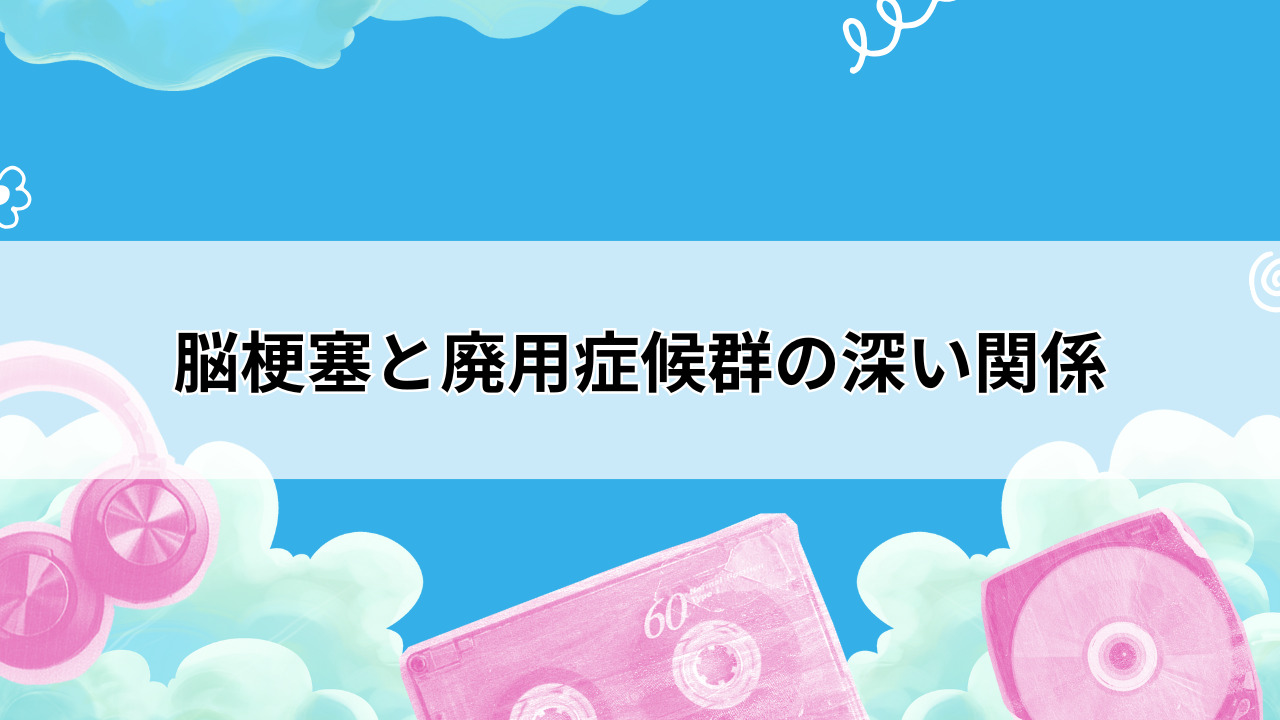
はじめに
こんにちは!
大阪府堺市中区大野芝町にある介護保険を使用しない完全自己負担型の自費リハビリで、脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・パーキンソン病・指定難病など幅広い疾患に対応しており、ロボットリハビリや型にとらわれない最先端のリハビリを受ける事が出来る「脳神経リハビリHL堺」というリハビリセンターで勤務する理学療法士です!
脳梗塞は突然訪れる大きな病気のひとつですが、その後の生活にも大きな影響を及ぼします。
中でも見過ごされがちなのが「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)」という状態です。
これは、長期間にわたって体を動かさないことで、筋力の低下や関節の硬さ、精神的な不調などが現れる症状のことです。
脳梗塞の後、十分なリハビリが行われなければ、この廃用症候群が進行し、回復の妨げとなることがあります。
この記事では、脳梗塞と廃用症候群の関係性と、どのようにリハビリが回復の鍵となるのかについて、理学療法士の視点からお伝えします。
目次
- 脳梗塞とは?その後に待ち受ける変化
- 廃用症候群とは?動かないことで起こる心身のトラブル
- 脳梗塞と廃用症候群のつながり(回復を妨げる悪循環)
- 早期リハビリテーションの重要性
- 廃用症候群がもたらす日常生活への影響

脳梗塞とは?その後に待ち受ける変化
脳梗塞は、脳の血管が詰まることによって脳の一部に血流が届かなくなり、その部分の脳細胞がダメージを受ける病気です。
これにより、手足が動かしづらくなる、言葉が出にくくなる、飲み込みが難しくなるなどの後遺症が残ることがあります。
脳梗塞の治療では、まず急性期に病院での処置が行われます。
その後、多くの患者さんは安静を保つことになりますが、この「安静にしすぎる」ことが、次の問題である廃用症候群を引き起こす原因になるのです。
廃用症候群とは?動かないことで起こる心身のトラブル
廃用症候群とは、長期間ベッドで過ごすなど、身体をほとんど動かさない状態が続くことで起こる、心と身体の機能低下を指します。
特に高齢の方に多く見られ、脳梗塞の後にこの状態に陥る方も少なくありません。
廃用症候群では、次のような変化が起こります。
- 筋力が弱くなり、歩く・立つといった基本動作が難しくなる
- 関節が硬くなり、動かしづらくなる
- 血圧の調整がうまくいかなくなり、立ちくらみやむくみが出る
- 気分が落ち込んだり、認知機能が低下したりする
つまり、身体だけでなく心にも影響を及ぼし、日常生活を自立して送ることが難しくなってしまいます。
脳梗塞と廃用症候群のつながり(回復を妨げる悪循環)
脳梗塞の患者さんは、病気によって体を動かす力が落ちてしまうため、活動量がどうしても減ります。
入院中や退院直後は、ベッドで過ごす時間が長くなりがちです。
しかし、この「動かない時間」が長くなると、筋肉が使われずにどんどん弱ってしまい、廃用症候群が進行します。
例えば、1週間安静にしているだけで、筋力が10~15%も落ちると言われています。
さらに3〜5週間も運動しない状態が続くと、筋力はなんと半分近くまで低下することもあるのです。
このように、脳梗塞で体が思うように動かないことと、安静によって筋肉が衰えることが重なり、廃用症候群へとつながっていくのです。

早期リハビリテーションの重要性
では、この悪循環を断ち切るにはどうすればよいのでしょうか?
答えは「できるだけ早く体を動かす」ことにあります。
リハビリテーションは、脳梗塞の後に早い段階で始めることが非常に重要です。
実際に、日本の調査では、脳梗塞で入院した患者のうち、入院から3日以内にリハビリが開始されたケースが96.5%にのぼるというデータがあります。
早期にリハビリを始めることで、筋力や体力の低下を防ぎ、廃用症候群を回避しやすくなるのです。
リハビリと聞くと「辛そう」「大変そう」と感じるかもしれませんが、実際には以下のような身近な活動も立派なリハビリになります。
- 毎日決まった時間にベッドから離れて椅子に座る
- ゆっくりとした散歩やストレッチを行う
- 食事や着替えなど、できる範囲で自分でやってみる
こうした活動を継続することが、心身の機能維持にとって非常に重要なのです。
廃用症候群がもたらす日常生活への影響
廃用症候群は、ただ筋肉が弱るだけの問題ではありません。
それは患者さんの生活全体に影響を及ぼす深刻な問題です。
たとえば、筋力が落ちてしまえば、トイレに行くことや椅子から立ち上がるといった基本的な動作さえ難しくなります。
また、気持ちが落ち込んだり、物忘れがひどくなったりすることで、社会とのつながりが薄れてしまうこともあります。
外出や友人との会話が減り、孤独感が強まり、リハビリへの意欲まで低下してしまう。
そんな悪循環に陥ることも珍しくありません。
さらに、体を動かさないことで誤嚥性肺炎や血栓症、床ずれ(褥瘡)といった合併症のリスクも高まります。
これらの病気は再入院や長期治療を必要とするため、患者さん本人だけでなく、ご家族の生活にも大きな負担となってしまうのです。

まとめ
脳梗塞の回復過程で、「動かないこと」が原因となって廃用症候群が進行するケースは少なくありません。
しかし、適切なリハビリを早期に始めることで、その進行を防ぐことができます。
それは、筋力や体力の回復だけでなく、心の健康を保ち、再び自立した生活を送るための第一歩なのです。
「今はまだ無理かもしれない」と思っても、小さなことから始めていくことで、確実に身体は応えてくれます。
私たちは、その一歩一歩を全力で支えていきます。
退院後のリハビリを通じて、再び活動的で豊かな毎日を取り戻していきましょう。
お問い合わせ
-
【堺市中区】脳神経リハビリHL堺に、お気軽にお問い合わせください!
TEL:072-349-7303
-
動画の配信を行っております!
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。