【堺市】脳梗塞とふくらはぎの関係とは?リハビリで注目される理由
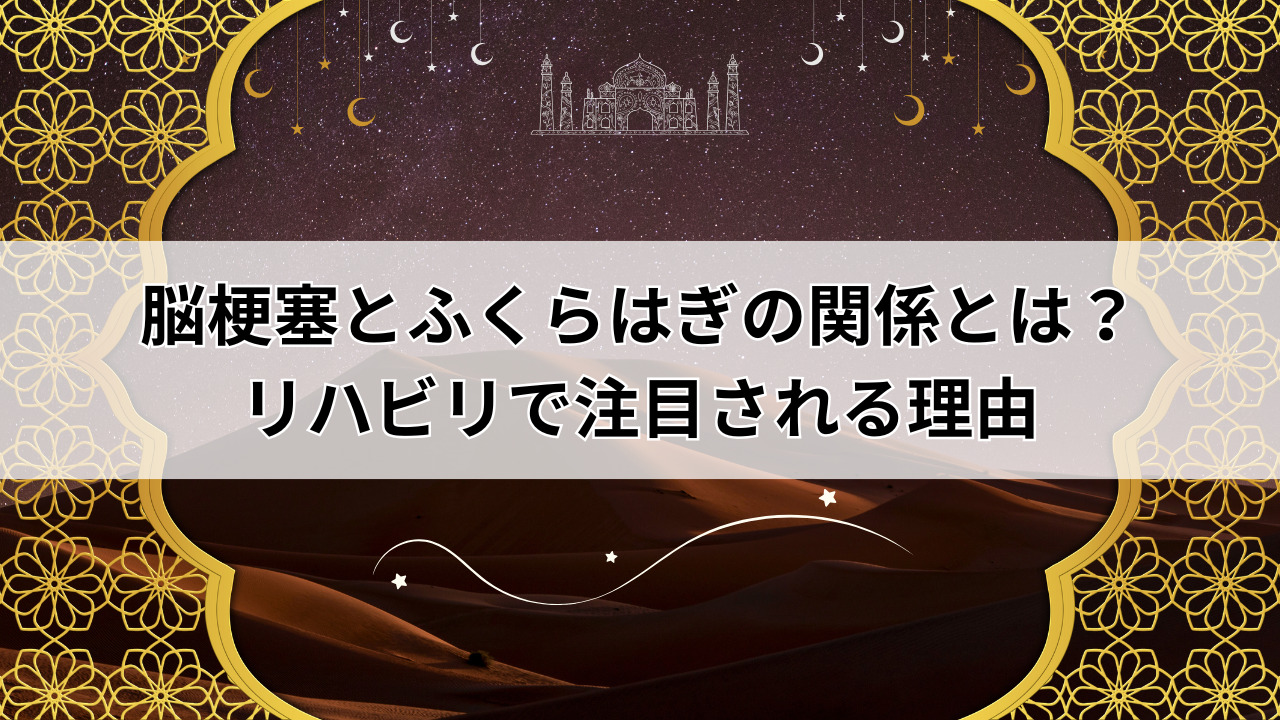
はじめに
こんにちは!
大阪府堺市中区大野芝町にある介護保険を使用しない完全自己負担型の自費リハビリで、脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・パーキンソン病・指定難病など幅広い疾患に対応しており、ロボットリハビリや型にとらわれない最先端のリハビリを受ける事が出来る「脳神経リハビリHL堺」というリハビリセンターで勤務する理学療法士です!
脳梗塞のリハビリを行う中で、「ふくらはぎ」の筋肉に注目されることがあります。
意外に思われるかもしれませんが、ふくらはぎの状態は脳梗塞後の身体機能の回復に大きく関わっています。
このブログでは、理学療法士の視点から、脳梗塞とふくらはぎの関連性についてわかりやすく解説し、リハビリにおける重要性を紹介していきます。
目次
- 脳梗塞によってふくらはぎに起きる変化
- ふくらはぎの太さが機能予後を予測する?
- リハビリでふくらはぎを鍛える意味
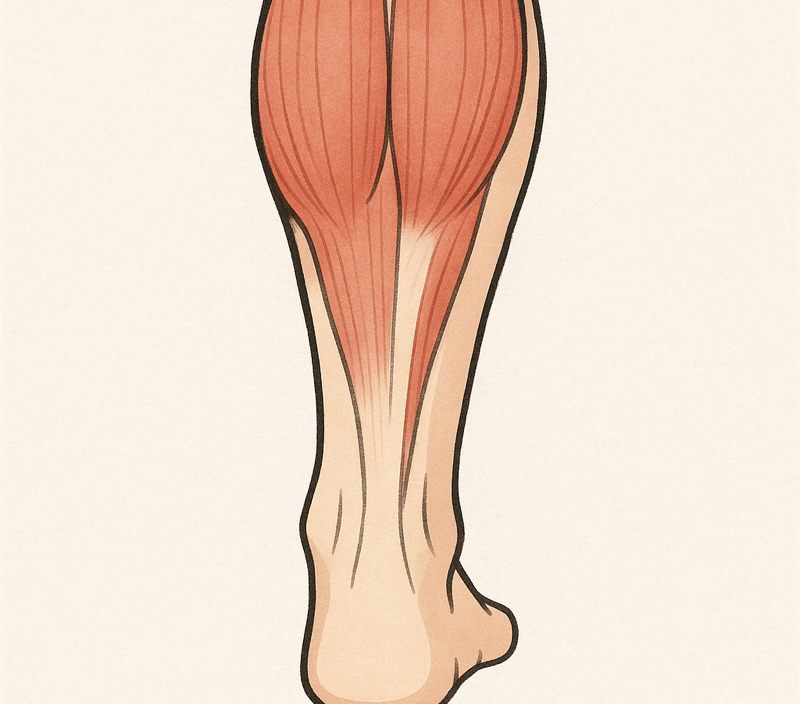
脳梗塞によってふくらはぎに起きる変化
脳梗塞は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の一部が損傷を受ける病気です。
この影響は全身に及びますが、特にふくらはぎにどのような影響が出るのかを見ていきましょう。
-
痙縮(けいしゅく)による筋肉の緊張
脳梗塞後には、ふくらはぎの筋肉、特に腓腹筋(ひふくきん)という筋肉が「痙縮」という状態になることがあります。
これは、筋肉が必要以上に緊張し、硬くなる状態を指します。
痙縮が起こると、足首の動きが制限され、歩行やバランスをとるのが難しくなります。
こうした変化は、日常生活の動作に大きな影響を及ぼすため、リハビリの中でも早期に対応すべき課題となります。 -
むくみの発生と「第二の心臓」の役割
ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれています。
これは、ふくらはぎの筋肉が血液を心臓に押し戻すポンプの役割をしているからです。
しかし、脳梗塞後に筋力が低下すると、このポンプ機能がうまく働かず、血液やリンパ液が足にたまりやすくなります。
特に麻痺のある側では、むくみ(浮腫)が起こりやすく、これも機能回復を妨げる要因になります。
ふくらはぎの太さが機能予後を予測する?
近年、ふくらはぎの「周径(しゅうけい)」、つまり太さが、脳梗塞患者の将来的な身体機能の回復と関係していることが注目されています。
-
入院時のふくらはぎの太さと回復の関係
ある研究では、入院時にふくらはぎの周径が30cm未満の患者は、12ヶ月後の機能的な回復が不十分である傾向があると報告されています。
これは、「Modified Rankin Scale(mRS)」という、脳卒中後の障害状態から生活レベルを評価するスケールを照らし合わせて明らかになったもので、ふくらはぎの太さが小さいほど、重度の障害が残るリスクが高いとされています。 -
虚血性脳梗塞との関連性
また別の研究では、ふくらはぎが細い人は、血管が詰まって起こる「虚血性脳梗塞」のリスクが高まる可能性があるという結果も示されています。
これは、筋肉量が少ない人ほど血管機能や代謝機能が低下していることと関係していると考えられています。 -
感覚と筋肉の連動がうまくいかなくなる
脳梗塞によって運動機能だけでなく、足の裏の感覚も鈍くなることがあります。
ふくらはぎの筋肉と足裏の感覚は、実は密接につながっています。
感覚が鈍くなることで、筋肉の使い方がうまくいかず、結果として足首やつま先の動きに影響を及ぼすことになります。
リハビリでは、こうした感覚と運動の両方を取り戻していくことが重要なポイントになります。

リハビリでふくらはぎを鍛える意味
ふくらはぎは歩行や立位の安定性に直結するため、リハビリではこの部分の機能回復が欠かせません。
以下に、リハビリで実際に取り入れられる方法をご紹介します。
-
ストレッチと筋力トレーニング
筋肉の緊張を和らげるためには、ストレッチが効果的です。
特に足首を動かす運動(背屈・底屈)や座った状態で行うつま先の上下運動は、筋力の回復に役立ちます。
また、こうした運動は血流の改善にもつながり、むくみの軽減にも効果があります。 -
医療用弾性ストッキングの使用
むくみの改善には、医療用の弾性ストッキングも有効です。
適度な圧力をふくらはぎにかけることで、静脈やリンパの流れを促進し、足の重だるさを軽減する効果が期待できます。
ただし、使用には医療者の指導が必要なため、リハビリスタッフや医師と相談のうえ使用しましょう。 -
早期介入の重要性と今後の展望
ふくらはぎの周径を早い段階で測定し、それに基づいてリハビリの方針を立てることが、脳梗塞後の機能回復を左右すると考えられています。
今後は、多くの病院で共通の方法に基づいた研究(多施設共同研究)が進められることで、より具体的な治療指針が確立されることが期待されます。
まとめ
脳梗塞後の身体の変化の中でも、ふくらはぎの筋肉は見過ごされがちですが、実は非常に重要な役割を果たしています。
筋肉の痙縮やむくみといった直接的な症状だけでなく、その太さが将来の回復具合を示す指標にもなることがわかっています。
適切なストレッチやトレーニング、医療的ケアを通じて、ふくらはぎの健康を保つことは、リハビリ全体の成果を大きく左右します。
これからのリハビリに、ぜひふくらはぎのケアに注目し、継続的に運動やケアを行っていくことをおすすめします。
お問い合わせ
-
【堺市中区】脳神経リハビリHL堺に、お気軽にお問い合わせください!
TEL:072-349-7303
-
動画の配信を行っております!
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。