脳出血の予後と退院後の生活・職場復帰について
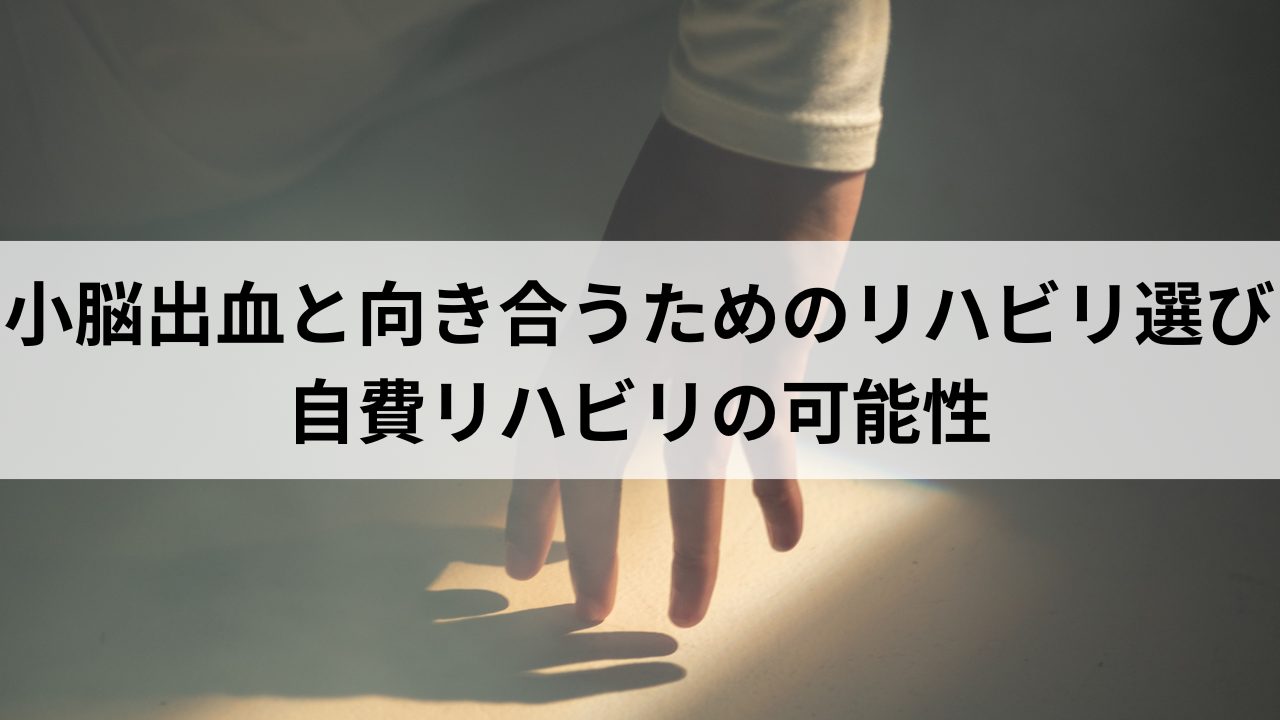
はじめに
脳出血は脳内の血管が破綻し出血する病気であり、発症後の予後や回復には多くの要因が複雑に関与します。
本稿では脳出血の予後を左右する主要な要素を詳細に解説し、退院後の生活や職場復帰に向けた具体的なステップ、利用可能な支援サービスについて包括的に説明します。
また、当施設に来られた方で職場復帰に至った方の紹介事例はこちらです。
脳出血(右麻痺)歩き方が分からない
目次
- 脳出血の予後
- 退院後の生活
- 職場復帰に向けた準備
- 自費リハビリの活用
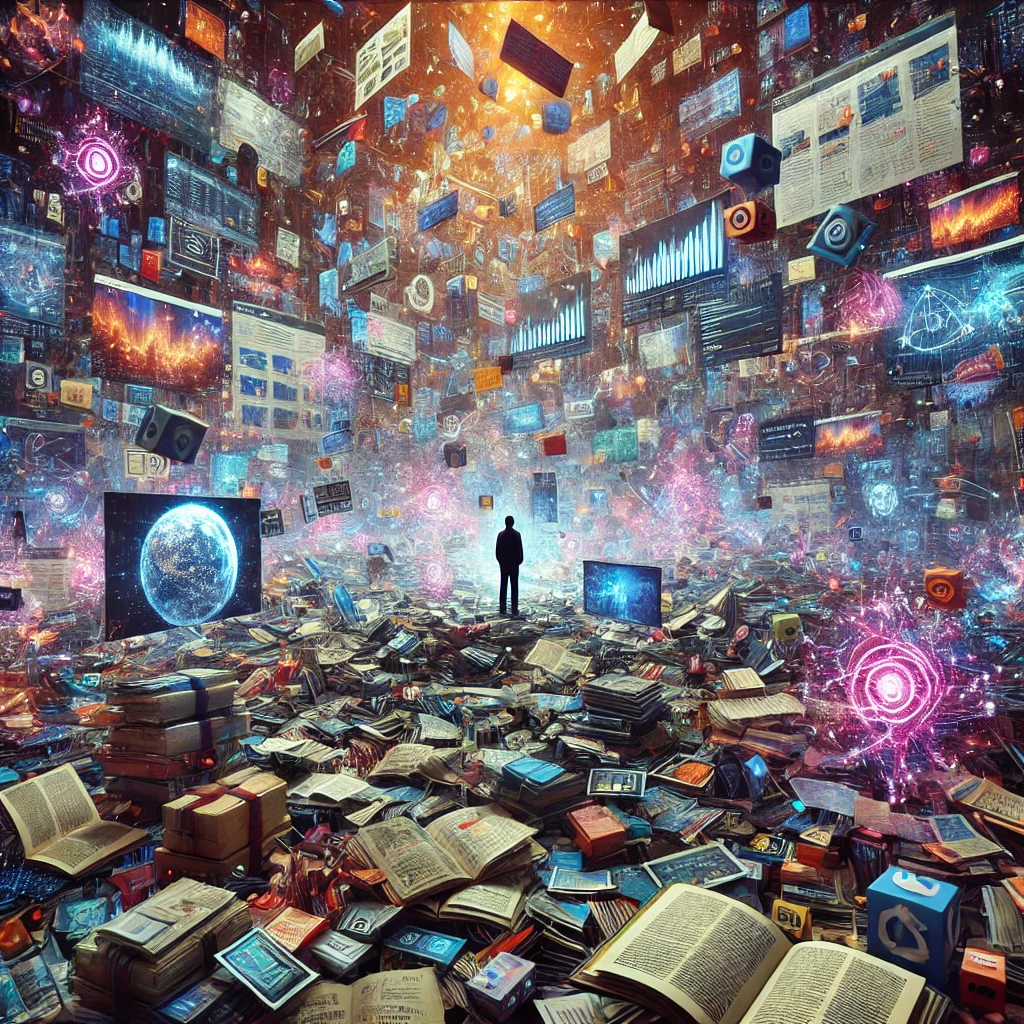
脳出血の予後
予後に影響を与える要因
-
発症時の意識レベル
発症時に意識状態がどの程度低下しているかは予後を大きく左右します。
意識レベルが低い状態(昏睡状態)であれば、重篤な後遺症が残存しやすく死亡率も高まる傾向にあります。
2022年の統計では、脳出血発症時に昏睡状態であった患者は約19.6%に達しており、これらの患者は特に慎重な経過観察と集中的な治療が必要です。 -
出血の量と部位
出血量が多いほどに脳組織へのダメージが広範囲に及ぶ為、予後は悪化します。
特に脳幹部は、呼吸や意識など生命維持に不可欠な機能が集約されている為、この部位に出血が及ぶと致死率が極めて高くなります。
一方で被殻出血や視床出血は脳出血の中でも比較的頻度が高く、全体の約65%を占めますが、これらの部位の出血でも出血量や周囲の脳組織への影響によっては重篤な後遺症を残すことがあります。 -
治療のタイミング
発症後に迅速かつ適切な治療を受けられるかが、予後を大きく左右します。
特に急性期における外科手術は、血腫の除去や脳圧の軽減を目的として行われ機能回復の可能性を高めることが報告されています。
脳出血が疑われる場合は、一刻も早く医療機関を受診し専門医による診断と治療を受けることが重要です。
生存率と後遺症
-
生存率
脳出血の5年生存率は、患者の年齢、基礎疾患、発症時の状態などによって大きく変動し約24%から58%と報告されています。
高齢者や合併症を持つ患者では生存率が低下する傾向にあります。 -
主な後遺症
脳出血後の患者の多くは何らかの後遺症を抱えて生活することになります。
主な後遺症としては、運動麻痺(半身麻痺など)、感覚障害(しびれ、痛みなど)、言語障害(失語症、構音障害など)、高次脳機能障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害など)が挙げられます。
これらの後遺症は日常生活動作(ADL)や社会生活に大きな影響を与える可能性があります。
予後改善のためのポイント
-
脳出血の予後は決して楽観視できるものではありませんが、適切な医療とリハビリテーションを行うことで機能回復や生活の質の向上が期待できます。
発症時の意識レベル、出血量、治療のタイミングは、予後を左右する重要な要素であるため、これらの情報を総合的に判断し、最適な医療を提供する必要があります。
また、脳出血のリスクを高める高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病を管理し、健康的な生活習慣を維持することが脳出血の予防と予後改善につながります。
退院後の生活
リハビリテーションの重要性
脳出血後の回復には、入院中だけでなく退院後も継続的なリハビリテーションが不可欠です。
リハビリテーションは、急性期、回復期、維持期の3つの段階に分けられる為、それぞれの段階で目標と内容が異なります。
- 急性期リハビリテーション:発症直後から行われ、生命維持を最優先とし合併症の予防や早期の機能回復を目指します。
- 回復期リハビリテーション:病状が安定した後に行われ、運動機能や嚥下機能の改善、日常生活動作の獲得を目指します。
- 維持期リハビリテーション:退院後も継続され、日常生活動作の自立、社会復帰、生活の質の向上を目指します。
生活習慣の見直し
脳出血の再発予防のためには生活習慣の見直しが不可欠です。
- ストレス管理:ストレスは血圧上昇の要因となるため、趣味やリラクゼーションを取り入れ、ストレスを適切に管理することが重要です。
- 食事の改善:塩分摂取量を減らし、野菜や果物を積極的に摂取するなどバランスの取れた食生活を心がけましょう。
- 禁煙と節酒:喫煙は血管を収縮させ、飲酒は血圧上昇や脳出血のリスクを高めるため、禁煙と節酒を心がけましょう。
家族のサポート
家族の理解とサポートは患者の回復を大きく左右します。
特にリハビリテーションの継続、生活環境の整備、精神的なサポートにおいて家族の協力が不可欠です。

職場復帰に向けた準備
復職のためのステップ
-
リハビリテーションの継続
身体機能や認知機能の回復を促し職場復帰に必要なスキルを向上させます。
-
業務能力の評価
職場復帰に向けた適応力を確認するため、リハビリテーション専門職による評価や職場でのトライアル勤務を行います。
-
職場環境の調整
作業環境の改善、業務内容の調整、勤務時間の短縮など職場環境の調整を行います。
-
復職のプロセス
段階的な復帰:短時間勤務から始め、徐々に勤務時間を増やしていくなど段階的な復帰を目指します。
コミュニケーションの重要性:上司や人事担当者と密に連携し必要な配慮やサポートを受けられるようにします。 -
メンタルヘルスのケア
職場復帰は患者にとって大きな心理的負担となることがあります。
カウンセリングやサポートグループを利用するなどメンタルヘルスのケアも積極的に行いましょう。
自費リハビリの活用
-
自費リハビリの利点
個別対応:患者の状態や目標に合わせたオーダーメイドのリハビリテーションプランを作成できます。
柔軟なスケジュール:保険診療に比べて、リハビリテーションの頻度や時間を柔軟に設定できます。
最新技術の活用:電気刺激療法や仮想現実を用いたリハビリテーションなど最新のリハビリテーション技術を利用できます。 -
活用方法
リハビリテーション専門家との相談:自費リハビリテーションを提供する医療機関やリハビリテーション施設に相談し、目標や予算に合ったプランを作成します。
段階的な目標設定:短期目標と長期目標を設定し、目標達成に向けて計画的にリハビリテーションを進めます。
定期的な進捗評価:定期的にリハビリテーションの効果を評価し、必要に応じてプランを見直します。
職場との連携:リハビリテーションの成果を職場に伝え、復職に向けた協力を得られるようにします。

おわりに
脳出血は、発症時の意識レベル、出血量、治療のタイミングによって予後が大きく左右されます。
生存率は患者の年齢や健康状態によって異なり、多くの場合は運動麻痺や感覚障害などの後遺症が残ります。
回復には、急性期から維持期に至る継続的なリハビリテーションが不可欠であり、生活習慣の見直しや家族のサポートも重要です。
職場復帰に向けては、リハビリの継続、業務能力の評価、職場環境の調整など段階的な準備が必要です。
自費リハビリの活用も有効であり、個別対応や最新技術の利用が可能です。
適切なリハビリと生活習慣の改善、職場復帰に向けた準備によって、社会復帰が期待されます。
当施設では、より安心した生活動作や職場復帰の支援を積極的に行っています。
ご質問がありましたら、ぜひお問い合わせ下さい。
当施設に来られた方で職場復帰に至った方の紹介事例はこちらです。
脳出血(右麻痺)歩き方が分からない

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。