脳の「見えにくい障害」高次脳機能障害とは? リハビリの重要性と社会の支援体制について
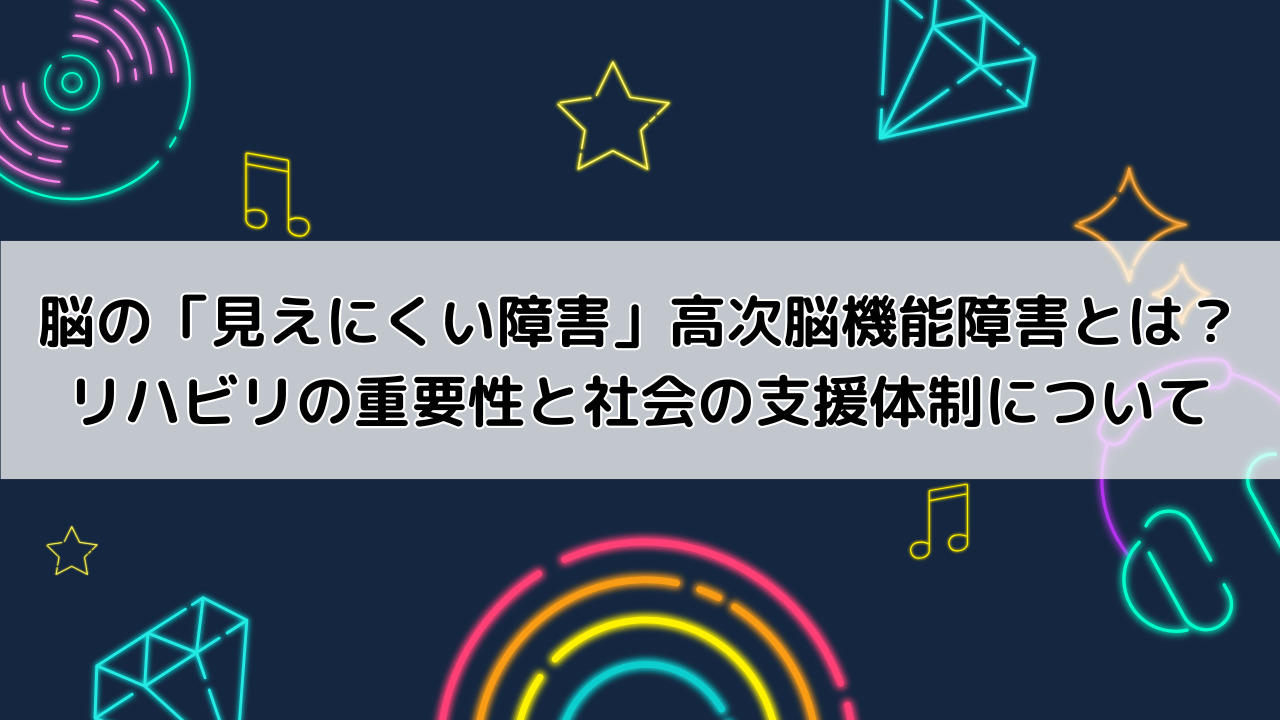
はじめに
病院を退院した後も、日々の生活の中でリハビリを続けたいと考える方は少なくありません。
特に高次脳機能障害という診断を受けた方やそのご家族にとっては、「これから何をすれば良いのか」「どんな支援が受けられるのか」といった不安が大きいのではないでしょうか?
この記事では、高次脳機能障害の基礎知識とリハビリの重要性、そして現在進んでいる社会的な支援体制について分かりやすく解説します。
目次
- 高次脳機能障害とは
- 主な原因と症状について
- 診断と治療のアプローチ
- 社会における影響と課題
- 社会的支援の進展
- 大阪府における先進的な取り組み

高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、脳の損傷によって引き起こされる「認知機能」や「行動」に関する障害の総称です。
ここで言う“認知機能”とは、記憶力や注意力、物事を計画・実行する力、言葉を使う力など、人が日常生活を送る上で欠かせない能力を指します。
この障害は、脳のどこに、どれだけの損傷があるかによって現れる症状が大きく異なるため、「見た目では分かりにくい障害」として知られています。
外見上は元気そうに見えても、内側では大きな困難を抱えていることが多く、本人も周囲も戸惑いを感じやすいのが特徴です。
主な原因と症状について
高次脳機能障害の原因として多いのは、以下のような脳の損傷や疾患です。
- 脳血管障害(脳梗塞や脳出血)
- 頭部外傷(交通事故や転倒などによる)
- 低酸素脳症(溺水や心停止による酸素不足)
- 脳炎や脳腫瘍などの疾患
これらの原因によって、脳の特定の部位に損傷が起きると、さまざまな症状が現れます。
- 代表的な症状をいくつかご紹介します。
記憶障害
新しい情報を覚えるのが難しくなったり、最近あった出来事を忘れてしまう症状です。
特に短期記憶に問題が出やすく、「言ったそばから忘れてしまう」といったことが起こります。
注意障害
一つのことに集中し続けるのが難しくなります。
そのため、複数の作業を同時に行うのが困難になり、些細な音や出来事にすぐ気を取られてしまいます。
遂行機能障害
「計画を立てて、それを実行に移す」という一連の流れがうまくできなくなる障害です。
例えば料理をしようとしても、材料を出したまま順番が分からなくなったり、途中で他のことに気を取られてしまうことがあります。
社会的行動の変化
以前は穏やかだった人が急に怒りっぽくなったり、場にそぐわない言動をするようになることもあります。
これは、感情をコントロールする脳の機能が影響を受けているためです。
視覚認知障害や感情の変化
物の見え方や空間の認識が歪んだり、不安や抑うつといった精神的な問題が生じることもあります。

診断と治療のアプローチ
高次脳機能障害は、「どこに、どんな損傷があるか」「どのような症状があるか」を正確に把握することが非常に重要です。
そのため、以下のような診断が行われます。
神経心理学的検査
記憶や注意、言語、空間認知などの機能を詳しく測るテストです。
日常生活に支障がある部分を見極めるために役立ちます。
画像診断(MRIやSPECTなど)
脳の構造的・機能的な異常を把握し、障害の原因や程度を判断します。
リハビリテーション
特に認知機能の再学習を目指す「認知リハビリテーション」は重要です。
社会における影響と課題
高次脳機能障害は、本人だけでなく家族や社会にも大きな影響を与える障害です。
社会復帰の困難
職場復帰や家庭での役割をこなすことが難しくなるため、自己肯定感が下がるとともに、家族の負担が増大します。
経済的な影響
働けないことで収入が減少し、生活の安定が脅かされます。
また、医療・福祉サービスの利用に伴って、医療費の負担も増える傾向にあります。
家族のストレス
行動や性格の変化により、家族が対応に苦慮する場面も多く、精神的・肉体的な負担が蓄積しやすくなります。
社会的支援の進展
幸いなことに、近年では高次脳機能障害に対する社会的な支援体制が整備されつつあります。
認知の向上と診断基準の確立(2005年)
診断基準が設けられたことで、早期発見や適切な支援につながるようになりました。
地域連携による支援体制の強化
地方自治体と医療機関、福祉サービスが連携し、地域で継続的なリハビリが受けられる体制が整えられています。
家族への支援制度の充実
介護者支援プログラムや相談窓口が整備され、家族の負担軽減を図る取り組みも進んでいます。
コミュニティによる支援の活性化
地域のボランティア団体や患者会などが、交流の場や就労支援の機会を提供することで、社会とのつながりを保つための支援が増えています。
テクノロジーの導入
記憶をサポートするアプリや料理支援システムなどの日常生活の自立を後押しする技術も開発・活用されています。

大阪府における先進的な取り組み
大阪府では、高次脳機能障害を持つ方々に対して、医療から社会参加まで多岐にわたる支援が実施されています。
- 専門的リハビリテーションの提供
- 相談支援センターの設置
- 福祉的就労支援の展開
- 医療・福祉職向けの研修会開催
- 地域団体によるネットワーク形成
特に堺市では、脳損傷協会などと連携しながら、当事者・家族・支援者が共に学び、支え合う体制が整いつつあります。
まとめ
高次脳機能障害は、その特性から「見えにくい障害」とされることが多く、周囲の理解が得にくいこともあります。
しかし、リハビリによって少しずつ機能を回復させ、生活の質を取り戻すことは可能です。
重要なのは、「本人」「家族」「支援者」「社会」の四者が協力しながら、長期的に支える体制を築いていくことです。
そして、リハビリは退院後も続く「人生の再構築」のプロセス。
焦らず、ひとつずつ積み重ねていくことが大切です。
当ブログでは、今後もリハビリに役立つ情報を発信していきますので、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
-
動画の配信を行っております。
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。