手足の痺れ、神経の異変を見逃さないために
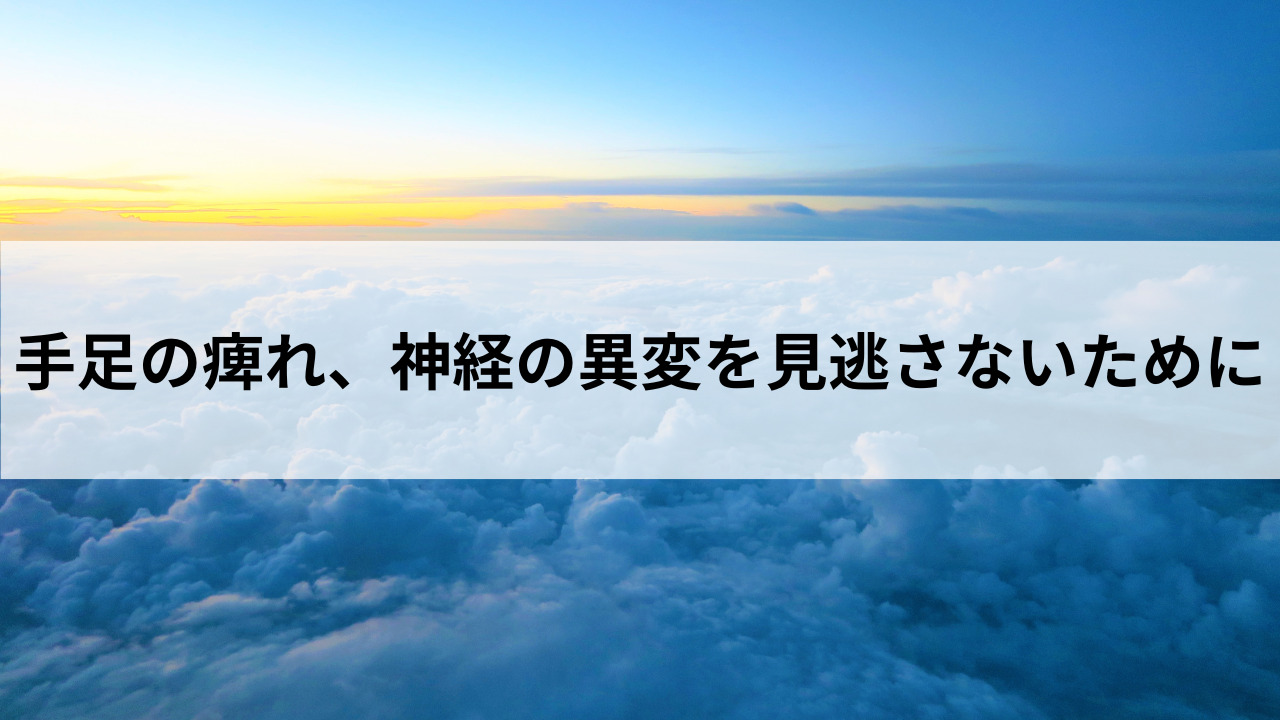
目次
- なぜ痺れる?脳卒中と神経の関係
- 痺れの種類と原因、そして対処法
- 自己判断は危険!こんな症状が出たらすぐに相談を
- 理学療法士はあなたの回復をサポートします
- まとめ
はじめに
脳卒中後のリハビリに取り組む中で手足の痺れを感じていませんか?そのうち治るだろうと軽く考えていませんか? それは回復に向かう過程で起こる一時的なものかもしれません。しかし、中には神経の回復を妨げるような問題が隠れている可能性もあります。
痺れは、あなたの体が発するSOSサインです。早期発見、早期治療でより快適な日常生活を取り戻せる可能性が広がります。今回は痺れのメカニズムから注意すべき症状、そして私たち理学療法士がどのようにサポートできるのかについて解説します。
なぜ痺れる?脳卒中と神経の関係
まず、脳卒中と神経の関係について説明します。
脳卒中は脳の血管が詰まったり破れたりすることで、その先の神経細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなる病気です。脳は体の司令塔なので、損傷を受けた場所によっては手足の運動や感覚をつかさどる神経回路も影響を受けます。
例えば「右脳の特定の場所が損傷を受けると左半身に麻痺が出る」「左脳の言語中枢が損傷すると言葉が話せなくなる」といった具合です。
1-1. 中枢神経と末梢神経
私たちの神経系は大きく分けて、脳と脊髄からなる中枢神経とそこから枝分かれして全身に広がる末梢神経から成り立っています。
中枢神経は司令官に当たる脳からの指令を伝える役割、末梢神経は脳からの指令を体の各部位に伝達したり逆に体の各部位からの情報を脳に伝えたりする役割を担っています。
脳卒中が起きるとこのどちらかあるいは両方にダメージが及ぶ可能性があります。
- 中枢神経損傷: 脳梗塞や脳出血によって脳内の神経細胞が直接ダメージを受けることで、麻痺や感覚障害などの症状が現れます。
- 末梢神経損傷: 脳卒中後の筋力低下や関節の動きの制限によって、末梢神経が圧迫されたり血流が悪くなったりすることで痺れや痛みを引き起こします。例えば、脳卒中後に腕の筋肉が硬くなってしまうとその中を通っている神経が圧迫されてしまい指先に痺れが出ることがあります。
1-2. 痺れの正体:感覚神経からのSOS
痺れは、様々な要因で感覚神経が刺激されることで起こります。感覚神経は触覚、温度、痛み、体の位置などを脳に伝える役割を担っています。脳卒中によってこの神経伝達がうまくいかなくなると以下のような痺れとして感じます。
-
異常感覚性疼痛: 実際にはない刺激を感じる、あるいは軽い触れるだけで激痛が走るなど。
例えば「焼けるように熱い」「針で刺されたようにチクチクする」といった実際には起こっていない刺激を感じる場合があります。 -
感覚鈍麻: 触れている感覚が鈍い、温度を感じにくいなど。
例えば「熱いお湯に手を入れたのに、熱く感じない」「誰かに肩を叩かれたのに、触れられた感覚がない」といった状態です。
痺れの種類と原因、そして対処法
一口に「痺れ」と言ってもその症状や原因は様々です。ここでは代表的な痺れのタイプとそれぞれの原因、そして対処法について解説します。
2-1. ピリピリ、チクチクする痺れ
まるで静電気が走っているような、あるいは針で刺されるような、鋭い痛みを伴う痺れです。
- 原因: 脳卒中後の神経の過剰興奮や神経線維の再生過程で起こる誤った神経接続などが考えられます。 脳卒中によってダメージを受けた神経は回復しようと活発に活動します。その過程で神経が過剰に興奮してしまったり、本来繋がるべき場所とは異なる場所に繋がってしまうことでこのような痺れが生じると考えられています。
2-2. 重だるい、締め付けられるような痺れ
まるで重いものを載せているような、あるいは紐で縛られているような、鈍い痛みを伴う痺れです。
- 原因: 筋力低下や関節の動きの制限によって神経や血管が圧迫されることで起こります。特に手根管症候群や胸郭出口症候群などの末梢神経絞扼性障害が疑われます。 手根管症候群は、手首の手のひら側にあるトンネル状の場所で神経が圧迫されることで、手の痺れや痛み、しびれなどが現れる病気です。胸郭出口症候群は、首の付け根にある神経や血管が鎖骨や肋骨、筋肉などに圧迫されることで肩や腕、手に痺れや痛み、冷えなどの症状が現れる病気です。
2-3. 冷たい、熱いなど、温度感覚の異常
熱いものに触れても熱さを感じなかったり、逆に冷たいものに触れたときに過剰に冷たさを感じたりするなどの温度感覚に異常が生じる痺れです。
- 原因: 脳卒中による感覚神経の損傷が考えられます。 脳卒中によって温度を感じる感覚神経がダメージを受けることで温度を正しく感じることができなくなります。
自己判断は危険!こんな症状が出たらすぐに相談を
痺れの中には、放置すると症状が悪化したり日常生活に支障をきたすものもあります。自己判断せずに早めに医療機関を受診しましょう。
3-1. 緊急性の高い症状
以下の症状が出た場合は、一刻も早く救急車を呼ぶか周りの人に助けを求めて病院へ向かいましょう。
- 突然の激しい痺れや麻痺: 新たな脳卒中の発症の可能性があります。 今まで経験したことのないような強い痺れや麻痺が急に出現した場合は、脳卒中が再発している可能性があります。
- 意識障害、ろれつが回らない、激しい頭痛: 脳出血やクモ膜下出血などの緊急性の高い病気が疑われます。 意識が朦朧としたり、呂律が回らなくなったり、今までに経験したことがないような激しい頭痛が起こった場合は、脳内で重大な事態が発生している可能性があります。
- 排尿・排便障害: 脊髄に障害が及んでいる可能性があります。 尿や便が出にくくなったり、逆に漏れてしまうようになった場合は、脊髄に障害が及んでいる可能性があります。
3-2. 専門家への相談が必要な症状
以下の症状がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し医師や理学療法士に相談しましょう。
- 日常生活に支障が出るほどの痺れ: 着替えや食事、歩行などが困難になるほどの痺れ。 痺れのせいで日常生活に支障が出ている場合は、症状が進行する前に適切な治療やリハビリテーションを受ける必要があります。
- 夜間や安静時に強くなる痺れ: 神経の圧迫や血流障害が進行している可能性があります。 日中は気にならない程度の痺れでも夜間や安静時に強くなる場合は神経の圧迫や血流障害が悪化している可能性があります。
- 痺れ以外に、筋力低下や筋肉の萎縮を伴う: 神経の損傷が進行している可能性があります。 痺れに加えて、筋力低下や筋肉の萎縮が見られる場合は、神経の損傷が進行している可能性があります。
理学療法士はあなたの回復をサポートします
理学療法士は、患者様一人ひとりの症状や状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し日常生活の動作改善や社会参加の促進を支援する専門家です。
4-1. 詳細な評価で原因を特定
理学療法士は、医師の診断結果を踏まえ、患者様一人ひとりの痺れの原因を特定するために以下の評価を行います。
- 問診: 痺れの症状、病歴、日常生活の様子などを詳しく伺います。
- 感覚検査: 触覚、痛覚、温度覚、振動覚などを評価します。
- 関節可動域検査: 関節の動く範囲や動きやすさを評価します。
- 筋力検査: 筋肉の力強さや持久力を評価します。
- 神経学的検査: 神経の働きを評価します。
4-2. あなたに最適なリハビリテーションを
評価結果に基づいて運動療法、物理療法、日常生活動作訓練などを組み合わせた最適なリハビリテーションプログラムを作成します。
- 運動療法: 関節可動域訓練、ストレッチ、筋力トレーニングなどを通して神経や血管への圧迫を軽減し、痺れの改善を図ります。
- 物理療法: 温熱療法、冷却療法、電気刺激療法などを用いて痛みや痺れの軽減を図ります。
- 日常生活動作訓練: 着替えや食事、トイレ動作などの練習を通して日常生活の動作を改善します。
4-3. 再発予防と日常生活のアドバイス
痺れの再発を予防するためのストレッチや運動方法の指導、日常生活での注意点などのアドバイスも行います。
- 再発予防のアドバイス: 痺れの原因となった動作や姿勢、環境因子などを特定し再発を防ぐための方法をアドバイスします。
- 日常生活でのアドバイス: 入浴方法や衣服の着脱方法、睡眠時の姿勢など、日常生活で気を付けるべき点についてアドバイスします。
痺れは、あなたの体が発する重要なサインです。決して一人で悩まず、私たち理学療法士にご相談ください。私たちはあなたの回復を全力でサポートします。
まとめ
脳卒中後の手足の痺れは、神経の損傷によるものが多く見られます。その症状は、ピリピリやチクチクする痛み、重だるい痛み、温度感覚の異常など様々です。痺れは体のSOSサインであり早期に対処することが重要です。特に、突然の激しい痺れや麻痺、意識障害、激しい頭痛などの緊急性の高い症状が現れた場合はすぐに医療機関に相談しましょう。
理学療法士は詳細な評価を行い、患者一人ひとりに最適なリハビリプログラムを提供します。適切なリハビリテーションを受けることで日常生活の質を向上させることができます。痺れやその他の症状でお悩みの際は、自己判断せずに専門家に相談することが大切です。