延髄梗塞後の予後とリハビリテーション(嚥下機能に焦点を当てて)
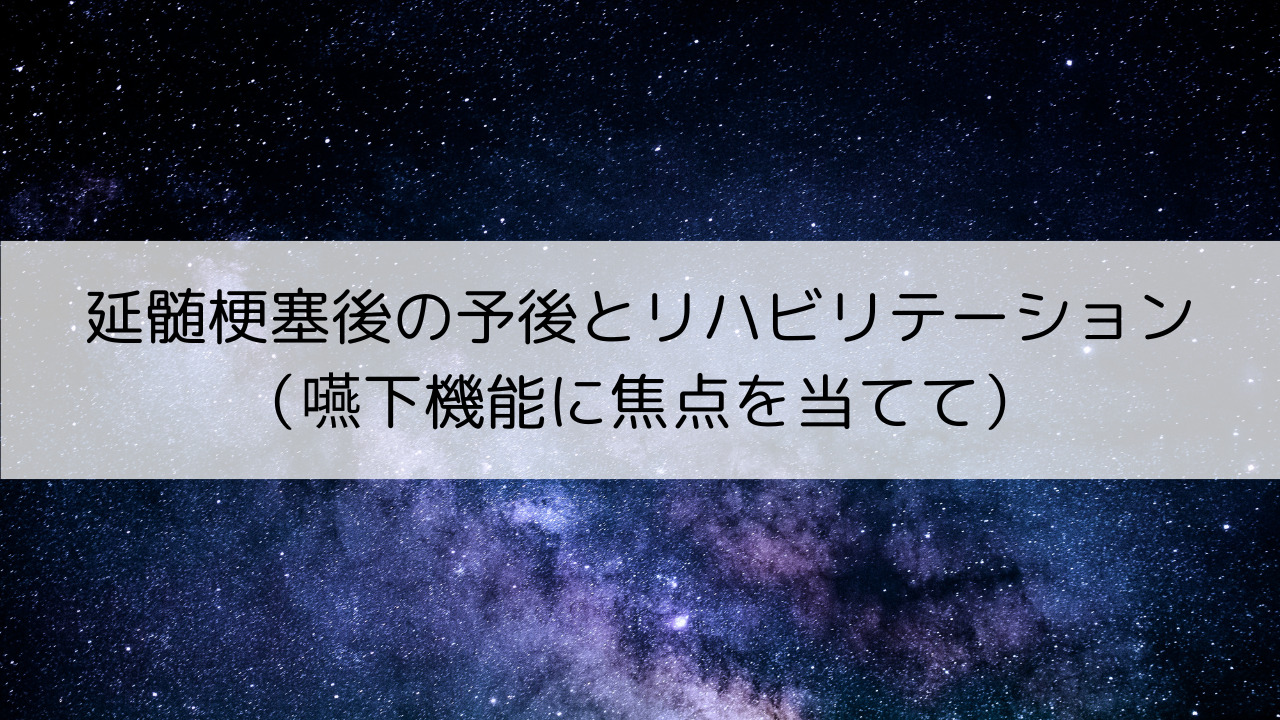
はじめに
脳卒中の中でも延髄梗塞は、私たちの健康と生活の質に深刻な影響を与える可能性があります。延髄は脳幹という脳の深部にある重要な部分であり、呼吸、心拍数、血圧といった生命維持に不可欠な機能をコントロールしています。この延髄に血液を送る血管が詰まったり破れたりすると延髄梗塞が起こります。今回は、その中でも嚥下機能に着目して本稿を投稿します。
目次
- 延髄梗塞がもたらす症状とその後の見通し
- 延髄梗塞のリハビリテーション
- 嚥下機能に焦点を当てたリハビリテーション
- 嚥下障害(その詳細と予防)
延髄梗塞がもたらす症状とその後の見通し
延髄梗塞の症状は障害された部位によって多岐にわたりますが、一般的には運動障害、感覚障害、嚥下障害、構音障害、複視、眼振、嘔気・嘔吐、眩暈、意識障害などが現れます。これらの症状の中でも、嚥下障害は食べ物を飲み込みにくくなる症状であり、誤嚥性肺炎や栄養不良のリスクを高めるため患者さんの予後を大きく左右する要因となります。
延髄梗塞後の見通し(予後)は、年齢、合併症の有無、梗塞の大きさ、発症からの時間などの様々な要因によって異なります。一般的には、高齢者や合併症のある方や梗塞が大きいほど予後が悪い傾向があります。また、発症後早期に適切な治療を開始できるほど予後が良いとされています。延髄梗塞の死亡率は約10%と報告されていますが、合併症の有無によって変動します。生存した場合でも、後遺症が残る可能性がありその程度も人それぞれです。

延髄梗塞のリハビリテーション
延髄梗塞のリハビリテーションは、患者さんの機能回復を促し生活の質を向上させることを目的としています。リハビリテーションは、急性期から回復期、そして維持期まで患者さんの状態に合わせて段階的に行われます。
急性期リハビリテーション(生命維持と合併症予防)
急性期リハビリテーションでは、生命維持を最優先とし合併症の予防に努めます。呼吸管理や循環管理、栄養管理などを行いながら、意識レベルの改善や運動機能の回復を促します。
回復期リハビリテーション(日常生活動作の自立を目指して)
回復期リハビリテーションでは、積極的に運動療法や作業療法を行い日常生活動作の自立を目指します。嚥下訓練や構音訓練などの高次脳機能障害に対するリハビリテーションも行い、患者さんの心理的なサポートも行います。
維持期リハビリテーション(退院後の生活を支援)
維持期リハビリテーションでは、退院後の生活を見据えて在宅でのリハビリテーションや社会参加を支援します。運動機能の維持や悪化予防、生活習慣病の管理などを行います。
嚥下機能に焦点を当てたリハビリテーション
延髄梗塞では、嚥下障害が高頻度に見られるため、嚥下機能に焦点を当てたリハビリテーションが非常に重要になります。嚥下訓練は、嚥下に関わる筋肉を鍛える訓練や食べ物を安全に飲み込むための練習などがあります。
嚥下訓練を始める前に、言語聴覚士が患者さんの嚥下機能を詳しく評価します。問診や嚥下造影検査、内視鏡検査などを行い、患者さんの状態に合わせた訓練内容を決定します。
嚥下訓練には間接訓練と直接訓練があります。間接訓練は、嚥下に関わる筋肉を鍛える体操や唾液を飲み込む練習などを行います。直接訓練は、実際に食べ物や飲み物を使って安全に飲み込む練習を行います。
食事の工夫も嚥下リハビリテーションの一環です。食べ物の形態や硬さを工夫し飲み込みやすいようにします。また、姿勢を工夫し誤嚥しにくいようにします。補助具を使用して食事をサポートする場合もあります。
嚥下訓練を行うことで、嚥下機能の改善、誤嚥性肺炎の予防、栄養状態の改善、生活の質の向上といった効果が期待できます。

嚥下障害(その詳細と予防)
嚥下障害は、食べ物を口から胃まで送り込む過程に障害が生じる状態です。延髄梗塞では、嚥下に関わる神経や筋肉が障害されることで嚥下障害が起こります。
嚥下障害には、食べ物や飲み物が口の中に残る、喉に詰まる、咳き込む、むせる、鼻に入る、唾液が口からこぼれるといった症状があります。
嚥下障害があると誤嚥性肺炎、栄養不良、脱水、窒息といったリスクが高まります。
嚥下障害を予防するためには姿勢を正して食事をする、ゆっくりとよく噛んで食べる、食べ物を小さく切って食べる、柔らかい食べ物を選ぶ、飲み込みやすいようにとろみをつける、口腔内を清潔に保つといった点に注意することが大切です。
まとめ
延髄梗塞後の予後は、患者さんの状態や合併症の有無によって異なりますが、適切な治療とリハビリテーションを行うことで機能回復を促し、生活の質を向上させることができます。特に嚥下機能に焦点を当てたリハビリテーションは、患者さんの予後を大きく左右する可能性があります。具体的な治療法やリハビリテーションについては、必ず医師や専門家にご相談ください。

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。