右片麻痺(まひ)とは?原因と主な症状
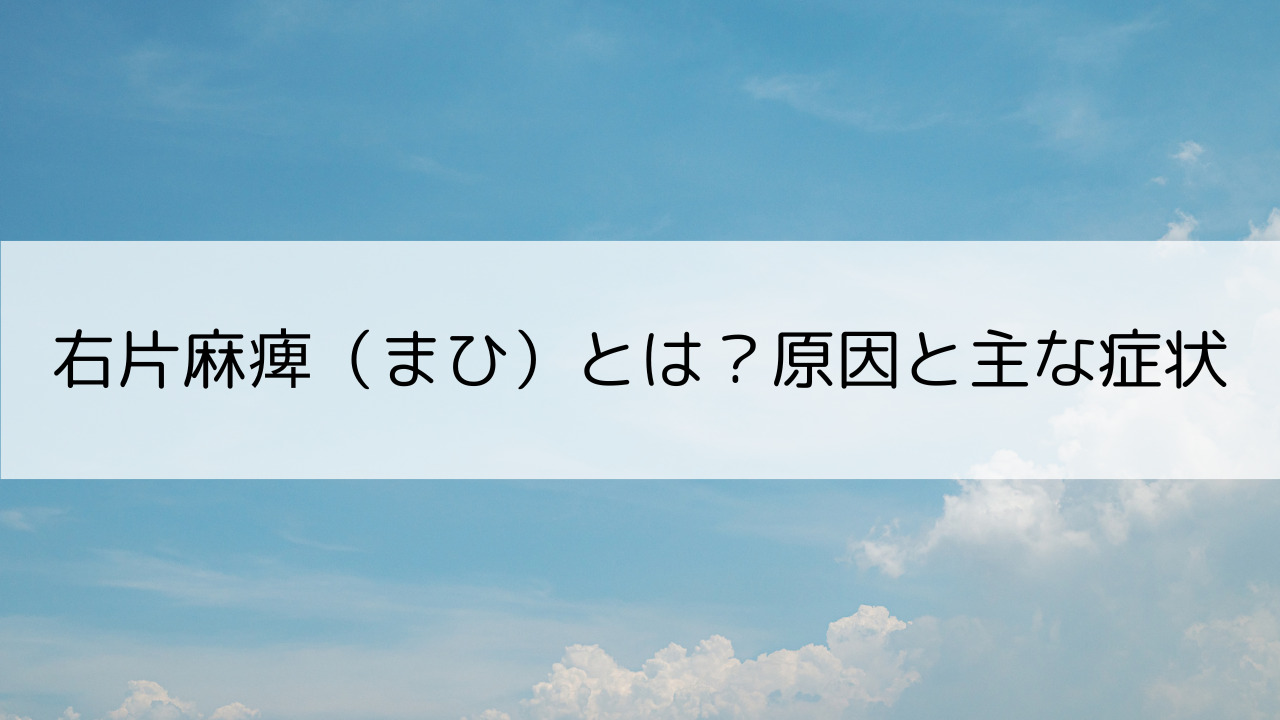

はじめに
右片麻痺とは、脳の左半球が損傷することで体の右側に運動障害が起こる状態です。
主な原因は脳卒中で、その他には外傷や腫瘍、神経系の病気も考えられます。
本稿は、右片麻痺に関する理解を深めると共に、当施設における改善事例の紹介を行います。
-
当施設における改善事例はこちら
右上肢の改善を目的に来所され、ついに趣味のキャンプに行く事が可能になった方
目次
- 右片麻痺とは?
- 右片麻痺の方が日常生活で困ること
- 脳卒中はどうして右片麻痺を引き起こすの?
- 上肢と下肢(足)ではどちらの回復が難しい?
- 上肢の回復を妨げる「学習された非使用」とは?
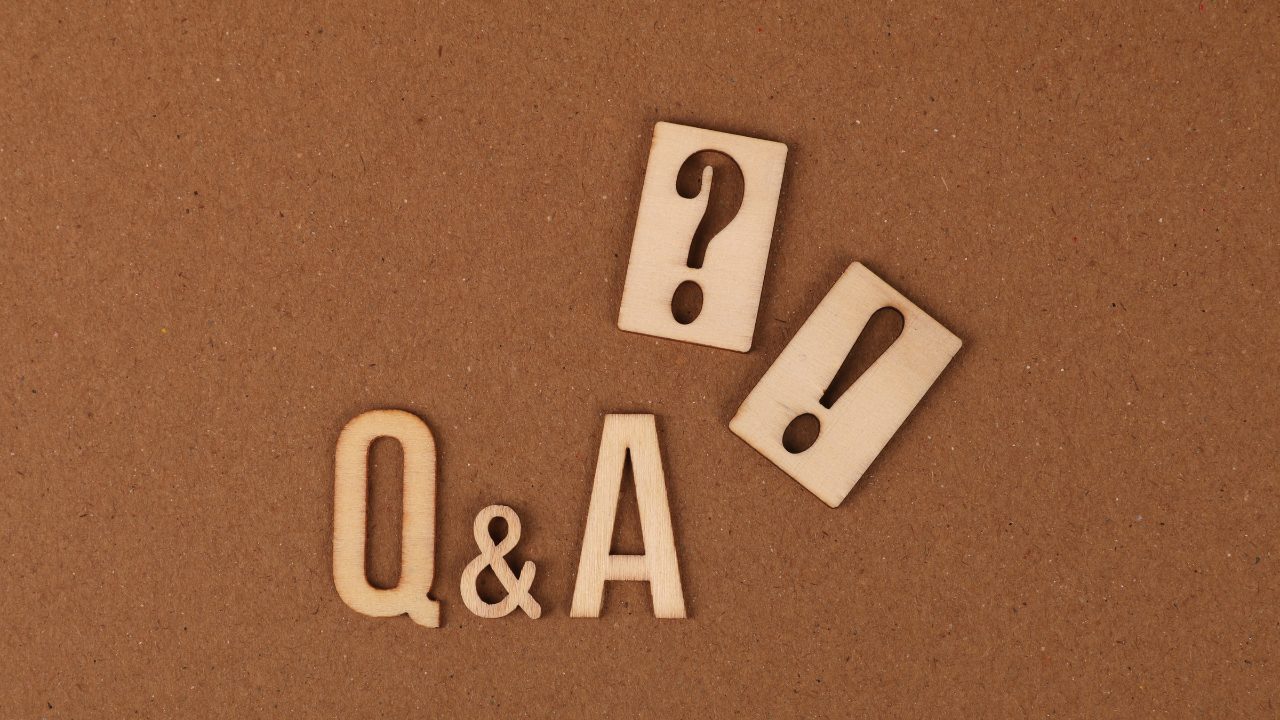
右片麻痺とは?
症状は人によって様々ですが、一般的には以下の様な症状が現れます。
- 右側の手足の運動能力の低下
- 右側の感覚の喪失
- 言葉が出にくい、または理解しにくい(失語症)
- 左側の空間を認識しにくい、または認識できない(半側空間無視)
リハビリでは、運動療法で筋力や柔軟性を高めたり、作業療法で日常生活での動作を練習したり、言語療法で言葉の回復を目指したりします。
特に手の力は日常生活に大きく影響するため、集中的なリハビリが必要です。
麻痺していない側の手をあえて使わないようにする「強制的使用」も麻痺側の手の機能回復に効果があると言われています。
回復の程度は、脳の損傷の大きさやリハビリの開始時期、年齢や健康状態によって異なります。
適切なリハビリを続けることで多くの方が機能回復を実感していますが、完全に元通りになることは難しい場合もあります。

右片麻痺の方が日常生活で困ること
右片麻痺になると日常生活の様々な場面で困難を感じることがあります。
例えば、歩行や立ち上がりが難しくなったり、食事や着替え、入浴などの日常的な動作が困難になったりします。
特に麻痺している側の手が使えないと生活は大きく制限されます。
また、左側の空間を認識しにくくなることで、物にぶつかったり、転倒したりするリスクが高まります。
言葉が出にくかったり、理解しにくかったりすると周りの人とのコミュニケーションが難しくなり、社会的に孤立してしまうこともあります。
これらの身体的な制限や社会的な孤立感から、うつ病や不安障害になる方も少なくありません。
しかし、適切なリハビリを続けることで、これらの課題を克服し、より質の高い日常生活を送ることが可能です。
脳卒中はどうして右片麻痺を引き起こすの?
脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳に血液が流れなくなり脳細胞がダメージを受ける病気です。
右片麻痺は、脳の左半球にある運動機能をコントロールする領域がダメージを受けることで起こります。
脳卒中には大きく分けて2つの種類があります。
脳の血管が詰まる「虚血性脳卒中」と血管が破れる「出血性脳卒中」です。
どちらの脳卒中が起こっても、左半球の運動野がダメージを受けると右半身に麻痺が起こります。
運動指令を伝える神経経路がダメージを受けると右側の手足が動きにくくなります。
動脈硬化や高血圧などの生活習慣病があると、脳卒中のリスクが高まり、右片麻痺になる可能性も高まります。
また、最近では新型コロナウイルス感染症も血液を固まりやすくし、脳卒中を引き起こすリスクを高めることが分かってきました。

上肢と下肢(足)ではどちらの回復が難しい?
脳卒中後のリハビリにおいて、上肢と下肢のどちらの回復が難しいかという疑問は多くの方が持つ疑問です。
一般的には、上肢の回復の方が下肢よりも難しいと言われています。
上肢の運動機能は脳の運動野からの神経経路に大きく依存しています。
脳卒中によってこれらの経路がダメージを受けると上肢の運動機能は著しく低下し回復が難しくなります。
また、脳卒中患者さんは麻痺していない側の上肢を使うことで日常生活の動作を補うことが多く、麻痺している側の上肢を使う機会が減ってしまいます。
これを「学習された非使用」といい、麻痺している側の上肢の回復を妨げる要因となります。
一方、下肢の機能は歩行や移動に直接関わるため、リハビリの初期段階では下肢の回復が優先されることが多いです。
また、下肢のリハビリは、歩行訓練やバランス訓練などの具体的な動作に焦点を当てやすく比較的早く回復が進むことがあります。
研究結果を見ても、上肢の機能回復は下肢に比べて遅れる傾向があり、特に上肢の運動機能は回復が難しいとされています。
上肢の回復には脳の神経可塑性が重要ですが、十分に機能しない場合は上肢の機能回復がさらに難しくなります。
脳卒中後のリハビリでは、患者さんの状態に合わせて上肢と下肢の両方に焦点を当てることが重要です。

上肢の回復を妨げる「学習された非使用」とは?
「学習された非使用」とは、脳卒中などで脳がダメージを受けた後に、麻痺していない側の手や腕を使うことで麻痺している側の手や腕を使わなくなる現象です。
この現象は、患者さんが麻痺している側の上肢を使うことに自信を失い、結果的にその機能がさらに低下することを引き起こします。
脳卒中後、麻痺している側の上肢を使うことが減るとその側の脳の運動領域の神経可塑性が低下し、機能的な回復が妨げられます。
また、患者さんは麻痺している側の上肢を使うことに恐怖感や不安を抱くことが多く、成功体験が少ないため使うことを避けるようになります。
「学習された非使用」は、リハビリの効果を低下させる要因となります。
麻痺している側の上肢を積極的に使うことが重要ですが、患者さんが使うことを避けることでリハビリの進行が妨げられます。
この現象を克服するためには、制約誘導運動療法(CIMT)などの治療法が有効です。
CIMTでは、麻痺していない側の上肢を制限し、麻痺している側の使用を促すことで機能回復を促進します。
最近の研究では「学習された非使用」の理解を深めるための取り組みが進められています。
特に神経機構やリハビリ戦略の改善に向けた研究が行われており、患者さんの機能回復を支援する新たな方法が模索されています。
「学習された非使用」は、脳卒中後の上肢の機能回復において重要な課題です。
この現象を理解し、克服するための適切なリハビリ戦略が必要です。

まとめ
右片麻痺は、脳の左半球がダメージを受けることで体の右側に運動障害が起こる状態です。
脳卒中が主な原因であり、その他にも外傷や腫瘍、神経系の病気などが考えられます。
リハビリでは、運動療法や作業療法、言語療法などを行い機能回復を目指します。
上肢の回復は下肢に比べて難しいとされており、「学習された非使用」という現象が回復を妨げることがあります。
しかし、適切なリハビリを続けることで、多くの方が機能回復を実感しているため、リハビリを継続していく環境を大事にしていく必要があると考えます。
-
当施設における改善事例はこちら
右上肢の改善を目的に来所され、ついに趣味のキャンプに行く事が可能になった方

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。