半側空間無視とは?最新のリハビリ治療法について解説
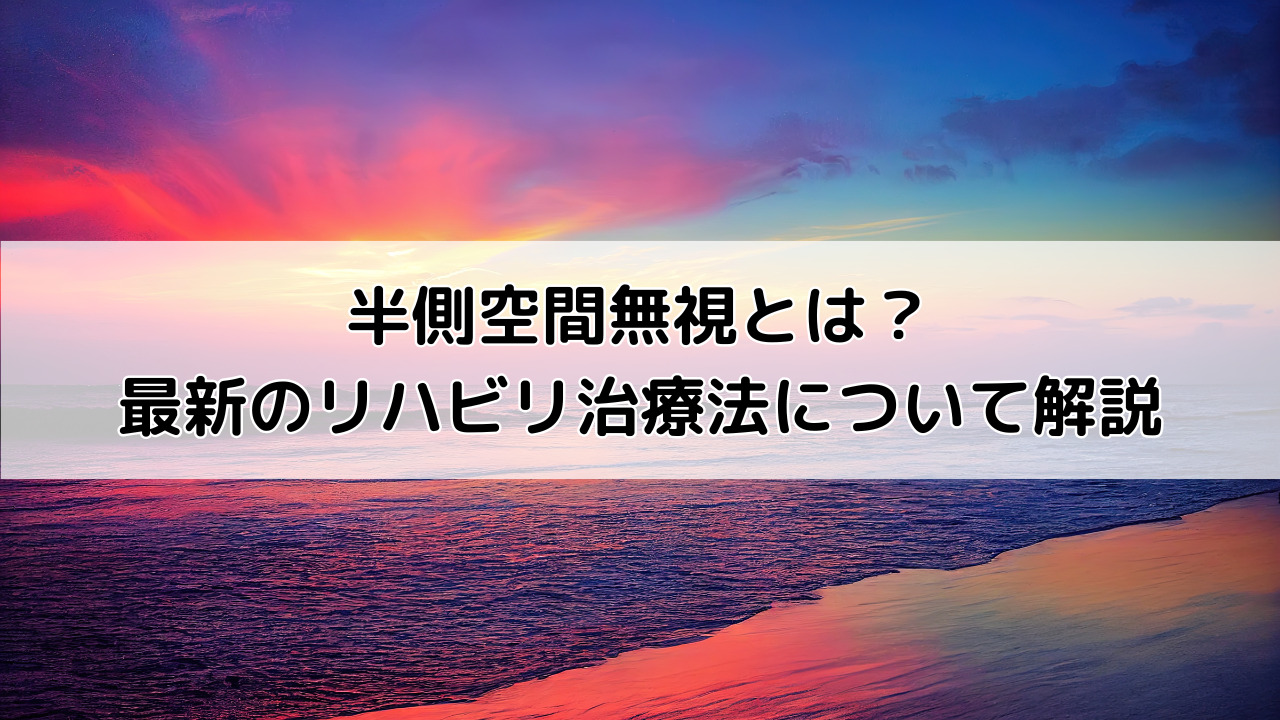
はじめに
半側空間無視とは、患者本人が「左側に意識を向けられない」だけでなく、「そもそも左側の存在に気づかない」という点で非常に厄介です。
見えてはいるのに“認識できない”という、脳の情報処理に関わる問題なのです。
今回、脳血管疾患と関連性が高い半側空間無視の症状と最新のリハビリ事情について解説していきます。
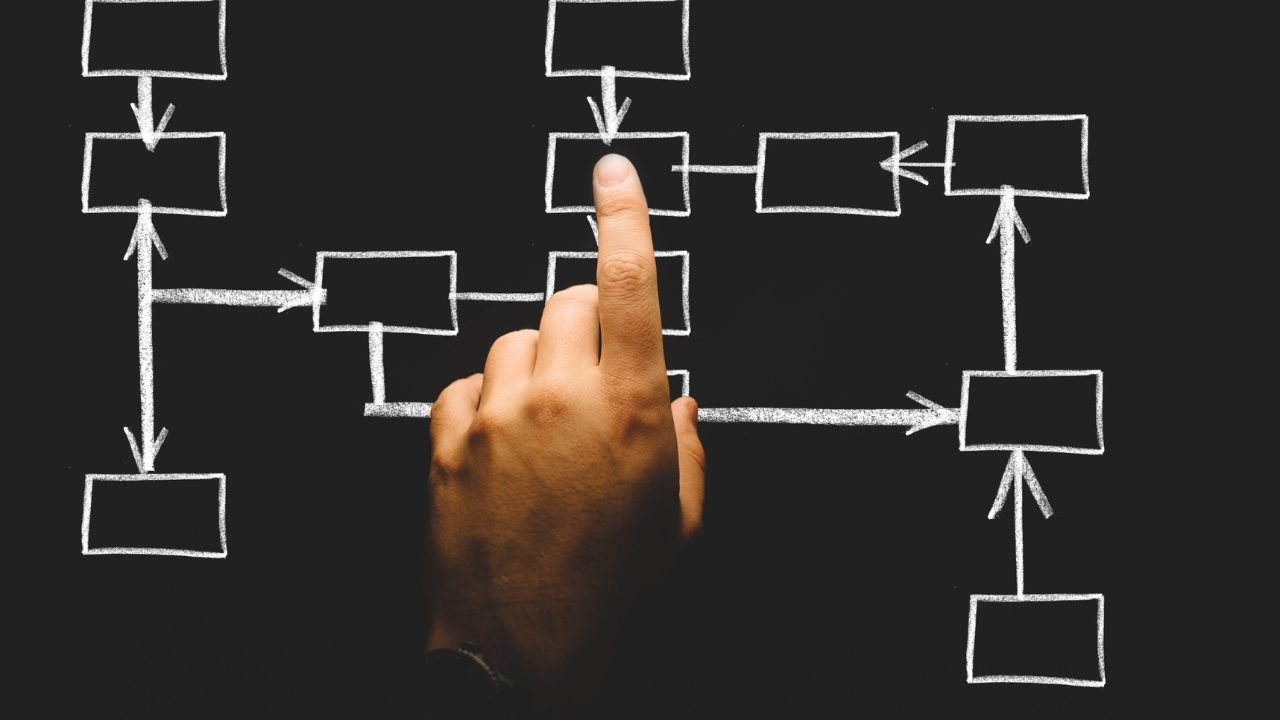
目次
- 半側空間無視とはどのような障害か?
- 脳卒中との深い関連性
- 半側空間無視に対するリハビリアプローチ
- 経頭蓋磁気刺激(TMS)について
半側空間無視とはどのような障害か?
半側空間無視(Hemispatial Neglect)は、主に脳卒中や頭部外傷などによって脳の片側、特に右脳が損傷を受けたときに見られる認知障害です。
特徴的なのは、視力や身体機能には問題がないにもかかわらず、視覚的・聴覚的・触覚的な刺激に対して、片側(多くの場合は左側)への注意が著しく低下することです。
たとえば、左側にある食事を残してしまったり、左側の洋服のボタンを留め忘れるなど日常生活にも多くの影響が出ます。
脳卒中との深い関連性
半側空間無視は、特に右脳の損傷を伴う脳卒中の後に高い頻度で見られます。
統計によると、右脳卒中患者の約80%に何らかの形でこの症状が出現すると言われています。
左脳卒中でも発症することはありますが、その頻度は右脳の場合に比べて低く、約43.5%程度です。
この障害は、単なる見落としや注意散漫と違い、リハビリの過程でも課題となりやすく、特に生活動作(ADL)や社会復帰に大きく関わってくるため、早期の評価と的確な介入が重要です。
半側空間無視に対するリハビリアプローチ
半側空間無視のリハビリには、脳の可塑性(=脳が損傷後に再構築される能力)を活かした方法がいくつも存在します。
ここでは、実際の現場で用いられている代表的な治療法をご紹介します。
視覚探索訓練
視覚探索訓練は、患者さんが無視している側(多くは左側)に意識を向ける練習です。
例えば、視覚的な課題(絵や文字など)を使って、視線を左側に動かすよう繰り返し訓練することで、注意の範囲を広げる効果があります。
根気強い反復が求められますが、効果が見られる方法の一つです。
プリズム眼鏡の活用
プリズム眼鏡は、視野を人工的にずらすことによって、無視されている側の空間を視界に入れやすくする装置です。
たとえば、視界を右に少しずらすことで、実際には左側にある物が“中央にある”ように感じられるようになり、その結果、左側の注意が促されるという仕組みです。
リハビリとの併用で効果が期待されます。

バーチャルリアリティ(VR)を用いたリハビリ
近年注目を集めているのが、VR技術を活用したリハビリです。
仮想空間の中で視覚的に情報を提示し、患者が左側へ目や身体を向けるよう誘導します。
楽しく取り組みやすく、従来のリハビリよりも集中力が持続しやすいというメリットもあります。
アイパッチ療法
健側(通常は右側)の視界をアイパッチで一時的に遮ることで、無視している左側への注意を意図的に引き出す手法です。
あくまで補助的な役割として使われることが多く、単独ではなく他の治療法と組み合わせることで効果が出やすくなります。
聴覚的な手がかりの利用
視覚だけでなく、音の刺激も有効な手段となります。
たとえば、左側から意図的に音を出すことで、聴覚を通じて左側への注意を引き出します。
これは、視覚よりも反応しやすい患者に有効で、環境音や声かけなどを利用するケースもあります。
スペイティオモーターキューイング(運動刺激による誘導)
これは、左側の上肢(腕)を意図的に動かすことで、左側への注意を高める方法です。
身体の動きと注意の方向が連動することを利用して、視覚的・空間的な注意力を回復させる目的があります。
経頭蓋磁気刺激(TMS)
TMS(Transcranial Magnetic Stimulation)は、近年注目を集めている先進的なリハビリ手法です。
これは磁気パルスを用いて脳の特定の部位に非侵襲的な刺激を与えることで、神経細胞の活動を活性化させる技術です。
経頭蓋磁気刺激(TMS)について
今回、TMSという言葉になじみのない方が多いと思われる為、今回紹介させていただきます。

神経活動の調整と再構築
TMSによる磁気刺激は、神経細胞の膜電位を変化させ、神経伝達物質の分泌を促します。
これにより、損傷した脳の部位やその周辺の神経活動が活性化され、情報の伝達効率が改善されていきます。
また、TMSはシナプス強化、特に「長期増強(LTP)」という学習や記憶の基盤となる神経の結合を強くするプロセスを促します。
これにより、失われた機能の回復を脳自身が補うように再構築していくのです。
神経栄養因子の増加と持続効果
さらに、TMSは脳由来神経栄養因子(BDNF)といった神経の成長を助ける物質の分泌を促進するとされています。
この因子は神経細胞の保護や成長に関わるもので、結果として長期的な脳の回復にもつながります。
TMSの臨床での効果は?
TMSは、特に右脳卒中に伴う半側空間無視の改善において、多くの研究で有効性が示されています。
例えば、反復的なTMS(rTMS)を使用した場合、注意力が高まり、日常生活での動作がスムーズになったという報告があります。
また、TMSは単独で使用されることもありますが、他のリハビリ訓練と併用することでより高い効果が期待されます。
リハビリの前後にTMSを組み合わせることで、脳の準備状態が整い、その後の訓練がより効率的になるのです。
ある研究では、TMS施行後に行動性無視検査(BIT)という検査のスコアが大きく改善し、その効果が数週間にわたって持続したという例も報告されています。
まとめ
半側空間無視は、視覚や運動に問題がないにもかかわらず、脳の損傷によって片側の空間を「無視」してしまう厄介な症状です。
日常生活への影響が大きいため、正しい理解と継続的なリハビリが非常に重要になります。
リハビリの方法には、視覚探索訓練やプリズム眼鏡、VR、アイパッチ、音の手がかり、運動刺激など、多様なアプローチがあり、患者一人ひとりに合わせて組み合わせていくことが成功の鍵となります。
さらに、最新の治療法として注目されている経頭蓋磁気刺激(TMS)は、脳の可塑性を促進し、他のリハビリ訓練の効果を底上げする可能性があります。
TMSはまだ比較的新しい技術ではありますが、今後ますます活用が期待される治療法です。
ご質問があれば、お気軽に当施設にお問い合わせください。
-
動画の配信を行っております。
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。