くも膜下出血後の生活(社会復帰に向けて)
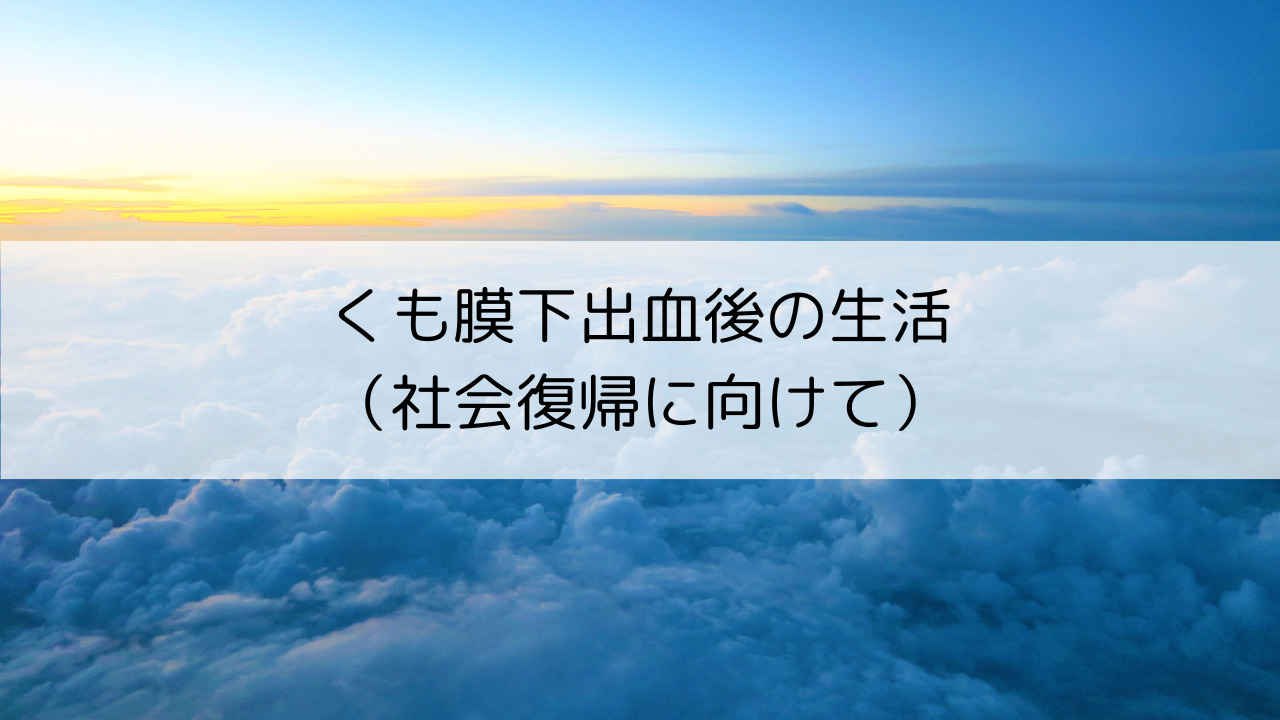
はじめに
くも膜下出血(くもまくかしゅっけつ、Subarachnoid Hemorrhage, SAH)は、脳を覆う膜の一つであるクモ膜と脳の間に出血が起こる非常に重篤な疾患です。
この出血は主に脳動脈瘤の破裂によって引き起こされますが、頭部外傷や動静脈奇形が原因となることもあります。
くも膜下出血は突然発症し、適切な治療が行われないと死亡や重篤な後遺症をもたらす可能性が非常に高い病態です。
本稿は、くも膜下出血に関するお話と予後である社会復帰に向けた内容で投稿いたします。
また、当施設における改善事例はこちらです。
くも膜下出血後、装具を外して外を歩けた!

目次
- くも膜下出血とは
- くも膜下出血の主な症状
- 診断と治療法
- 予後と後遺症
- リハビリテーションと社会復帰
- 社会復帰の可能性と課題
くも膜下出血とは
くも膜下出血は、脳の血管にできた動脈瘤が破裂することで脳の表面にあるクモ膜と脳の間に出血が広がる状態を指します。
この出血は、脳に深刻なダメージを与えるため様々な神経学的症状を引き起こします。
くも膜下出血の主な症状
くも膜下出血は以下のような症状を特徴とします。
- 突然の激しい頭痛:「雷鳴のような頭痛」と表現されるほどにこれまでに経験したことのないような激しい痛みが突然襲います。
- 意識障害:意識を失うことがあり、重症の場合は昏睡状態に陥ることもあります。
- その他の症状:吐き気、嘔吐、首の痛み、視覚障害、けいれんなどが見られます。
これらの症状は出血の程度や発生した部位によって異なりますが、いずれも緊急の医療対応が必要です。

診断と治療法
くも膜下出血が疑われる場合、迅速な診断と治療が重要です。
診断方法
CTスキャンやMRIなどの画像診断により、出血の有無と原因を特定します。
必要に応じて腰椎穿刺を行い、脳脊髄液の検査を行います。
治療法
- 手術療法:破裂した動脈瘤に対して、クリッピング術やコイル塞栓術などの手術を行い再出血を防ぎます。
- 薬物療法:血圧管理や脳血管の痙攣を防ぐ薬剤を使用し、合併症のリスクを低減します。
予後と後遺症
くも膜下出血の予後は、発症時の重症度、治療の迅速さ、患者の年齢などによって大きく左右されます。
予後の概要
- 発症後の死亡率は30~50%と高く、特に病院到着前に死亡するケースも少なくありません。
- 生存者の約1/3は何らかの障害を抱えることになります。
- 初回の出血後、24時間以内の再出血リスクが高く、これが死亡率をさらに高める要因となります。
影響を与える要因
- 年齢が高齢者ほど予後が悪い傾向があります。
- 発症時の意識障害が重いほど回復が難しくなります。
- 早期の適切な治療が予後の改善に大きく寄与します。
主な後遺症
くも膜下出血を生き延びた患者の約50%に何らかの神経学的な障害が残るとされています。
主な後遺症としては、以下のようなものがあります。
- 運動機能障害では、手足の麻痺や運動機能の低下が見られます。
- 認知機能障害では、記憶力や思考能力の低下、高次脳機能障害などが起こります。
- 言語障害では、言葉を話す、理解する能力の低下が見られます。
- 感覚障害では、しびれや痛覚異常などが生じます。
- 視覚障害では、視野欠損や視力低下などが起こります。
- 精神的影響では、うつ病や不安障害などが起こりやすくなります。
これらの後遺症は、患者の日常生活に大きな影響を与え、社会復帰を困難にする要因となります。

リハビリテーションと社会復帰
くも膜下出血後のリハビリテーションは患者の機能回復と社会復帰に不可欠な要素です。
リハビリの目的
- 運動機能や日常生活動作の改善といった機能回復
- 言語療法や作業療法を通じて認知機能やコミュニケーション能力の回復を図る認知機能の向上
- 心血管系の健康管理を行い再発のリスクを低減する再発防止
この3つがあげられます。
リハビリの段階
リハビリテーションは、急性期、回復期、維持期の3段階で進められます。
- 急性期では、発症直後に行うベッド上での運動や呼吸訓練が中心です。
- 回復期では、入院中に理学療法や作業療法を集中的に行い、日常生活動作の向上を目指します。
- 維持期では、退院後の自宅やリハビリ施設で継続的な運動と生活習慣の改善を行います。
リハビリの方法
リハビリの方法は、理学療法、作業療法、言語療法の3つがあげられます。
- 理学療法では、筋力トレーニングやストレッチを行い身体機能の回復を図ります。
- 作業療法では、日常生活に必要な動作の再学習や生活環境への適応訓練を行います。
- 言語療法では、言語やコミュニケーション能力の回復を目指し言語障害の改善を図ります。
リハビリの効果
- 運動機能や日常生活動作の向上が期待できる機能的改善
- 社会復帰の可能性向上
- 自立した生活を送るための支援が得られる生活の質の向上
- 適切な運動と生活習慣の維持により、再発防止や健康維持に繋がる長期的な健康管理
といった効果が得られます。
社会復帰の可能性と課題
くも膜下出血後の社会復帰は後遺症の程度によって大きく異なります。
社会復帰できる確率
- 軽症の場合:約70%が社会復帰可能です。
- 重症の場合:社会復帰率は大幅に低下します。
社会復帰の障壁
- 運動機能や認知機能の障害:仕事や日常生活に必要な能力が低下します。
- 精神的健康の問題(うつ病、不安障害):社会生活への意欲や適応能力が低下します。
- 社会的認知の障害(対人関係や職場適応の困難):コミュニケーション能力や社会的な状況理解が困難になります。
これらの障壁を乗り越えるためには、患者自身の努力だけでなく、家族や医療スタッフ、職場などの周囲のサポートが不可欠です。
まとめ
くも膜下出血は、非常に重篤な疾患であり迅速な診断と適切な治療が生存率の向上に不可欠です。
発症後のリハビリテーションが機能回復と社会復帰に大きく寄与し、患者の生活の質を向上させる鍵となります。
患者自身の努力だけでなく、家族や医療スタッフのサポートが社会復帰の成功に不可欠です。
くも膜下出血は誰にでも起こりうる病気です。
日頃から健康に気を配り、激しい頭痛などの症状が現れた場合には、ためらわずに救急車を呼ぶなどの対応をしてください。
ご質問がありましたら、いつでもお問い合わせのご連絡をいただければ幸いです。
当施設における改善事例はこちら
くも膜下出血後、装具を外して外を歩けた!

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。