堺市【脳の可塑性に着目!】最新のリハビリテーション
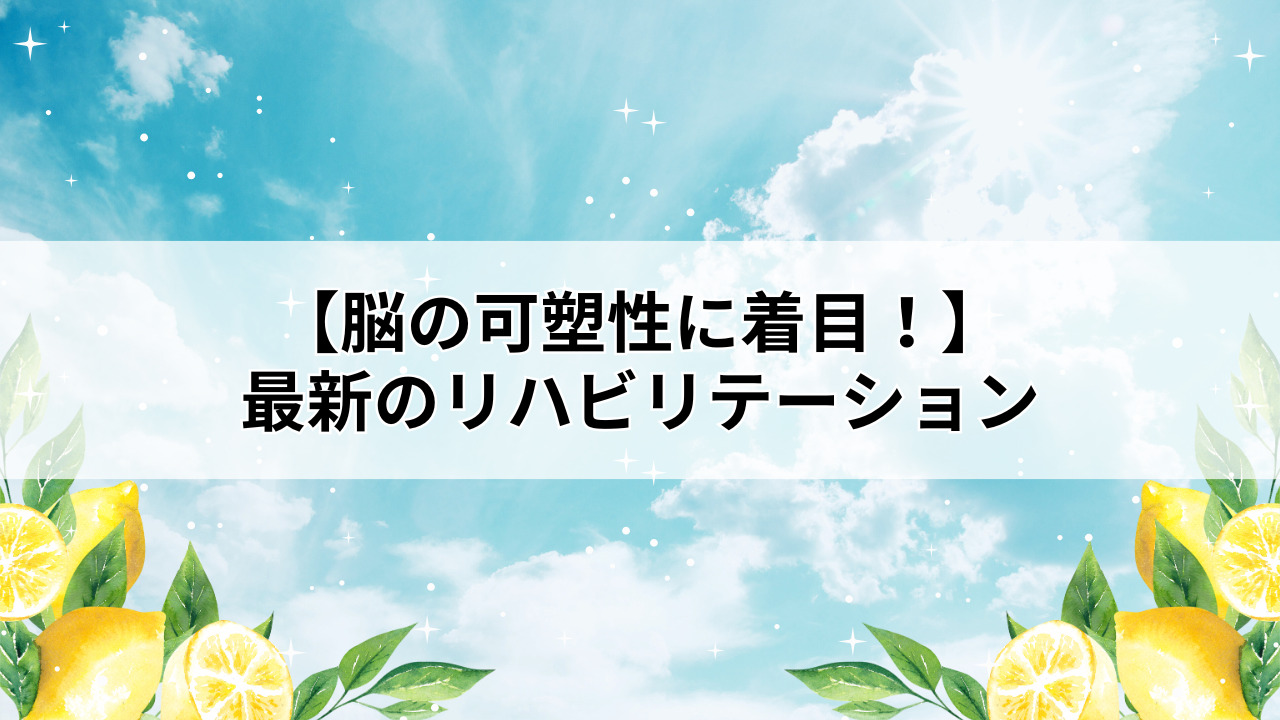
はじめに
こんにちは!
大阪府堺市中区大野芝町にある介護保険を使用しない完全自己負担型の自費リハビリで、脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・パーキンソン病・指定難病など幅広い疾患に対応しており、ロボットリハビリや型にとらわれない最先端のリハビリを受ける事が出来る「脳神経リハビリHL堺」というリハビリセンターで勤務する理学療法士です!
脳は「変化できる臓器」です。
この変化する力を「脳の可塑性(かそせい)」と呼びます。
特に脳卒中や外傷によって脳にダメージを受けた場合、脳の可塑性はリハビリを通じて再び機能を取り戻す鍵になります。
本記事では、脳の可塑性がどのようにリハビリテーションに影響し、どのようなアプローチが有効なのかを理学療法士の視点から分かりやすく解説します。
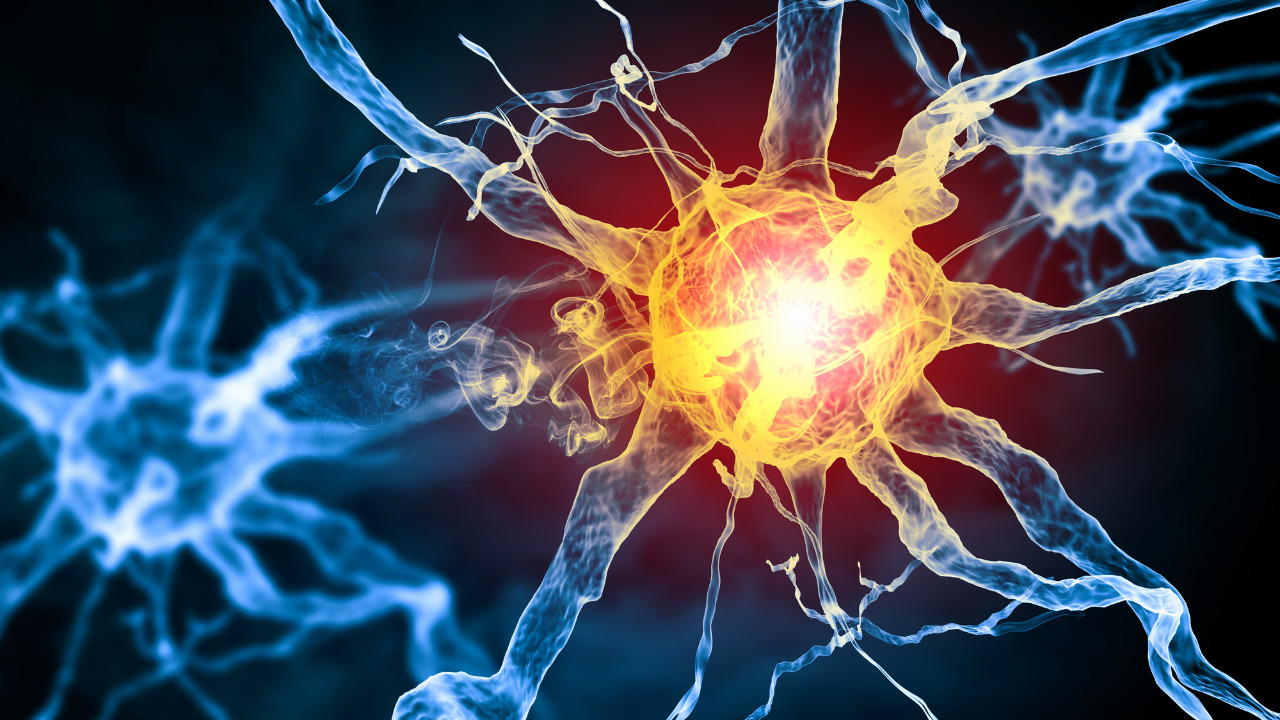
目次
- 脳の可塑性とは何か?回復の土台となる脳の力
- 回復を支えるリハビリのアプローチ:脳を活性化する刺激とは?
- ロボットや最新技術の活用:現代リハビリの進化
- 認知機能にもアプローチ:記憶や注意力の回復を目指す
- 一人ひとりに合わせたリハビリが、最大の効果を生む
脳の可塑性とは何か?回復の土台となる脳の力
脳の可塑性とは、脳が経験や刺激、損傷などに応じて自らの構造や働きを変える力のことです。
たとえば、脳の一部がダメージを受けた場合でも、別の領域がその役割を代わりに担うようになることがあります。
これにより、動かなくなった手足が再び動くようになるなどの失われた機能の回復が期待できます。
この脳の柔軟性こそが、リハビリによる回復の基盤です。
つまり、「もう元に戻らない」と諦めるのではなく、「脳は変われる」という科学的根拠に基づいた前向きな取り組みができるのです。
回復を支えるリハビリのアプローチ:脳を活性化する刺激とは?
-
早期介入とタスク特異的トレーニング
リハビリはできるだけ早く始めることが、脳の可塑性を最大限に引き出すために重要です。
特に「タスク特異的トレーニング」と呼ばれる方法は、たとえば「スプーンを使って食べる」など、日常生活に即した動作を繰り返し練習するものです。
脳はこうした実践的な刺激によって、より効率的に新しい神経回路を作り、機能の回復へとつながります。 -
運動療法による神経刺激
体を動かすことで、脳内では「神経成長因子」と呼ばれる物質が分泌されます。
これは神経細胞の成長やシナプス(神経のつなぎ目)の強化を助ける働きがあります。
つまり、運動そのものが脳を活性化し、再生を促してくれるのです。
軽いストレッチや歩行練習でも、毎日の積み重ねが大きな変化につながります。 -
制約誘導運動療法(CIMT)
「CIMT」とは、健常な手の使用を一時的に制限して、麻痺した側の手を積極的に使わせるリハビリ法です。
この方法は、脳に「そちらの手をもっと使うように」と刺激を与えることで、神経回路の再編成を促し麻痺の改善に効果を発揮します。
実際に多くの研究で有効性が証明されています。
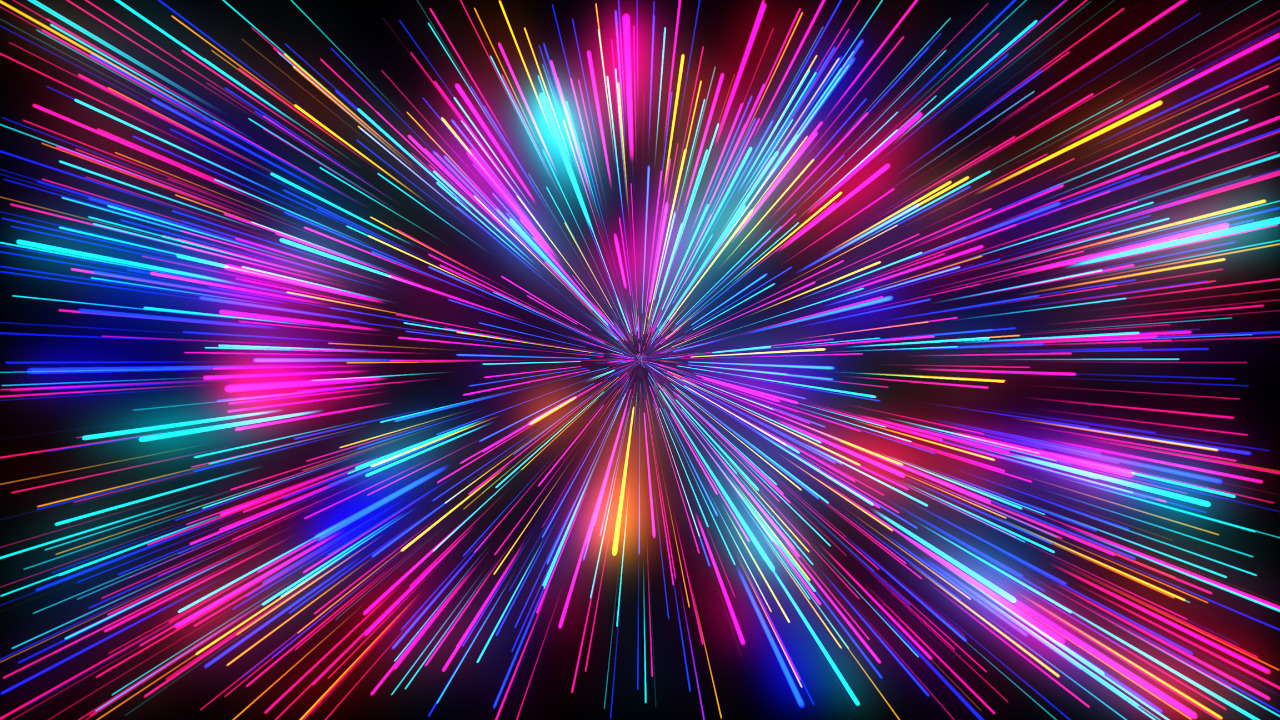
ロボットや最新技術の活用:現代リハビリの進化
-
ロボット支援療法
ロボットを使ったリハビリでは、患者さんが自力で動かすことが難しい部分をロボットがサポートしてくれます。
これにより、正しい動作を何度も繰り返すことができ、脳に「これが正しい動きだ」と認識させることができます。
反復練習は神経可塑性を引き出す鍵ですから、ロボットはその効率を高めるツールとして注目されています。 -
脳刺激技術(非侵襲的脳刺激)
最近では、「経頭蓋磁気刺激(TMS)」など、外から脳を刺激する技術も使われています。
これは、頭に磁気パルスを当てることで、脳の特定部位を活性化させ、リハビリの効果を高めるというものです。
痛みはなく、比較的安全に使用できることから、医療現場でも導入が進んでいます。 -
脳-コンピュータ・インターフェース(BCI)
BCIは、脳の信号を直接読み取り、麻痺した手足を動かす補助をする技術です。
たとえば、患者さんが「手を動かそう」と意識しただけで、その脳波を読み取り、機械が手を動かすのです。
このような繰り返しが脳の神経回路を再編成し、自力での運動機能回復を促すことが期待されています。
認知機能にもアプローチ:記憶や注意力の回復を目指す
リハビリの対象は、運動機能だけではありません。
脳の損傷によって、記憶力や集中力、コミュニケーション能力が低下することもあります。
そうした認知機能に対しても、可塑性を活用したリハビリが行われます。
たとえば、記憶トレーニングや注意力を鍛える課題、ストレス管理、会話の練習などを組み合わせる「多面的アプローチ」が行われます。
また、グループ療法では、他者と関わりながら社会性を高める取り組みも行われます。
バーチャルリアリティ(VR)を使ったトレーニングでは、より現実的な環境で日常動作を練習でき、モチベーションも高まりやすいです。
一人ひとりに合わせたリハビリが、最大の効果を生む
脳の可塑性を最大限に引き出すには、「個別化」が欠かせません。
年齢、生活環境、目標、身体機能の状態は人によって異なるため、同じ訓練でも効果の出方が違います。
そのため、私たち理学療法士は、常に患者さん一人ひとりに合わせてリハビリの内容や方法を調整しています。
定期的な評価とフィードバックを通じて、今の状態に合った最適な方法を見つけていくことが回復の近道です。

まとめ
脳の可塑性は、脳卒中や外傷などによるダメージからの回復を支える大きな力です。
運動療法、タスク特異的トレーニング、ロボット支援、脳刺激技術、そして認知リハビリなど、多様なアプローチがこの力を活用するために開発されています。
そして、何よりも大切なのは、患者さん一人ひとりに合わせた個別の対応です。
「もう治らない」ではなく、「まだ変われる」。
そう信じて、前向きにリハビリに取り組むことで、脳は必ず応えてくれます。
もし今、回復への道に不安を感じている方がいたら、ぜひ当施設に問い合わせください!
お問い合わせ
-
【堺市中区】脳神経リハビリHL堺に、お気軽にお問い合わせください!
TEL:072-349-7303
-
動画の配信を行っております!
Tik Tokアカウントはこちら
YouTubeアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。