小脳出血とめまいについて

はじめに
私たちの脳は、大きく分けて大脳、小脳、脳幹という3つの部分からできています。
この中で、小脳は体のバランス感覚や運動の調節に深く関わっているとても重要な部分です。
たとえば、あなたが「右手を上げて」と意識した時に大脳から「右手を上げろ」という指令が筋肉に伝わります。この時、小脳は「スムーズに、正確に動くように」と微調整を行っているのです。
今回は、小脳の機能を障害する小脳出血とめまいの関連性について説明します。
目次
- 小脳出血とは?何が起きているの?
- 小脳出血の原因は?なぜ出血するの?
- 小脳出血の症状は?どんな症状が出るの?
- なぜめまいが起こるの?
- 診断と治療
- 再び自分らしく生きるためのリハビリテーション
- 日常生活で気を付けること
小脳出血とは?何が起きているの?
小脳出血とは、この小脳の中で血管が破れて出血が起こる病気です。
水道管が破裂して水が漏れるのと同じように、血管が破れると血液が周囲の組織に流れ出し、圧迫してダメージを与えたりします。
小脳出血の原因は?なぜ出血するの?
小脳出血の主な原因は以下の通りです。
-
高血圧:高血圧が続くと血管壁がもろくなる為、破れやすくなります。
高血圧は小脳出血の最大の危険因子です。 -
血管奇形:動静脈奇形(AVM)や脳動脈瘤といった血管の形の異常があると血管が破れるリスクが高まります。
これらは生まれつきの場合もありますが、成長の過程でできることもあります。 -
外傷:頭部に強い衝撃を受けると血管が損傷し、出血することがあります。
交通事故や転倒などが原因となることがあります。 -
その他:血液凝固異常や脳腫瘍などが、まれに小脳出血の原因となることがあります。
これらの病気は、血液の流れを妨げたり血管を圧迫したりすることで、出血のリスクを高めます。

小脳出血の症状は?どんな症状が出るの?
小脳出血の主な症状は以下の通りです。
-
めまい:突然、激しい回転性のめまいが起こり、吐き気や嘔吐を伴うことがあります。
まるで自分がぐるぐる回っているような、または周囲が回っているように感じます。 -
頭痛:突然、激しい頭痛が起こり、特に後頭部に痛みを感じることが多いです。
ズキズキとした痛みや締め付けられるような痛みとして感じることがあります。 -
運動失調:バランス感覚が失われ、歩行が困難になったり、手足の動きがぎこちなくなることがあります。
まっすぐ歩けなかったり、物をうまく掴めなかったりします。 -
構音障害:ろれつが回らなくなり、言葉が不明瞭になることがあります。
舌がもつれるような感じや呂律が回らないような感じがあります。 -
眼振:眼球が不随意に揺れ動くことがあります。
目が左右に揺れたり、上下に揺れたりします。 -
意識障害:重症の場合には意識が低下したり、昏睡状態になることがあります。
呼びかけに応じにくくなったり、意識がなくなったりします。
なぜめまいが起こるの?
小脳出血によるめまいのメカニズムは、以下の3つの要因が複合的に関与していると考えられています。
-
神経経路の障害:小脳は、平衡感覚を司る前庭神経核と密接なつながりを持っています。
出血によってこれらの神経経路が障害されると平衡感覚が正常に機能しなくなる事で、めまいが生じます。
特に小脳の特定部位(虫部や半球)への出血は、めまいを引き起こしやすいことが知られています。 -
圧力変化:出血によって小脳内の圧力が上昇すると周囲の神経組織が圧迫され機能が障害されます。
また、出血が脳室内に流入すると脳脊髄液の循環が妨げられ、さらに圧力が上昇する可能性があります。
これらの圧力変化がめまいやその他の神経症状を引き起こすと考えられています。 -
血流の障害:出血によって小脳への血流が減少する事で、神経細胞が酸素や栄養を受け取れなくなり機能が低下します。
特に小脳の深部にある神経核(歯状核など)への血流が障害される事で、めまいや運動失調が起こりやすくなります。
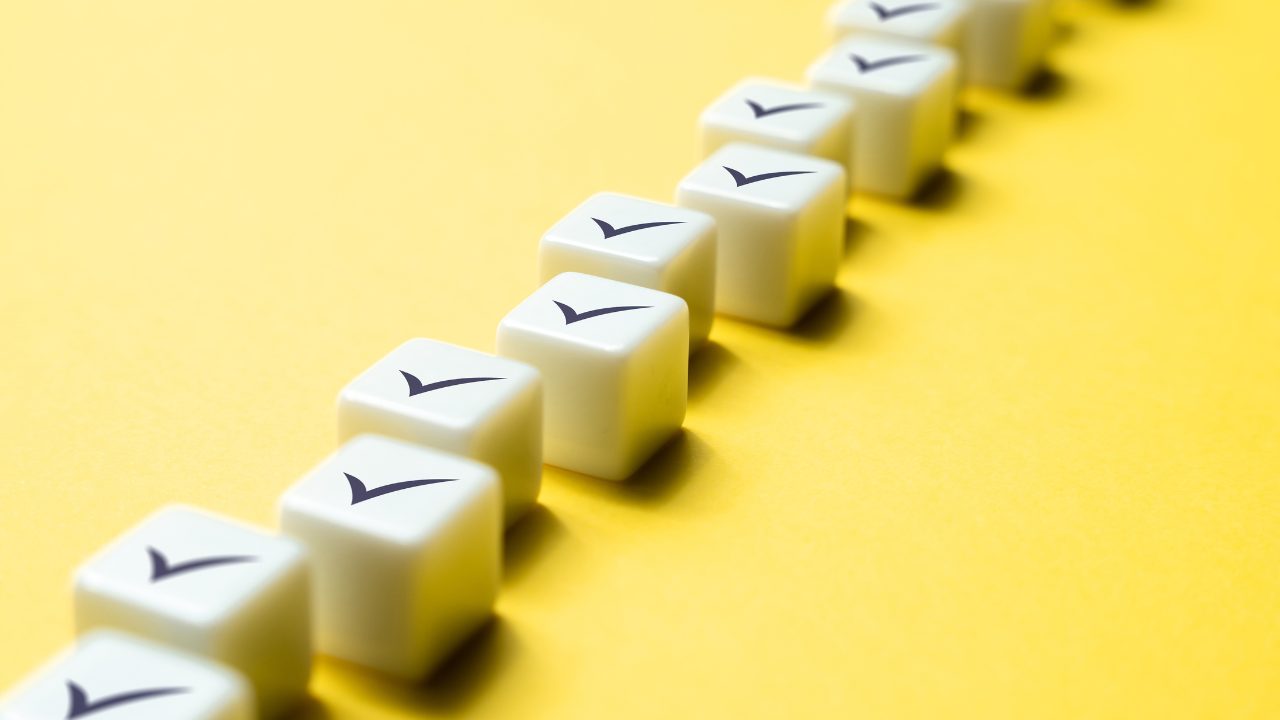
診断と治療
小脳出血が疑われる場合には、出血の原因や周囲の組織への影響などを確認する為、以下の検査を行います。
- CT検査:脳の断面を画像として確認し、出血の有無や場所、大きさなどを調べます。
- MRI検査:CT検査よりもさらに詳しく脳の状態を調べることができます。
治療は、出血の程度や原因、患者さんの状態によって異なりますが一般的には以下の方法があります。
- 安静:出血が止まり、症状が安定するまで安静に過ごします。
- 血圧管理:高血圧が原因の場合は血圧をコントロールします。
- 薬物療法:止血薬や脳浮腫軽減薬などを使用し、症状の改善を図ります。
- リハビリテーション:症状が安定した後、運動機能や平衡感覚の回復を促すリハビリテーションを行います。
- 手術:重症の場合や出血の原因が血管奇形などの場合には、手術が必要となることがあります。
再び自分らしく生きるためのリハビリテーション
小脳出血は、平衡感覚や運動機能に影響を与える可能性があるため、リハビリテーションが非常に重要な役割を果たします。
リハビリテーションは、小脳出血によって失われた機能の回復や残された機能を最大限に活用し、再び自分らしく生活を送るためのサポートを行います。
リハビリテーションの内容は、患者さんの状態や目標に合わせて様々な方法が組み合わされます。
理学療法
理学療法士は運動機能の回復をサポートします。
- バランス訓練:バランスパッドやバランスボールを使った訓練、姿勢を保持する練習、階段昇降や段差越えの練習
- 歩行訓練:平行棒内での歩行練習、杖や装具を使った歩行練習、屋外での歩行練習
- 筋力トレーニング:抵抗運動や重りを使った筋力強化、立ち上がりや座位保持に必要な筋肉のトレーニング
- ストレッチ:関節の柔軟性を高める、筋肉の緊張を和らげる
作業療法
作業療法士は、日常生活動作の自立をサポートします。
- 食事動作訓練:食器の持ち方、使い方、食材の切り方、調理方法
- 着替え動作訓練:ボタンやファスナーの着脱、袖やズボンの通し方
- 入浴動作訓練:浴槽への出入り、体の洗い方
- 高次脳機能訓練:パソコンを使った作業、計算問題やパズル、会話練習
言語療法
言語聴覚士は、言語機能の回復をサポートします。
- 構音訓練:発音練習、舌や口の筋肉のトレーニング
- 言語理解訓練:指示理解、読み書き練習
- コミュニケーション訓練:会話練習、コミュニケーション手段の提案
日常生活で気を付けること
小脳出血を予防し、健康な生活を送るためには、日々の生活習慣に気を配ることが重要です。
- 食生活: バランスの取れた食事、減塩、コレステロールコントロール、適量、水分補給を心がけましょう。
- 運動習慣: 適度な運動、ストレッチを無理のない範囲で行いましょう。
- 睡眠: 十分な睡眠時間を確保し、質の高い睡眠を心がけましょう。
- ストレス管理: 自分なりのストレス解消法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
- その他: 禁煙、節酒、定期的な健康診断、血圧管理、持病の管理を行いましょう。

まとめ
小脳出血は、めまいやバランス障害などの様々な神経症状を引き起こす危険な病気です。特に、高血圧の方や血管に異常がある方は注意が必要です。
しかし、早期発見、早期治療を行うことで、後遺症を最小限に抑え社会復帰できる可能性も高まります。
もし、突然の激しいめまいや頭痛、運動失調などの症状が現れた場合には、速やかに医療機関を受診して適切な診断と治療を受けることが大切です。
具体的な症状や治療法については必ず医師にご相談ください。

執筆者:池田
理学療法士
理学療法士の池田です。
2018年に理学療法士免許を取得し大学を卒業後、回復期病院のリハビリテーション病棟にて勤務。2021年に急性期病院の脳外科病棟にて勤務。2022年に訪問リハビリにて勤務。2025年より脳神経リハビリHL堺にて勤務となります。
回復期病院では、疾患の知識や治療技術の勉強に励み、外部研修に積極的に参加。
急性期病院では、脳外科病棟にて勤務。脳血管疾患のリハビリに従事し、発症間もなくの患者様の回復状況を予測する為の研究に参加。
訪問リハビリでは、日常生活状況に合わせたリハビリや住宅環境の相談など介入。
リハビリでは、本人様にとって安心して出来る日常生活動作を増やして行くと共に、特に歩ける生活を大事にしたいと考えます。よりよい生活が送れるように全力で援助をさせて頂きます。